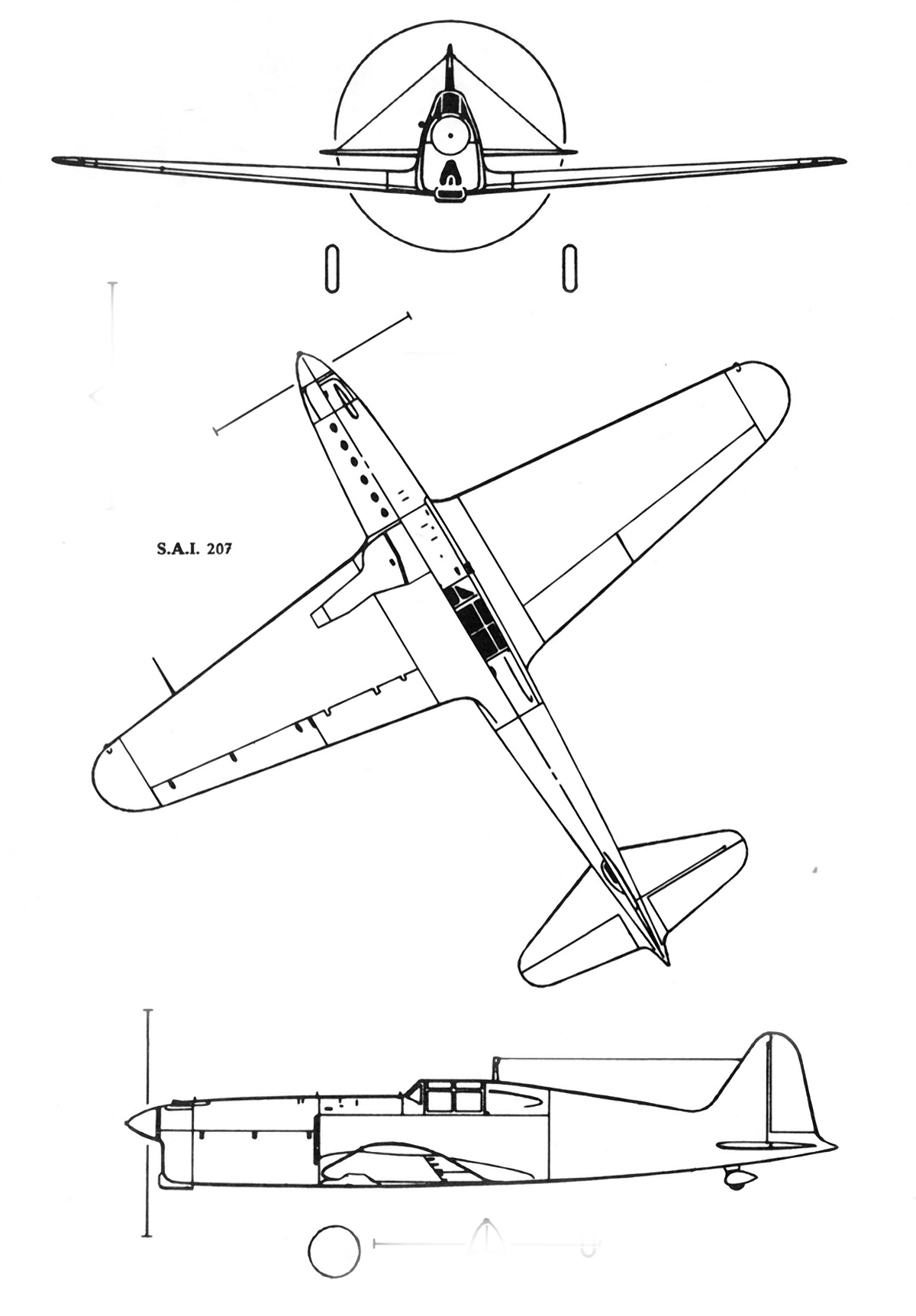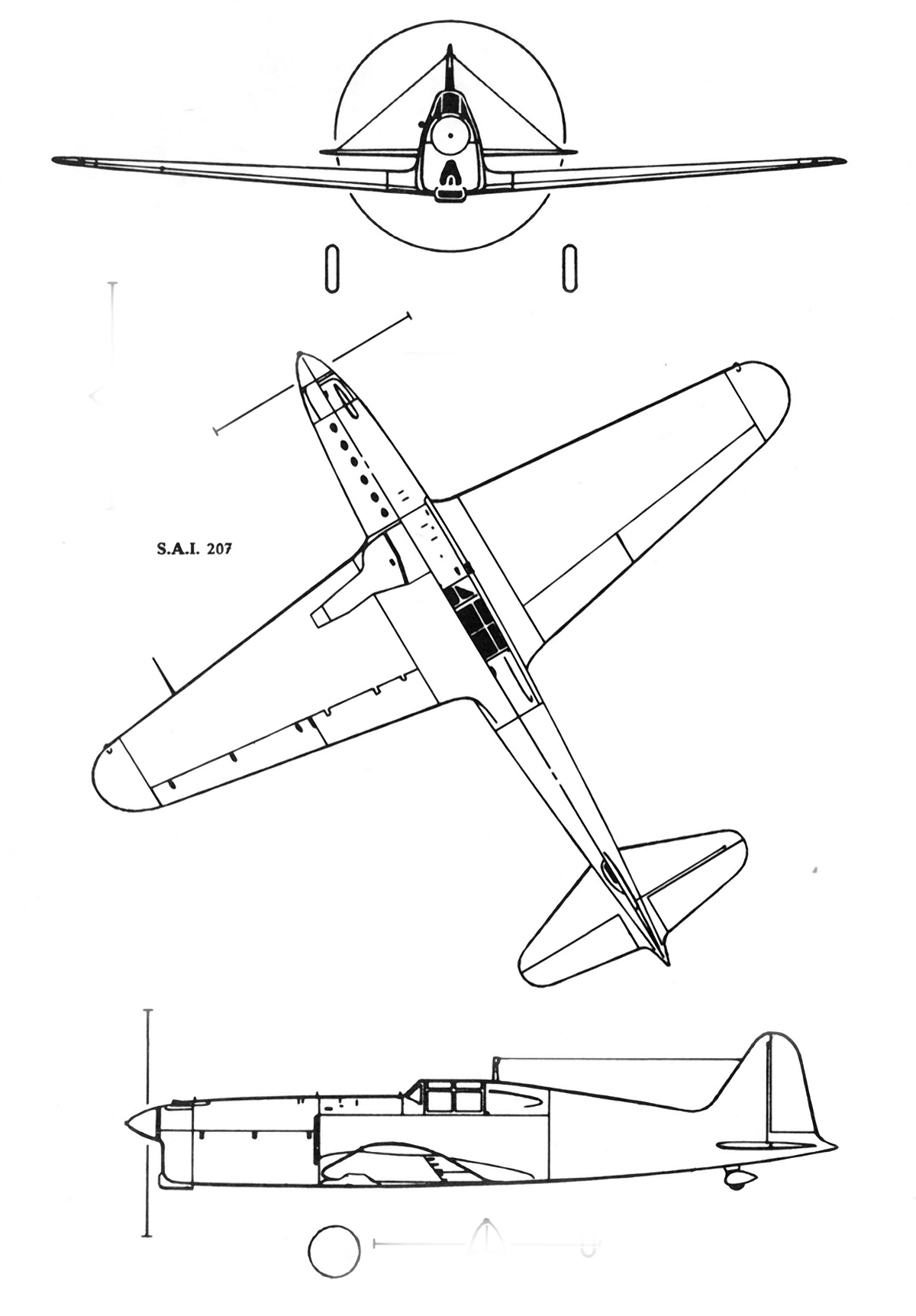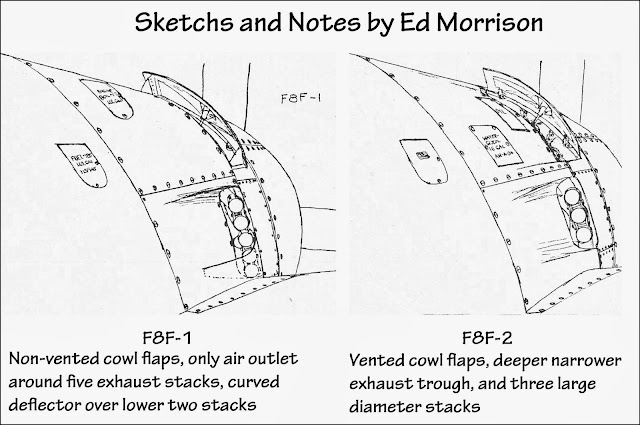�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �����p�V �Ƃ݂������:�ǒn�퓬�@���d���̂V YouTube����>1�{ ->�摜>17��
����A�摜���o �b�b
���̌f����
�ގ��X��
�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1543328863/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
>>1 ���ł��B
�ł��O�X���́f���̂T�f����Ȃ����H
http://2chb.net/r/army/1526551814 >>2 �������N�ɂ͂��̃X����������̂����H
�ǂ������ǂ���������ȂɊ��������͂Ȃ�
���͗��d���̂U�͂Q������
�Ȃ����������Ă��o�ė��Ȃ��H��X���ƂȂ��ĊC��ɖ����Ă�����
���̃X�����_�����ƂŌ��Ă�
��ߥ(ɄD`)�ߥ�
�Q�����˂�̕��Ɂf���̂U�f���Q���邼�B
���d���łڂ�
>>5 ���d�A��͂̂Ƃ���ɕʂ̋@�̂���ꂽ�������ˁB
�ł����R�@�̖��O���������̂͌������ƂȂ��ȁB
������p�t�@�����Ĕn�͑��������[�łȂ����肻������
�v���y���㗬���l�����Ȃ������̓��{�̕��������ł�
302���20�N4��19����20NA��P-51D�ɎO�@�̗��d�����Ă���Ă���B
���̎ʐ^�͌������Ȃ���������
�Ŋ��̏͌�������
http://www.naniwa-navy.com/senbotu-fukuda-hahaue1.html �u�����Ă��W�@�̒��ւQ�@�����œːi�����B���ߓG�R�@��ǂ��Č������e�ۂ�����������풆�A�p���ы@���傫������ƁA���̌������G�S�@���ǂ������Ēe�ۂ��W�������B
�R�A�S�S�Ă̒��̂��ƂŁA�Ђǂ������ł��������A���̎��̖����e�ŋ@�͋���������܂ƂȂ��ė������ė����v�ƁB
�퓬�@���l�Ԃ�����Ă͂��߂Đ퓬�@�ɐ���̂��Ǝ�������
����
>>10 ���c�@�̎ʐ^�͐��E�̌���@Vol61�C�R�ǒn�퓬�@�u���d�v�Ɍf�ڂ���Ă��܂����B
���̐�������ɏ��X�Ō��������u302��v�Ƃ����^�C�g���̎ʐ^�W�ɂ͕��c�@�̔��
�̘A���ʐ^���f�ڂ���Ă��܂����B
�����u302��v�͐��������������̂ōw�������������L��������܂�����������
�݂���2500�~������w
�����猋�\������̎ʐ^����
���a16�N�A�C�R�̓h�C�c����AHe100��A���A��s�������Ă����B
���Ⴀ�����̋����ŋǐ����낤���A�Ƃ݂Ă�40�^�͉ߋ����1����1080hp/����2000m�A�h12�^�̑S�J4200m�܂ł����Ƃǂ������Ȃ��
�A���u���V�[�jSAI 207�i����s 1940�N�j
�y�Y����w�Z�ɂ͔�e���Ă��ꂽ���d�̈ꕔ���W�����Ă���
����ꂽ�n�͂ōő呬�x�����߂�ɂ͖��C��R�����炷���߂ɓ��̃T�C�Y�����������ĕ\�ʐς����Ȃ�����̂��őP
>>15 ���̃X�y�b�N�͉R�������Ǝv���Ȃ�
��ݿ�ƴMS406��860�n�͂ōő呬�x486�L��
�ޫ����D520��910�n�͂ōő呬�x529�L��
750�n�͂�635�L���o�܂���
���Č����Ă��M�����ւ��
�v���l�Ȃ�������łȂ��ƎQ�l�ɂ��Ȃ��̂͊��o
�������[�T�[�@������˂�
>>21 �}�~�����x��960�L�����L�^�����Ƃ�������
���x�v����������
���[�T�[�オ��̒����^�E���R�ȋ@�̂ŁA����ɂ��Ă��X�y�b�N���Ȃ����A
>>23 ���₢��L�蓾�Ȃ����l������
�������Ƃ��낾����
�v���p�K���_���낤����
�����܂Ŕ�є����Ă�ƉR���Ă킩�邩��t�ɗǐS�I
���̎��̎�͋@�ɂȂ�\�肾�����炵�����Nj��^�p�ł�����?
>>26 �J�e�S��A��J�ł͉^�p���قȂ�̂ɂ��ꂪ�s���B
����͖h��킪��̂ƂȂ�ƍl���Ă����̂��˂��H
SAI207����403�����̓n�C���P�����O�H�����C�Z���X�~�������Ă��Ƃ����b��
�m���ɃX�y�b�N��������Ƌ������������x��
�@�̏d�ʂ͍ō����x�ɂ��قlje�����Ȃ����ăA���A�v���̂܂܂ʼnς����Ă����قǕω��͂��Ȃ���
>>27 ���肪�Ƃ��B
����ϖ����ȂB
�Â��v�̋@�̂𗬗p���Č��ʓI�ɗ��ʉd���オ��̂�
>1�@�����B
�NjL�FSAI207�̎���2���@�͋}�~������̈����N�������ɁA��r���e�X�y�[�X�ɓ��荞�C���̈��͂Ŕ������Ă�������B
>>33 6�炍�܂�7��30�b�͔n�͉d���炵���炩�Ȃ�D�G
�摜���猩���v���y���̍��������̓����Ƃ͋�̓I�ɂǂ��H
>>34 �|��T�C�g�̖�肾�Ǝv�����Ǎq��H�w�I�ɂ͔����Ƃ����\���͎g��Ȃ�
�����͋����ƌ����ׂ�
960km/h�̑J������ł̓\����p�̐v�����Ă��Ȃ����葀�c�s�\�ň����N�����Ȃ�
F6F-5�̋}�~���������x��796km/h
F4U-4��787km/h
���d����796km/h�ňُ�U��
����������960km/h�o�Ă�������������N������قNj�͍L���Ȃ�
�n�ʂɌ��˂��������
....�Ƃ͂����i������������Ă����j�}�~���������x�̗y����O�ŋ���������������Ƃ�����������Ă���
���̋}�~�����̃y���ߑ����Ă̂̓n�~���g���P���y���̃s�b�`�ύX�p�x��30�x�����Ȃ����
���̋}�~�����̃y���ߑ����Ă̂̓n�~���g���P���y���̃s�b�`�ύX�p�x��30�x�����Ȃ����
>>36 �\�͐펎��@�̎��̂̂��ƁH
���̎��̂Ȃ炻��͌v�Z���Ԉ���Ă��������Ő������x��1000km/h�Ƃ��Ă�
����ł���H
>>39 �v�Z�����Ԉ���Ă�Ƃ������A�u���ʕ��z�������ɋߎ������͌^������Ď������Ȃ��ƃ_���v���Ă����F�����i���E�I�Ɂj�Ȃ�����
�ǂ�ȋ@�̂ł��z�肵�Ă�ȏ�̕��ׂ�������Ε�������킯�ŁA
�Ȃ�SAI�́u�N���[���ȏ�ԂȂ�M�������鑬�x�ŋr�h�A�J���Ă��琁����т܂��v�͌��ׂƂ܂ł͌������[�Ɏv��
����Ƃ��čl����u�������������Ɛ������x�Ƀ}�[�W���Ƃ낤��A�퓬���Č����������v
�Ƃ͎v������
>40
> �Ȃ�SAI�́u�N���[���ȏ�ԂȂ�M�������鑬�x�ŋr�h�A�J���Ă��琁����т܂��v�͌��ׂƂ܂ł͌������[�Ɏv��
> ����Ƃ��čl����u�������������Ɛ������x�Ƀ}�[�W���Ƃ낤��A�퓬���Č����������v
> �Ƃ͎v������
�����l����͖̂������Ȃ��������A���������������b�ł͂Ȃ������B
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambrosini_SAI.207 >the light structure also led to problems, with the second prototype wing exploding during a dive recovery due to internal pressure built up,
> caused by the lack of internal fairings in the undercarriage bays.
��������3���@�ȍ~�͋r���e���ɓ������lj������������A�����ɏ���ڒ��s�ǂ�����}�~�����Ɏ嗃���܂��������Ă��܂������ˁB
>34
>>38 �G���W���S�J�Ńt���t�F�U�����O��ԂɂȂȂ����畁�ʂɃG���W��������
�߉�]�̓s�b�`�ύX�p�̕s�������������Ǒf�����X���b�g�����삪�K�v�ȋ@�������鎞��
�G���W�����Ȃ��悤�ȃs�b�`�R���g���[���[���ő��ɂ��Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ���������
>>41 �܂��ǂ��l���Ă��U����ƍl���ĂȂ��@�̂ɖ����������炢���B�B�B
SAI207���Ĕ��Œ肾��
�������̓v���y�����a�������Ă���ۂ�
���ֈ������݂��ۂ�SAI403 ��r�������Ȃ����H
wiki�ɂ���}�~�����x960�L���͉����Ɠ����������̑��x�v�̌��ׂƂ�����
���E�ɂ���\�����Ǝv����
>>42 ���x�s���Ƃ�����蓖���̎����Ȃ�v�Z�Ȃ肪���̕Ӎl�����ĂȂ������A�ł���
�ُ�U���Ƃ������u���̑��x�o�����炻������v
�����Ƃ������l������������̑��x���A���Ȃ�Ŏア������ア���낤��
>46
�v�Z�l�ő��v�Ȃ��甖�������Ⴆ�I�@���Ă̂͌y�ʉ���Nj����Ă�Γ��R�̔��z�ł͂�����ǂ�
SAI201�́A�p��wiki �ɂ����������l�L�ڂ�����B
���Z�Z�L���ɔ���}�~���e�X�g�i���d���j
http://ktymtskz.my.coocan.jp/J/JP/denkai8.htm ��C��R�͑��x�̓��ɔ�Ⴗ�邩���������̂ɂ����\�ȍ��x�������
�����A���^�ɂ���邪�}�b�n0.7���炢����Ǐ��I�ɉ����֒B���͂��ߏՌ��g������
�g�͂������Ĉ����N�����s�\�ɂȂ�
>>14 �����Ɋ�蓹���ĂȂ���ΐ�����Z�^�A��Z�^�Ɠ�������
1080�n��/4200m�̋����l�Z�^�A1100�n��/6000m�̋����܁Z�^�����ꂽ
������������菬�^�����̐����Ƃ�����蓹�̂��ߔj�]���Ă��܂�����
�������s���l�܂������1400�n�͂̉h�A�����ė_�ɖ�������
���̌㑱�i�܂���Me109D��E��F�݂����ȂقƂ�Ǖʂ̔�s�@�݂����Ȗ{�i���nj^�j���o�Ȃ�����
�v����ɏ����a�����@�ւ̉ߏ�Ȏ�����
�q��@�J�����_���ɂ��Ă��܂�������
������̕����ŁA�^���N���m��Ɠ������z�Ɏ����Ă��珬���a�����@�ւ̎������痣��
�ΐ��ɉ��������������Ƃɂ��\�l���ǐ�̊J���x�����Ȃ�
�܂����͏��߂���������ڂŁi�������������Ȃ��������̌^�͈�N�V�����j
�_�a���Ȃ��������A������������\�l���ǐ�̃n42���ڂ����蓾��
���ʖʐς̏����Ȕ����@��������{�I�ȂƂ����
�����^��300�n�͈����グ����ُ�U���N�������G���W�����Ȃ��āH
1800�n�͏o�锭���@�Ƃ��Ă͔j�i�̌y�ʂ���
>>15 >>19 �ō����x�̎w�W�ɂȂ闃�ʔn�͂̔�r
SAI.107 540hp/13.1�u�@41.221 560km/h
SAI.207 750hp/13.9�u�@53.956 636km/h
SAI.403 750hp/14.46�u 51.867 648km/h
Bf109�b-1 700hp/16.35�u�@42.813�@470km/h
spitfireMk.Ia 1030hp/22.48�u�@45.818�@582km/h
spitfireMk.Vb 1470hp/22.48�u�@65.391�@605km/h
Bf109F-1 1175hp/16.2�u�@72.530�@630km/h
Yak3 1240hp/14.85�u�@83.501�@650km/h
���O�@1550hp/11.�O�u�@140.909�@699km/h
SAI.107�͂܂��펯�͈͓̔�
SAI.207�ASAI.403�A���O�͏펯�O
�h�C�c�ł���A1800�n�͂̔����@������̂͗e�Ղł͂Ȃ�
�ΐ��^�̐U���͉������g��Ȃ���܂����e�͈͓������A�ΐ���܌^�ȍ~�͉���������ł������܂Ŗ��ɂȂ��Ă��Ȃ�����
�A���@�p�̐��^�X�C���̃z�[�l�b�g�A�V�T�O�n�͂��i�d�˂ɂ��ĂP�W�C���P�T�O�O�n�͂ɂ���
>>57 ����͉������W�Ȃ���
���U�ł����ɂȂ��Ă邵��
>>57 1000�n�͂Ɏ~�܂����̂�
1300�n�͂�1400�n�͂̉h�����߂Ēׂ������ʂŁi�ꎮ��V�����a19�N��ʂ��ĕs���ɔY�܂��ꂽ�j
�����R����Ă������Ȃ珺�a17�N��1300�n�͍͂s������
1500�n�͂̓P�����͂葽���̍q����������ۂ�ʼnΐ��g���s������
2���̍q�����������́A���ړI�ɂ͔R��120���b�g���A����10���b�g���A���킹��100kg�̑��ő��E�ł���
���ۂɂ͂���ōςނ̂͗��`�◃�ʐς�ς�����K�͂ȉ��ǂ������ꍇ��
�������Ȃ瓷�̌㕔�̃^���N���݂ƂȂ�A�h�e������̂ł���ɐ��\kg�����邪
�������Ƌ�����p�t�@���Ƒ������̂��㏸�͖��̋ǐ�ɑI�R��
�ʂ����Ă���ȍׂ����v�Z���C�ɂ������̂�
����ς�܂����p������ĂȂ����̐V�s�@�Ɠs���悭�����������̒������Ŕ�ׂ�
���r���[�ȋ@�́A�Ɛ�̂ĂĂ��܂����̂ł͂Ȃ�����
>>59 ���U�̂͂܂����e�͈͓��������A������̗p���ꂽ�B���ꂾ����
�����^���ˎ��́A���I�N�^���K�\��������������ł��Ȃ��Ȃ������Ƃɑ��鉞�}�[�u��
�\�l���ǐ�̖���
>>55 �ō������r����Ȃ�A�����n�͂���Ȃ��āA1-2���̑S�J�n�͂̔n�͉d�̔�r���K���ȁ@( �L��`)
�V���x�c�H�t ASh-82�͔r�C��41���b�^�[��1850�n�͂ƃX�y�b�N���猾���Ηǂ���������
>>65 �ł��������ґ�Ȃ��ō̗p�����̂��\�A�̋������Ǝv��
�����ȋ����^���A�e�ɂ��ĐV�s�@�̍X�V��ӂ邱�Ƃ͂��Ȃ�����
�����������Ă������A���̏d���đ傫�Ȕ����@�Ő퓬�@���d�グ��v���ł����̂�����
���O����R-2800���@�����čŏ��͖ڂ������Ȃ�悤�ȉғ�����
�킩���ЂƂɂ͂킩�肸�炢��������Ȃ���
�n42�Ƃĉΐ��̌��ׂ����̂܂܈����p���ŏo�͈����グ����s����o�A�o���Ƃ����������G���W���Ƃ͌����܂���
���������G���W���ȂɍS���Ă��Ȃ���
����RR�}�[�����O���t�H���͗��q�@�p�Ƃ��ĉ������˂������
�呺�x���c����������(߁��)��������!!��װ�֒�
�a���`����������߂����d(�ΐ��Ńt�H�b�P)�͂悭�������
yak-3�̂���{�̂ЂƂɁAHe100���オ���Ă�ȁB
>>74 �ȂR�~�P�̓��l���ł��̕ӂ���Y���Y�����ׂĂ�{�����������Ǔ����������Ă���>�l�ނ�����
�P���ɒn�������ĕ����ɃA�s�[�����o�����\�Z���o�Ȃ��Ƃ����A���{�̊�b�������邠��Z�b�g�̂P�������l��
�N���[�NY�̂܂�܂��ă}�W�H
�����A�O�H�⒆���A�쐼�Ɋ�b����������]�͂��Ȃ��̂ł���A
>>76 ���{�Ńv���y�������ł����̂́A���}�n�Ƃ��Z�F�n�~���g���Ƃ��A���Ђɗ��܂邵�A�����i�����B
�����̐��̋Z�p�҂̎���������ƁA
���ł́AClark-y�Ƃ��ANACA4000�V���[�Y�̗��^�̃v���y����p���āA�v���y���������̌v�Z���Ă��A
���Ă̂��l�b�g�����Ō�����B
�����̓��{�̃v���y��������A�σs�b�`�̊p�x��20�x����30�x�ɍL�����肷��̂Ŏ��t�A
�t���t�F�U�����O�܂ł́A�t�����X���`�G�̋Z�p�ڐA�ł��L�c�������B
���^���ǂ܂Ŏ肪����Ă��Ȃ��B
���������Ӗ��ł̓��P�b�g�����ɓ]�������A�����̈ꗬ�̋�͉��̈�l�ҁA
���씎�m�̎�������肭���p�o���Ȃ������̂��A�Ƃ����z�������Ȃ�B
��b������n���ɐςݏd�˂āA�[�����琶�ݏo���ꂵ�݂́A��������������B
>>78 ���������ƈ�R���ꂻ������
�A������VDM��`�F�v���y���𗃌^���ƃt���R�s�[����Ƃ������z�ɂ͎���Ȃ������̂��낤��
>>73 �������铷�̂Ƃ̊����^���́H
��������n�܂鎸���͑O���Ƃ��Ċ��m�ł��邩����S�Ƃ���Ă��H
�t�B���b�g�̐����Œ����ł��鎖����
�|���̂͂����Ȃ藃�[���玸������ꍇ�ł���
�����[�����Ȃ�Ă܂���������������玸�����ĕs�ӎ��]�N�����p�^�[��
�o���@�̃i�Z���X�g�[���Ɨ��d�̓��̂���������ɂ��Ă邯��
�o���@�̓��̂͗��d��肸���Ƒ�����
TAIC���|�ɂ��A���d�̎����͑O�����Ȃ����f���͈����Ȃ��͑����Ƃ���
>>81 �o���@�͒��������瓷�̂Ƃ̊��͋ɗ͗}�����锤����
����������n�܂�ƈ��S���ǂ����͂�����ƕ����肩�˂�
�܂��z���̈Ӗ����o�Ȃ��̂ł͂��邪�A�؋�����l���đw���������ׂŖ�肾�����炱��ȂɎ��O�ɕ����肫���Ă����̂ɂǂꂾ���Ԕ����Șb���Ƃ������ɂȂ�
�ƂȂ�Ɠ��̑����^���̂����R�ł͂Ȃ�����
�ΐ��ɑ��Ă����܂ő������Ă�Ƃ͎v��Ȃ�����
�{������w
>>82 �֏悵�ĉ����������Ă݂��
���ʂ̋��ᗃ�@�ł͐��ʐ}�Ō������̂Ɨ���ʂƂ̊p�x���k���ɋ߂��̂ɑ���
���d�͑����̂����Łڎ��Ƃ������u���ɐ����Ă�
���ꂪ�������ɉE��]���ł���v���y���㗬�ɐ�����u���ɂȂ��Ă���i�������j
�R���Z�A�̋t�K�����i���j�Ɠ������������N�����₷���ꏊ�Ɏv����
����ɑO�����a�̏��������w�����̂����ō��u���̕��������O�������C�ɋǕ���������̂ł͂Ȃ���
�����̈���o�Ȃ��ϑz�ł���
m(_ _)m
�ΐ�22�C���ł��瓋�ڂł������ȑ���
�O�H�Ƌ�Z���͂Ȃ������{�I�ɕ������ԈႦ�Ă��Ƃ��������悤���Ȃ��ȁA����
�I����Ă�ȁB����Ȉꌩ���ĉ������ȃI�J���g���_���ԂɎ��x�z�B�͉e������₷���q�B�������낤��
>>88 ��Y����̓V�R�F���{���ȁB
�D�G�ȋ@�̂����������ݏo�����G���W�j�A�����܂���
�T�����ŏ������݂���Ă�z���������Ă��B
�u�D�G�ȋ@�̂ݏo�����v�҂�����v���Ă����̂͂����̃}�E���e�B���O�Ȃ�
>>89 �����G���
�e�����Y�v���@�𐬗��������z��Ɠ����j�I�C������
���˂ɓ쒩�N�̎��Ɍ��т��邠���蓜���̋^���������
wiki�ɂ́A
���������������Ƃ́H
���킸�ɍ̗p�����̂���肾������
�v���y���㗬�͎��k��
>>96 �R��ׂ���]���Ńy�����Ȃ����Ƃɂ͑����ᗃ�̑��c�������킩��Ȃ���
���������킩��Ȃ����Ƃ�O��Ɏ������Ă��
������ꂽ�I���Ǝv��
����Ńv���y������Ƀu�b�g�����̂��T���Č㗬���ז�����͔̂���������ȁ[
>>93 �ő�g�͌W�����]���ɂ��Ē�R�ጸ��}�����̂��w����������
���ʂ̗��`��莸���������͎̂d������
�ő嗃�����O�ɂ����đO�����a���傫�����`�ɂ͂ǂ��撣���Ă����ĂȂ�
���d�Ƃ��Ă͗��[�͕��ʂ̗��`�ɂ��Ă���玸�������Ɂw�z���x�͂��Ă�
�ނ�����L���ׂ��͕\�ʂ̕��������ێ��ł��Ȃ�����w�����̌��ʂ͎�����Ƃ����_
�f�����b�g�������c���
�������ێ��ɏd�ʂ������Ă܂ł�鉿�l������̂��Ƃ����^��
�v���y���Ď������Ȃ����Ď�����̂��ˁH
�@�̂̍R�ׂ͂�Ƃ��͂��ĂȂ��������Ď�������
�������ōČ���������͑S�����ł���̂��y����
�����������ċ�C��R�W���͂��Ȃ�悩�����炵�����˂��c�c
���ł̍����̎����@�i���O�ƈӖ��������Ⴄ���ǁj������Ă��
�Ƃ���ł����A�˂�
>>105 �k���N������Ƀ~�T�C���ɉΐ��Ɩ��t���Ă�̃��J�����
���d�̑�������
�x�z������Ɏ����ꂽ�����ɂ悭������
>>107 ��������������
�t�H���g���Ɠ�����
�g�o�����ӂ���
����@�ŋ�����藃�ʐς��������̂ɍő呬�x��90km/h�����D���łȂ��\�l���ǐ�
>>112 ���d�͗��C�R���ʐ퓬�@�Ƃ��đ���₾���
�C�R�@�Ƃ��Ă͑��Z���Ă����R�@�Ƃ��Ă͏\���Ȃ��炢����
���́[�X�~�}�Z��
�a���`��߂ď��c�e�C�X�g�ɂ����犄�Ƃ���
��m�b�œ����ɂ����Ɣw�L�т����悤�݂����Ȕ��z�����A�Ƃ���������t�w�L�т����̂����炠��ȏ㖳��
�w�L�т���Γ]�шՂ��Ȃ�A���R��
����ȍ��]�݂͂��Ȃ�����A�Ƃ��ƂƐ����ɂ��ǂ蒅���ĐU�����𑁊��ɉ��������G���W��/�v���y����ς��d���A1�N���葁�����퉻����ĂĂق��������B
�U�����Ŏv���o��������
>>84 �̑������A�n43�ςދC����������Ƃ������Ă邯�ǁA
�v�͍ŏ�����S�R�i��C���Ȃ����Ă��Ƃ��H
>>103 >�����������ċ�C��R�W���͂��Ȃ�悩�����炵�����˂��c�c
��������Ǖ����ł̊���̐��l�Ȃ킯�ł���
������G���W�������ł��@�̂̋�͂͑S�R�������ĂȂ����A
�������������܂������Ӗ��Ȃ��������ăI�`���t���Ă�����
�͌^�ɂ�镗�������̐��l�ł�
������_�ɑ��ď\������������
>>124 �_���o�͊z�ʊ��ꂵ�Ă��킯�ł��A�ŏ����犷���̗]�T��������
�ł����@�̍����������킯�ł��Ȃ��A�_�O��ő��܂�������
���v�Ɛ��\���Z�������������������łނ���
�����ŏ�����n43�z�肵�Ă��犮�S�Ȏ��s��ɂȂ��Ă��������c
�ł����̕t�߂����Ƀv���y���㗬�Ƃ��������Ⴎ����̗�����łǂ�����čČ����邩���Ă̓����˂�
���d�̓����������Ă����Ă�F6F�Ƃ��Ƃ���قǂ͕ς��Ȃ��ˁH
���C�Â������ǁAFM-2���Ĕr�C�ǎ����F6F�ɋ߂��v�ɉ��߂Ă��
�����Fw190�ɉe����F8F�������ǁA���Ȃ藐���}���ӎ����Ă��ۂ�
>>128 F6F�͂��Ƃ���R-2800�i���a1,321 mm�j����Ȃ���
R-2600�i���a1,397 mm�j�ɍ��킹�Ă���
���ƃ^�[�{�`���[�W���[�̓��ڌ��z���ĉ����X�J�X�J
��[�������S�̌����⒆����A���U�͂�����������A
>>131 �t����
�����lj߂����B�C���e���߂����Ɣᔻ����Ă����B
�����Ɋ�Â����a���`�u���_�v�ɍS�D����
�����P���͂�����Ɣ����Ă���Ƃ���������Ă��낢��G�ȏ�蕨����鎖�����������ǁA�_��
���_��͖a���`�͐������A�����猋�ʂ��F�����Ȃ��Ă��ʂ�������I�A�Ԉ���Ă���Ȃ痝�_����ؖ����Ă���I���ꂪ���d�`�[��
����ʼnߒ��͂ǂ�����A���ʂ��F�����Ȃ��A����͂����H�A�ׂ������R�̉𖾂͌���I�A���ꂪ�����P��
������ΏǗÖ@�I�ȑ[�u��ǂ��Ƃ��邩��
�Ⴆ�Γ��I�̋r�C���ʼn��Ovs���̘b�͗L������
���̏ꍇ�����́u�w�p�I�Ɂv�������͉̂��O��������
14���ǐ���A���Ȃ킿���d21�^�̎���@�̏����̎�����s�ł�
>>120 ����t
�A�����J���אڋC��or���p�ʒu
>>133 �_�����@�ł��U�����o�ē����悤�Ȃ��Ƃ����Ă����炵��
�܂�A��͐��\���]���ɂ�����������ɂ�鋤�̉���
>>125 �܂��^�]�����̍�������_�͊z�ʊ��ꂵ�Ă��Ǝv��
�@�̂����ł����i���������łȂ��N�\�����j�͎̂���
���d������������(�G���W���ւ���)���c�ɂ��Ƃ���
>>136 �ꎮ��͗��ɗ��ł���
�ŏI�I�ɐ��\�͈ꏏ�ł���������N�x��
���ʼn��������g���u���𗤏�@�̈ꎮ�킪��N�x��Œǂ�������
�ꎮ��̑���ɗ����̗p���Ă�Γ�����͐����Ɗy��������
�\�������Z�i�����Ă�����������Ȃ�
�悭������ƌ�����O�^�����Ď��ۂ͔����@�g���u��������������
�����ė��53�^���G���W���قړ�����������퓊������Ă���g���u���������
�����^�I�~�b�g���Ď��퓊���ς݂�����w�[�L�w�[�L�I>53�^
>>137 �\����Ȃ珮�X����c�����Ȃ�
���ꂱ�����R�̖{���ŁA�ꎮ�͊��ҊO��̍�i�ł����Ȃ�����
i-16��b�T�[�𗤌R�e�C�X�g�Ɏd�グ���̂����c
���c�ɉΐ��A���͔r�C�ǁB���ꂱ���\��ɂ͕s��
�����m�Ő키�Ȃ痋�d�B
���Ƃ����Ƃ��V���{���X�P�[���ł̔�r�������Ӗ�
>>140 �\�������A�j���[�M�j�A�͔�s�ꂪ�����̂ł��ꂱ���͐킪�~�����Ȃ���
���ׂł͕ČR�̊͏�@���劈��ł����i�܂��ē��{�Ɨ�����j
���������肭���ȓ��{�p�C���b�g�����a����������������A�V�^�@�̓����ɃP�`���t���B
����x�e�������R�����邩�炶���
F4U�Ɣ�ׂ��痋�d�Œ����͊y�Ȃ��̂������炵���B
Bf109�͎����J�̃X���b�g����������A�������̗g�͑����i�������x�ቺ�j��ڎw���Ă�B
>>137 ����Ⴀ��ꂪ���C�ōX�ɔ����@�̌}�������˂���Ȃ��������͗ǂ���
���A�܂��ꓖ����Ńp�C���b�g���ƔR�������
���̂ɔR���z�u�����X�ɍŏ�������h�e�S���t���̔�
�ČR�퓬�@�ɂ܂�Œʗp���Ȃ�7,7mm�A��������̂���Ȃ�20mm
�}103���nj�͑�12,7mm�ɑΉ����ƂĂ��s���̂����@�e�ɂȂ�����
�[���U�^�̎��_�ŗ�킪��킵�Ă�F4U���G��������
�V�^�Ɏ����Ă�F6F���畔���P�ʂň��������A����ł��w�ꏏ�x�Ƃ����̂��H
���Ղ���}�Ȗh�e�lj��ʼn������㏸���݂��Ȃ�R�ł��Ȃ��Ȃ�������
���Ղ���I�Ղ܂œG�@�ɑR�o���ėł��傫���s���ɂȂ邱�Ƃ����������������H
���̂��߂Ɍ���ƕt�������������悤��
�U�^���f���߂��������ŇV�^�������܂ŕ����ғ����ɂȂ��ĂȂ�
>>146 F4U�͗�킩����ɓ�G�Ƃ݂͂Ȃ���ĂȂ���
��ʂ��}�����������L���Ƃ��������ł���Ȃɗ���ĂȂ�
�C�R�͍�킪�Ƃɂ�������Ő�������Ȃ������ɍq��U���ɓ]��������
���������m�Ŋ�P�����肵�Č����䗦��������
���R�͊�n�Q�����p���Ė���������A���펞�ɂ͋@���W���ɐ������Ă�
�X�ɕ����������̂͋@�̂̐v�Ɩ��W�����i���R�ŗ����g����13�~��������ȏ���j
����ɒ��͋�̏ȗ����l������Ζh�e�����̏d�ʂ��z���ł��邵
���R�ŗ����̗p���Ă�Ε���2�{�ň�N�����o�ꂷ��̂ɂ͕ς��Ȃ�
���������������C�R�����ɘa�������H
���͎O��^�܂ł͗ǂ��������A�ܓ�^�ȍ~�͖��炩�ɓݏd�ɂȂ��Ă�
���͐푈�ɏ��������̂�������ܓ�^�ȍ~�̃V���[�Y���g��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ƃ��낾��
�_�̐U���͔R���͋ψ�z���łȂ����H
�X���^�C�Ƃ͊O��Ă��܂����A�ΐ���1500�n�͂���ЂƂ���т�1800�n�͐����^�ɂȂ������A�h��930�n�͂���1130�n�͂������1300�n�͐����^�ɂȂ���
���ƈꎮ��̏d�ʂ̍��͋@���̔R�����ڗʂƕ������傫�����Ȃ̂�
>>132 �a���`���_���̂��̂�NACA������̂���ł���Ȃ�ɐ��E�̃g�����h�ɂ��Ȃ������
���̌�u�v���y�������������Ă��Ȃ��H�H�v�ɂȂ��Ă��܂��C�ɂ���Ȃ��Ȃ�����A
�n�͂ʼn���������
���{�͂��̕ӂ̌������ʂ��A�����ɂ����������n�͑���Ȃ��̂��Ђ�����@�̑��ʼn��Ƃ����悤�Ƃ�������
>>154 �C�R�����Ăɂ��Ă��̂��܂��ɂ���
���\�肾�������ǂł��Ȃ������i���R�̕������a19�N�ɂ��ꍞ�݁j
����������܁Z�^�ւ̊�����肻�����̕����������Ă̂œ��ւ̊����͌������Ă��܂���
>>157 �ΐ����s���Ȃ�������Ƃ����p���ɂ��������ĉh�������x�ꂽ�Ƃ����璆���̑Ӗ�������ނ��肾
>>155 �E�B�L�y�f�B�A�̏��͐M�p�Ȃ��
�������h�̗����o�͂��o�L�ڂ���
�ꎮ���^�̎��d�Ƃ��Ēm���Ă���̂�1729kg�B1975kg������ق猩���邪�d�߂���
����ς������◃�ʐς��ł����y��
���̑���ɋ}�~���������x��600km/h(�ƕ����ă}�j���A���ɂ͗v650km/h�Ƃ����邪���̗v�������Ӗ����邩�͕s��)�ŁA�t���[����������
>>149 �����Ă������}103��C�M�ǂ������Ă���������ȁH�e��̌݊����������H
�����������Ƃ��Ă��C�R�ɉ�قǐ����ł����Ƃ͎v����
������G���W���p���[�������Ƒ��b�ɕ����ē݂��Ȃ������Ȃ�āc
>>152 �����Ȃ�Ɖ��ł����𐄂����ǂ�w
�����A���ꂪ�Ȃ��Ƃ��ĉ������\���D�G�ŏ㏸�̗͂ǂ�(�����x�𖡕��ɂ��₷��)
�ō��������d���ɕ��ԇV�^��I�Ȃ����R�͂Ȃ�
��킿����F6F����������悤�ɂȂ��Ă���o�����āH
�@�̂̐v�Ɩ��W��������
�n�C�I�N�^���K�\�����������ł��Ȃ����_��
>>160 �����Ƃ痤�R�ɂ����Ĉꎮ��Ɨ��̂ǂ������̂�ׂ����������̘b�����Ă���
�Ȃ�ŊC�R�Ƀz103���]�T�̗L���̘b�ɂȂ邩�킩��܂����
��킪�ꎮ��̑���ɍ̗p����Ă���
�z���ƕs��̉����A�ʎY�̈ȍ~�͈�N�����Ȃ�
�����͔{���ł������A�h�e�����͋�Ȃ��Ȃ�͈͂Ŏ��܂�����
�G���W���p���[�����Ĉꎮ��O�^�Ɠ����^�C�~���O�ŋ����ł����i�Ƃ͂��������͒x�����ғ����͂���ϒႭ�Ȃ邯�ǁj�ł���A�Ƃ����b
>>163 �嗃�͂��Ƃ�蓷�̂ɂ�12,7mm�Ή��h�R�^���N���H������ǁH���͑��u���Ă���Ȃɏd���́H��
�h�e�����Ńt�[�t�[�����Ă邶����w
�Δ����@�͖{�����̎d������Ȃ����炻��Ȃɂ���ȁ[���A�����[���A����܁[
�܂��@��20mm�Ȃ�ǂ��Ǝv�����ǂ�w
�[���P�N�����Ƃ��{�C�Ŏv���Ă�H�����낪�������琔�����₵���悗
�����̋����͋i�ق̉ۑ�ňꎮ��Ɠ����v�҂�
>>164 �ꎮ��̔z�����Ɣ�ׂĂ݁H
�������ꎮ��͕����z����̋���������
�����т̎��̌�A���C���I���Ă���ΕĐ���}�������ɑ���
�ꎮ��͂���ɑ���������ǂ��s���Ȃ��܂܁A�͂邩�ɏ��Ȃ��z�����œ����������}����
>>166 �����u���R�̍ő吶�Y�͂��ւ�E�`�̐��Y���C������Ɋ����Ă�������犴�ӂ���v
���x�����x�������Ă邪����Ƃ̔�r�ł����ď������͔ے肵�ĂȂ���
�����AF6F�Ɏ�������o�Ȃ��Ȃ��Ă�̂ɂ����݂��ăp�C���b�g������
�����Ƃ����Ɠ������̔��̕����悭�ˁH���Ęb
70kg������
>>169 �ŁH��s�����Ɍ��I�ω����������Ƃ����̂����H
���N���X�̃^���N�̉��ǂ����L���Ő�����������Ƃł��H
�����Ėh�e�����t���ŃX�s�b�g�ǂ��锹�Ɍ������ė��_�ɂȂ�Ƃł������̂�
>>168 �ꎮ��̕����ǂ����т��c�����̂͗��R�̍q��@�J���̕��j�ƍ�킪�ǂ���������ł́H
�֓����ł̖h���ł͈ꎮ��͂��܂芈�ĂȂ���ۂ����ǂǂ��Ȃ̂�
���ƂĐ��ƑԐ��������Ȃ�F-6F�Ƃقڌ݊p�ɐ킦��
�ꎮ�킾���Ė��R�Ɛ��I�̂܂܍U���𑱂����藣������ܒ@���ɂ��ꂽ�����I�ɕ����Ă��܂�
>>171 �����ŃX�y�b�N�ɏo�Ȃ��������̍����������Ă����
�܂��\�Z�̃A�z�ɐU��ꂽ���ɂ������̂͂��邯��ǂ�
�ł����Đ���������܂������C�R�ƈႢ�r���}���ʂɎc����Ă��̂�������
F6F�͋�B���ʂ̂������Ƒ����A�t��B-29�̗��铌���ɔ��̏o�Ԃ͂����Ȃ�
�Ԑ����s���ł����s����F6F���낤��������锹�������Ƃ������Ď��ɂ�
�������̐퓬�@�����Ă�Ƃ��Ȃ�����w�����邾�����ʂȗ�ł���
�_���Ȃ������Ă�����������l����ɂ���������
�ꎮ��͂����@�̂����C�R�ɐe�E����ĎR�{�j�N�V�[����̉ߏ�ȃu�T�グ���ăo�J�Ɍ������
>>174 ���ŃW�W�B�M�҂��ȁH��
�ނ���m��Βm����C�R�X�L�[�����{���Ă����l�����Ǝv�����ǁc
>>171 ���͂܂Ƃ��Ȍ�p�@�Ȃ�����d���}���d�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��傫��
�ΐ퓬�@��Ȃ炠�����܂Ŗ����ȕ��������͕K�v�Ȃ���
�ꎮ�킪�i����ɓ����Ă�Ƃ�����A
>>176 ���ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂͋��̗e�ʂ��傫��
�����ł����䗦�����Ȃ����A��������Ŏg�����ɂ��㏸�͂ɂ��s����������
�ŁA�Y�܂ꂽ�̂����d�����ǁc������ď��c����_���Ȃ́H���Ęb��w
�`���ɂ���Ă͉Η͂��\�����Ȃ���
���P�̂ł�F6F��F4U(���x����)���}�V�����Ǐ\���G���̔��e
�Ȃ��A��Ԍx�����ꂽ�̂�P-47�A���_��P-51
>>177 ��䂳�̈�_�łȂ�Ƃ������Ă�P-40�Ȃ͎����Ƒg�܂ꂽ���Ƃň����n���ꂽ�`�ɂȂ���
���Ƃ����ĉ��������őR���悤�ɂ������t���Ăėe�Ղɂ����Ȃ�
�Ȃ��A���̃R���r�̈�Ԃ̓G�͉ғ�����������
>>176 ���̏ꍇ�͏�@�������^�U���@�����ނł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�
��n�q����łȂ�
�ΐ퓬�@�퓬�����C���Ƃ��闤��b�퓬�@�Ƒ�^�@���}�����鉳�퓬�@�ɕ�������\�肾����
����ǂ����ۂɂ͒P���@�����Ă���ɂ��ܓ^�̉Η͂����߂��邱�ƂɁi�����F-6F�ւ̑R��j
���{�̋Z�p���̂��̂Ȃ�
>>181 ���Ƃ����ăh�C�c��Bf109(DB605���ڂ�)�ғ���30%���x�������Ƃ����邵�A�O�g��50%�Ƃ������b
�ĉp�����ŕ���Ă������������A���ɏ����Ă��ꂽP-51���G���W���̕s���K�[�Ƃ���������Ɏg���Ă���
B-29�̃G���W���s�����L�����낤
��������܂��������������A���ꂪ�傫������ꂾ���o���鐔������Ă��邩��
���Ȃ݂ɐ푈�]�X�Ō����\�A�����ȊO������Ă邾�낤����
>>153 ���d�̃y���͋�͂��Q�l�Ɍ����������A�ʉ_�͏I�풼�O�Ɂu�{���̔��^�v���y���v�����Ă��Ŏ����o�܂Ō����Ȃ��Ă�̂͊m��
>>158 �h31�^�̎��p���x��͐ΐ쓇���h�̎��̂ɂ��C�R�R���̒x�ꂪ����
���R�̐����^�t�n115-2��44�N�Ăɂ͎���ɏo�Ă�
���㉻�����͓˂����܂�
�ʍ쒼�s����Ȃ���
�_�ɔ��^�v���y���t�����瑬�x�オ�������Ă͈̂ȑO�������тꂽ���ǂ̖{�ɂ���̂��~����
>>184 �L���ǂ��낾�Ɩx�z���̑����e
���s�勳���̘_���ł��o�Ă���
�C�R�Ɉ�ԕK�v���������̂͏d�����̊͐킾������Ȃ�����
7.7mm�Œ�@�e���闤�R89���ƊC�R97���͒e�̌݊�������������}�E���g�͂قڈꏏ�������炵�������
>>186 �h�O��^�͎��s�����̂ł́H
�O�^�͎����@�݂̂ŏI�����������B
>>187 ������ǂ���������
�Ȃɂ��z103�͒e���y�����玊�ߋ�������Ȃ��ƃ}�e���݂ł����܂�Ӗ����Ȃ�
�t�ɐڋ߂���ΗD�ꂽ�e�����y���e�Ńw������Ԃ���
�����^�h�˂��c
����悩�����Ȃ�炸
�Ђ≈�C�B����\�A�R�@�������������Ɏ���
>>186 ��̎��ǂ��납50���a�~6���З͂ƌy�ʐ��ŗ������z�I�ȕ������Ǝv����
�����1300�n�͂̔����@������F-6F�Ɍ݊p�ƊC�R�͍l���Ă���
���^�@����ɂł�7.7�~���ł͂����Ƃ������ς̐�P����J�����n�߂��ɂ��Ă�
���R�ɔ�ׂĎ��Ԃ������肷�����͈̂�̂Ȃ����̂�
�z103���C�R�ł����Y����Ηǂ������̂ɂƂ�
����邱�Ƃ̏��Ȃ�IF������
�鍑�C�R�ƂĐ퓬�@�̕���������
>>193 ��C�M�ǂ��Z�b�g����Ȃ��ƊC�R������Ǝv�����A�\�����邵
�t�Ɍ�����C�M�ǂɖڂ�t�����C�R�̂��̂����o�b�N�A�b�v�����烏���`�����H
���邢�͋t�Ɂu��\�~���@�e�͐퓬�@�ɂ͕S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��v���ʂ��������
���₻��IF���Ɠe�͂ł��Ȃ���
>>195 �z103�ő�^�@�������肾�������R�ƈႢ
�C�R��13�~�����y���e�͋��߂ĂȂ��̂�
7.7�~���̑���œO�b�e�ƏĈΒe�����ł����炭�͉䖝�Ƃ������ƂɂȂ肻���ł�
>>198 �y���e�����Ă����̑ΓS�H���Ȃ̂ɔ�������7,7mm�Ƒ卷�Ȃ��悤��w
>>199 �O��13�~�����y���e���Ȃ�����
�ł�20�~���@�e���Ȃ�����Ȃ玎����邩������Ȃ�
�����C�R������20�~���@�e���y���e�Ɠ��������\���̐M�ǂɉ��ǂ���闬�ꂩ��
��C�M�ǂ͂ǂ�����ł��o�Ă��锭�z�ł͂Ȃ�����
G38�����J�[�X������4���d�����@�̐��Y�̎��ɃG���R��20�~������e��������Ȃ�
7.7�~�����Ɩh�e�]�X�ȑO�ɊO�ɒe���ꂽ��
>>200 �O���͉����o�ꎞ�����ȁc
20mm�Ȃ��y���e�͂S���@�ł��Ȃ���Ηv��Ȃ��C������
�C�R�ł͑Ώ��^�@�ł��S�����@�ɑ���7.7�~���͂��͂���p�����Ȃ�
�y�������̒��팻�ۓ��ԁA�{��18��56���z�@��������t�e�n��}�@�g���[����������ǂ�Ȕ������邩��
http://2chb.net/r/liveplus/1545444404/l50 >>203 �I�`�L�X�̑�@�e�̒e���g���Ƃ���
�V�u���v�Ȃ̂�
�J����X�}�[�g�y�ʂőg�ݍ��킹���a�V�ȃz103���
�Z�p�I�ɂ͊ȒP�����Ȃ���Ȃ�ł��x����ł����
������ւ�̎���ɂ͋���������
�P���ɍq��@�e�����Z�p�͂����������Ƃ���
99��20�~��1����23�L��
����100���e�q�����
99��20�~��1����23�L��
1930�N��ɓ��������ł���x���g���e��20�~���@�e�̓\�A�ɂ����Ȃ�
�ꍆ�e��P-40��B-17�̔R���^���N�ɑ���
>>211 �������o���Ȃ��x���g���e���o���Ȃ��G���R��FF�͗ւ������ĕs�����������A����������
������\�A�͖ڂ����ꂸ�A�h�C�c�����{���R���s���������瑼��20mm���J���������A�C�R�����Ƃ��x���g���e�͂����
�j���ŗv�������Ȃ������ȏ�A���R�ő�X�I�Ƀ��C�Z���X���Y����Ƃ����I�����͂Ȃ�
����͎��v������Ȃ�ɖ������Ă����̗p�����
>>213 �x���g���e���������ł��Ȃ��̂̓C�X�p�m��20�~������������
������1930�N��̓\�A�ȊO�̍��͂ǂ��ł�
�ǂ����Ă�20�~�����~������C�X�p�m���G���R���̃��[�^�[�J�m��
�܂��̓G���R����FF��FFL�����Ȃ�
�������C�X�p�m�̕��͊��ȃJ�o�[���e���܂ł��Ă��˂Ȃ炸
�嗃�ւ̎��t������
��������G���W�������Ȃ���20�~�����K�v�ƍl���Ă���I�����͂قڂȂ�
���������R�͂��������@�֖C��13�~����B-17��������Ǝv���Ă���
������ʂɃx���g���e�⓯�������ւ̂�������20�~���@�e���̂Ă��킯�ł͂Ȃ�����
13�~���ł���d���Ă₾�Ɩ���͌����Ă���
>>214 �����炳
���̃C�X�p�m��������������A���P���ꂽ�킯�ł���H�C�M���X������s������������
����܂ł̌q���Ƃ��ăh�����e�q�œ����o���Ȃ��Œ�@�֏e���悵�Ƃ��邩�́A���{���R�̌��߂鎖��
�N�̌������́A�����̋@�֖C�ł̓\�A�ȊO����������ۂނ����Ȃ��A�Ƃ������̂�
���R�Ƃ��Ă͌�ɍT����z5������ȏ�A�x���g���e���h�����e�q�ɂ��o���Ȃ��G���R���̎�͉��ɋ����������Ȃ��͓̂��R�̎���
���R�A�s�����ȃC�X�p�m��FF��FFL�̗��R�̃��C�Z���X���Y�����蓾�Ȃ�
>>215 ����1930�N���20�~���@�֖C���~�����Ǝv���Ă��痤�R���G���R����I�Ǝv����
�ǂ��̍����ł�����[�^�[�J�m����~�����������ǂ�
�����ăC�M���X�����đI�������Ȃ����炵�炭
�h�������e�����Ɏ��t���ɂ����C�X�p�m�ʼn䖝�����킯��
���R�̏ꍇ�A�q���������ΕĐ킪�n�܂�܂�13�~���ł����Ǝv���Ă��킯��
�͕�Ƃ����ƊȒP�ɕ������邩�������
�{�i�I�ȃG���R����20�~���@�e���ł���
�ꉞ���a15�N������J���͂��Ă��z103�̊g��ōς܂��悤�Ƃ�����
�M�����ŃG���R���ɓ���y�Ȃ�������
�o������a19�N�܂Œx�ꂽ
�Ƃ����̂�����
�J�^���O���\�͂�������
�@�֕����ł����ė��ɂ͓��ڂ��
�ߑ�������ŕ~�����S�̏d���ŃG���R����ƒe����݂ɏd��
���c�̗��ɐς߂�A�@�֕��̏����ȃG���R�����������痤�R�͂����Ԋ���낤
>>216 �s��̗v���������˂��A
����Ȃ��ƌ�������G���R�����͂邩�ɒᐫ�\�̗��R20�~���@�֖C�̐��X�͂ǂ���������́A��
>>218 ���̃G���R���Ɣ�ׂė�邩�̊�͐l�ɂ�邪���Ȃ��Ƃ��u�G���R�����y���ɒᐫ�\��20mm�v���������Ƃ������͖w�ǐ��Y���ꂸ���܂��ɏI����Ă邾��
�\�A�͖����Ƃ��āA���ǗA������MG151/20�y�уz5�̓o��܂ŁA��X�I�ɐ��Y�������قǗ��R�̖����̂����@�֖C�͓o�ꂵ�Ȃ������Ƃ������ɉ��̕ς����Ȃ��̂���
�w�ǃ{�c�ɋ߂�������Ă��邻�����ǂ����Ă���H
>>217 ����A20mm���~�����ƂȂ�G���R����~�����������낤�A����Ȃ��āA20mm�ȗv����������̂��Ȃ�����20mm��~���Ȃ�������
�G���R��������Ί�H�^�����o�Ȃ炢����ł��������
����Ȋ���Ȃ�Ȃ��������Ȃ����������l����
���R�Ƃ��Ă�20�~���@�֖C�͒��炭�o���@�̑����܂��̓��[�^�[�J�m���i�ł����炢���ȁj�ł���
>>219 ���R�����ۂɃz5�܂ł̌q���ɂ����̂��z3�Ƃ������_�Œm���ł���
���ꂪ�G���R������������c�̏����ȗ��ɂ��ς߂邵�͂邩�ɍ����\����
���R���Ȃ��G���R���̓������������Ȃ��������Ƃ����Ƃ��ꂪ�ł��鎞���ɂ�
�P���퓬�@�p��20�~���@�֖C���������y�����Ă�������ɑ��Ȃ�Ȃ�
���[�^�[�J�m���ɂ͋����������čw���A���ڋ@���J��������
�嗃�p��20�~���@�֖C�͂��������K�v���ƌ��ʂ��Ȃ�����
���ꂪ�S��
���R��20�~���@�֖C�J���͊J�n���x��
>>221 �����猾���Ă��A�z3�͓j�����炢�ɂ����ς߂Ȃ����S�R���Y����ĂȂ�����B�q���ɂ��Ȃ��ĂȂ�
���R�̓z5�̕��ɒ��͂��Ă����ȏ�G���R���ɖڂ������킯���Ȃ�
���R���������ł�20mm�@�֖C���~�����Ȃ�A�z103�̊J���̎��_�ŁA�u���_��12.7mm�e�ł͂Ȃ�20mm�e���I�肳��A�J�������܂邾���̎�
�z5�̓z103���{�A�A�b�v�������̂������
>>223 �ڂ�����Ȃ��������A���a15�N������G���R�������悤�ɂ���ɖ����Ȃ�
����̋@�\�������o���Ȃ�����
����Ƃ��ᐫ�\�𗝗R�ɋp���������t���ł�����́H
�u���[�j���O�n�̊g�傪��������܂ł̓G���R���̐��\���ǂ�����ǂ����悤���Ȃ�
�d���Ȃ������C�����̒ᐫ�\�@�֖C�ɗ��炴��Ȃ�����
20�~���@�֖C���Ȃ��̂Ŏ����C�����̒ᐫ�\�@�֖C�̎�����肽����������
���ڂł���@�̂��R�����̂Ő��Y�����L�тȂ�
�����ĒP���퓬�@�̕����Ƃ��Ă͊����i�A���ȊO�ɉ������邷�ׂ��Ȃ�
�{���̃z5�ł���
�z103�̌o�����������̂�
�z���͏��a19�N�ŕs��͏I��܂ő���
�����Ȃ�20�~���Ƀ`�������W���Ă���S�邽��L�l��
���������嗃�ɐς߂Ȃ��ł���������
���c��������7.7�~���ɂȂ����܂�
�z5���嗃�ɓ��ڂł����͎̂l�����
>>224 API�u���[�o�b�N�̐����o�����������������
���������O�^�܂ł̓e�������l�Ȃ���
�ނ���z3�̕����y��
���Ǘ��R���z3�ɖ������Ȃ������ȏ�A���O�̂���FFL�������l�Ȍ��ʂɂȂ��
��Ńh�����e�q�ł����ł������Ȃ�A�������ł�20mm�~�����Ȃ瑽���y�ʂȃz3��100���e�q�p�ӂ��邾������
�ނ��낱�����̓N���[�Y�h�{���g�ɉ��ǂ��ċ@���ł�����
>>226 ���������G���R���͐�O���珀�����Ȃ��Ƃ��������I�����ɂ͂Ȃ�Ȃ���ł���
�����āA�z3��100������e�q�⓯���������ł���Ȃ����Ă��I
���ꂪ�ł��Ȃ������J������
����FFL�͐퓬�@�̎嗃�ɓ��ڂł���Ƃ����̂��傫���i�Ƃ��������ꂪFF�AFFL�̎������j
�K�R�I�ɓ��ڂł���@�̂�����
�������������������K�v�Ȃ�
�z3�͑o���@�ɂ������ڂł��Ȃ��̂ŁA���Y��������̏������ꂽ
�����������ł��Ă���A�S�R�]���͈�����̂���
>>227 ����100���e�q���J������Ȃ�������������
�������Ă̂��ǂ����玝���Ă���
�G���R�������čŏ���60���������킯�ŁA���̂܂܃x���g���e�ɔ��ł�����u100���e�q�͖����������v���Ď��ɂȂ�̂��H
�N���[�Y�h�{���g�����Ɏ����Ă͈Ӗ��s��
���ꂪ�o���Ȃ��l�Ȃ�V���[�g���R�C���̃}�L�V���n��u���[�j���O�n�͑S���_���ɂȂ�
���Ǘ��R�̗~����20mm��̌�������z5�ɂȂ�킯�ŁA30�N�ゾ�낤���j�����낤�����������܂Őv������z5�ɍs�����������Ȃ�
>>227 ���ƃz3�͏d�ʂ�43kg�Ŕ��ˑ��x��300��/min50������
�o���@�̓��̖C�Ȃ疽�����̌��オ�x�����ˑ��x�����ė]�肠�邪
FFL�i29kg�A480��/min�j60�`100���e�q�Ɣ�ׂĂǂ����Ƃ�����
FF����2��ς߂Ă��܂��d������
FFL�n�̃x���g���e�����ł�40kg���y��
>>229 FFL�y�߂�����
FFL��38kg�A�����܂ł����API�u���[�o�b�N�ł����������y���Ȃ�
�\�A��B-20�݂����ɕ��@�\�݂��ăK�X�I�y�ɂ��������y���Ȃ�ꍇ������
�z3��32.63kg�̏d�ʂȂ̂ɏ���880m/s��FFS�ɋ߂��З͂̎�����g���Ă�
>>228 ���ےe�q��傫�����悤�Ƃ��Ă��I��܂łł��Ȃ������ł���
�N���[�Y�h�{���g�ւ̉��������ۂɂł��Ȃ�����
����Ȃ̂ł��~�����Ȃ̂�
�G���R���𐫔\�𗝗R�ɐ�̂Ă邱�Ƃ͂Ȃ��ł���
�������x�����č��Ȃ������̂�����
�h�������e�����炢��ˁA�����ł��Ȃ����炢��ˁA�Ƃ������f�ł͂Ȃ�
�������G���R���������Ă��Ă��z5�͎��������낤����
����Ƃăx���g���eFFL����Ɋ���������ǂ����������ȁH
�z5�͏I��܂Ŏ��̂���������
>>230 38kg��FFS
�܂��̓x���g���e�Ŕ��ˑ��x��750��/min�܂Ō��サ���܌^����
�Ȃ���Ȃ�������FFL��29kg�Ȃ�ł���
�������y��
�l�b�g���ɗ��肷���Ȃ��悤��
>>232 ������j���̋@�炢�ɂ����ς܂�Ă��Ȃ�����N���[�Y�h�{���g�ւ̉����͂��Ȃ������������낤��
��͂ɂ͊��Ƀz5�����܂��Ă������
����Ȃ̂ł��~��������Ȃ���
�z5����C���M�ǂʼn��P���ꎟ��s�v�ɂȂ���̂��A������̎�͋@�֖C�Ƃ��ĕʓr�ɑ�ʐ��Y������킯���Ȃ����낤��
����ɏI��܂Ŏ��̂����������Ƃ����Ȃ�܂��ʂ̗v������
�}�e�̑����̌��͑�ς݂����A�����̗����Ȃ�G���R���ł��N���肤��b��
���ۂɋ�㎮�̍o�������d���̃G�[�X�@�ɋN���Ă�̂͗L���Șb����
>>234 �b�����ݍ���Ȃ���
���R�̓G���R���𐫔\�ʂŌ��������̂ł͂Ȃ���
�G���R�����ᐫ�\���ėp�������ȋ@�֖C���̗p���Ăł�20�~���@�֖C���~�����̂�
����͑o���@�ɓ��ڂł�����̂����p�ӂł���
�z5����������܂łȂ����ׂ��Ȃ������Ƃ����b�����Ă邾��
�z5�����邩�瑼�͂���˂���A������ᐫ�\�̂͂���˂���A�Ƃ������f�ł͂Ȃ�
��������z3�͂����������Y����Ȃ�
���ƃ}�e���낤��膅���͋N�������Ă���
��㎮20����z103���M�Ǎ\�����i���ꂼ��ʍ\�������j���߂Ď��̂����炵���̂Ƃ�
���炩�ɈႤ
>>235 �z5�����邩�瑼�͂���˂���A������ᐫ�\�̂͂���˂���A�Ƃ������f�ł͂Ȃ�
��������z3�͂����������Y����Ȃ�
����A��������Ȃ���z3�͂��̒��x�̐��Y���ɂƂǂ܂�Ȃ�
�����Ȃ����̂̓z5�̑��݂���
���x���������P���@�p�̌Œ�@�֖C�Ƃ��ė��R�̖����̂������ʂ��o���Ă��Ȃ�����̗p����Ȃ���
�G���R�������������Ȃ�̗p����Ă���
���ۗ��R���G���R���̓����̌o���͂���
���R����������ɂ̓x���g���e���K�v�Ȃ�
���x���������z3�͑o���@�̓j���������B�I�[�v���{���g�̕����D�܂���
�P���@�ɐςނɂ͋@���A�x���g���e�A���̓�����߂��Ă������Ɖ��疵�����Ȃ����A���ۂɒP���@�ɑ��Ắu�G���R�����ᐫ�\���ėp�������ȋ@�֖C���̗p���Ăł�20�~���@�֖C���~�����v�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ�
���ƃz5���o�����N���������Ă����Ƃ����͉̂����\�[�X�ł�����̂��ȁH
>>236 ���₾���痤�R�͒P���퓬�@�ɂ͍ڂ�Ȃ��悤�Ȕėp���̒Ⴂ���d���ᐫ�\�C���̗p���Ă邶��Ȃ���
�G���R���ɖ��������Ȃ�̗p���Ă��Ƃ������Ǐ��a15�N������ł�
�G���R���̐��\���ǂ����ꂱ���ʎY����̂͊C�R�̑S�ʋ��͂��Ȃ���s�\�ł���
�����ĊC�R�ɂ���Ȃ�Ƃ�͂Ȃ�����
���R�ɂ͒P���퓬�@��20�~���@�֖C�Ƃ��ċt�Ƀz5�ȊO�̑I�����͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂�
20�~���@�֖C���~��������������Ȃ��ʼn߂�������Ȃ��Ȃ���
�P���퓬�@�Ɋւ��Ă̓G���R�����U�R���C�Ƃ�����֍瓾��ꂸ
�P�C�݂�����40�~���@�֖C���炢������܂킷�n���������킯��
�z5�͓��̖C������ۍŌ�܂�膅���O��ŋ@�̂��v����Ă������Ƃ��番����悤��
���炩�Ɏ��̂̔����p�x�̑z�肪�Ⴄ
��㎮20���̏ꍇ�A膅���\�h�ŏe�g��j���Ŋ����Ă��������͂���3�N�O�ɁA�M�ǂ̕ύX�ŏI�����
���x���������z3�͑o���@�̓j���p������̗p���ꂽ��
>>237 �z5�̍o���������Ă������̃l�b�g�ɗ���߂���Ȃ��̌����Ă�����A�o���̕����ς�炸�オ���Ă���Ƃ��ł͂Ȃ������̏؋�����̑z�����I�H
�O���͂��ꂠ�肫�Ő��Y����Ă��邵�A�ǂ��Ƃł������邾�낤
�l���ɉ��߂đĂ����Ƃ����؋��������ė���Έꔭ����
>>239 �l����͗����Ȃ��
�ǂ����悤���Ȃ��ł���
���̂Ŕ�������̓}�V�����炻�����Ɉڍs���Ă�
�����������̂ɍڂ������Ȃ����炠���Ȃ��Ă�킯��
�܂�����������r������[�܂��Ă������A�̗p����Ȃ�������Ă̂͒P�ɐ����̗p����邩����Ȃ������Ď��������Ă���̂��ƌ�����ĂȂ����낤�ȁH
�̗p����邾���Ȃ�G���R���͂Ƃ��̐̂ɗ��R�ɂ���������Ă�
����Ȍ��t�̃A�������Ă����̂��H
���O�͒P���퓬�@�ɐςނ��߂�FFL���ʐ��Y���ǂ������ƌ����Ă���낤���B����ɂ��Ă���B
>>240 �z5��150���A����ł����ˑ��x���l����Ώ\���Ƃ͌����Ȃ��̂�����A�@��Ƀz103��350���͏\���L����l���Ƃ��Ă͕s�{�ӂƂ��~�ޖ����Ƃ͌����
����Ɏ����̊J�������͂܂��}�e�̌�������������
�������͏؋�����Ȃ��Ă����Ƃ������̂������Ă��Ă���ƌ����Ă����
���R�����������G���R����FFL����Ȃ������オ�S�R�Ⴄ����Ȃ����I
���[�^�[�J�m���܂��͎嗃�pFFL�AFF
>>242 ����Ⴛ������FFL��苭�͂ȑ�����g���Ƃ͂����A�ʂɒP���@����Ȃ����x���g����Ȃ��Ă������ł��Ȃ��G���R�������č\�킸�̗p���邺�H�H������������b��������Ȃ�������Ď�����I�H
���Ǝl����͂��̗��z�̃z5�~4�ɍŏI�I�ɂȂ��Ă邶����H
�l����Ŕ����@���|�͉��߂Ă��܂������H
���ꂪ�ǂ����ł͂����肷�邾��H
�l�b�g�ɗ���Ȃ��̌�������A�W���ł����������ė��邩�ƌx���������A�������͏؋��͊��ق��Ă���
�O�����^����45�N1���Ő��Y�I�����B�}202��44�N�Ă̌�t�J�n������������O�������̋��^�}�e�̍Ɉ�|�����˂Ă�Ƃ��A���[������ł��A�����B
�d��Ȗ�肾���ɏ؋��͊��ق��Ă���
���ꂾ���������Ă���Ȃ�̏\�{���\�{�ł��オ���Ă邾��
�펞���͍��݂����Ɉ��S��͌������Ȃ�����ɑΉ�������ǂ���������s�v�ɂȂ�����
�L12���̗p����20�~���𑁊�����^�p���Ă���ʔ��������̂ɂ�
�㎵�킮�炢������������A�N�`���G�[�^�̏d�ʃP�`�邽�߂Ɏ蓮���̈������r�ɂ�����悩�����̂�
>>247 ���{�̃`�n�A�h�C�c�̃��b�T�[���c
Fw���q�������Z������㏉��P-47�����ˑނ����Ȃ���
���d�̓h�C�c�Ȃ�B-17����Ɋ���ł��������킩����w
�L27�͂��̂܂܂ł��\������Bf109��n���P�[���Ɣ�ׂĂ��p���������Ȃ��㕨���Ǝv���̂���
>249
�n���P�[���u�X�s�b�g����A���Ƃ�낵���v
�p�R�X�s�b�g�͓��{�����ĂɈꌂ���E�Ȃ�Ă��Ȃ����B
>>252 (�c�R�C�c�˂����ݑ҂����H����A�������c)
�c���[�cE�^���X�^�Ƀ{�b�R�{�R�ɂ��ꂽ���D�u�Ɠo�ꂵ�A(�����̑O�Ȃ狏�Ă��ǂ��Ɋ|����)
���������������Ǒ��肪�\�ɂȂ�ABf109��G�^�ɂȂ钆
Fw190�͐퓬�����@�ɂȂ�ΐ퓬�@�\�͂�S���������Ȃ��������ǁc���삪�������Ђ�H
�ł����ăI�[�X�g�����A�Ȃ̃X�s�b�g�͊i����܂����Ȃ��������ǁE�E�E�E���@��@���@���@���@�Ё@��@�H�H�H
>>253 �N���Ⴂ���܂����Ă��B
�_�[�E�B���̃I�[�X�g�����A�R�̃X�s�b�g�͂Q���܂Ŋi�������Ă����B
�P���ڂ͑o���������đ��Q�o���B�Q���ڂő呹�Q�ĂR���ڂňꌂ���E�ɐ�ւ����B
�r���}�̃C�M���X�R�͈ꌂ���E�����Ă��Ȃ������̂̓r���}�q���ǂ߂킩��B
>�R�C�c�˂����ݑ҂����H
���₢��B�N�̃��x�����Ⴂ�����B
�������m��Ȃ����Ɠ˂����܂�đ��l�m��������͎̂~�߂悤�ˁB
�n���P�[���u�X�s�b�g����A���Ƃ�낵���v
�ꌂ���E�Ƃ����T�O���́A�C�M���X�Ƃ��h�C�c�ɂ������́H
�ꌂ���E���_�ō��ꂽ�̂�Bf109�����
���͂Əd�����ň�C�ɃP��������̂�Fw190�̂ق���
�X�s�b�g�t�@�C�A�͈ꌂ���E���ӎ����Ă��͂Ƃ������A�����̂��A�ŗՊC�}�b�n���������ċ}�~���ɓO����Ǝ苭������������
�i������������͈̂��|�I�ɑ�������������
>>262 �����̈Ӗ���������������Ɍ����Ȃ��ƈӖ�������
(�C�M���X�̏ꍇ�����S�ƋR�m���̖ʂ������Ƃ͎v����)
�����@�}���Ȃꌂ���E�͂܂���������ȁA����Ă�Ԃɔ����@���ʂ����Ⴄ
�ꌂ���E�ŏ\�����j�\�������蕡���̍U���ł������̐퓬�@������Ɣ��f�����܂ł�
������Ȃ��}�E���g������^�~���̃X�s�b�g�V�L�b�g���Ƃ����f���A�[�g�ȕ����̓����~���҂�ǂ���
�\�͐�̔C���͍U���@�̌��ނƊϑ��@�̑|��
�X�s�b�g�ɋ��Ƃ����̂������̋�R�̉^�p���Ɉ˂�
���{�Ƃ��ẮA����Ȏv���オ��̒��_�ɒB���������̕@���ւ��܂��Ă�����̂����A�ǂ����ޓ��͎U�X�����Ԃ�ꂽ�����炪�i��Ǝv���Ă���炵��
���┹�����ȃX�s�b�g�t�@�C�A�A�F�X����낤����
���[���b�p�ƈႢ�A�q���n���m������Ă���
>>250 A6M��F6F�F���ւ��o���ςȂ��̋����@�͖ق��Ă�I
>>252 �|�[�g�_�[�E�B���̃X�s�b�g�͍ŏ��̐퓬�ŗ��Ƀh�b�O�t�@�C�g��Ń{�R��ꂽ
�̂œ���ȍ~�͈ꌂ���E��@�ɐ�ւ������ǂ���ς�{�R��ꂽ��H
���̕ӂ̓p�C���b�g�̎��̍������
>>272 �@�̂��}�~���Ɍ����Ė����̂��������
���x���o�Ȃ��Ƃ�����Ȃ��U���Ƃ����̂�����
���Ƃ͒��r���[�ȑ��x���Ɛ�Ԃ����Ƃ����ʂɑ_����Ƃ�
����̉������s���Ɠ��Ɍ����A���̕ӂ͌o������
�r���}�Ɍ��ꂽ�̂�Mk.8���H
�v���ΐ�n�͖����̃G���W���ň�������ɂ��Ă͗��A��������
�o�g���I�u�u���e���ɂ͊Ԃɍ���Ȃ���
����ڂ��G���W����������ł�����
���͔{�̔n�͂̌㔭�V�s�@�Ɣ�r���Ă�����Vx�㏸���ł����̂��푈�����ł��킦�����
>>275 ���͋�ɂǂꂾ�����҂��Ă�
���낹��̂̓t�b�N���炢����
�����������͑Βn�U���ɂ͌����Ȃ�
���ő����킯�ł��Ȃ���
�R���^���N�����Ĕ�e�Ɏア��
�V���G�b�g���傫��
��G�@���ŗ��O�ɃV������邮�炢�ؚ�
�y�ʉ��̂������
�ނ����b�l�ł�������
�����̃V���ƃV�������킹�ăV����
���ĕ��d�̃R�}�[�V����
>>258 �ꌂ���E��[���A���x�����Đ��a���i����܂ł̕��t�@���j�ł�������Ƀp���[������Ԃ�A
����L���㉺�ɂ��g���Ĕw���_���܂���A���Ă���
�ǂ�����Ȃ��Ȃ�����u���C�N����̂͂�����b��ł������Ȃ�
�����Ƃ�Me109�͉ʊ��ɐ���킩�܂��Ă����炵�����ǂ�
>>279 �Ȃ�ƒ��͋����70���L���O�������팸�ł�����H
�N���V�[�����낹�A�܂藤�R�@�Ƃ��Ă͂����Ԃ�y���Ȃ��Ƃ����킯��
���ꂪ�͏�@�̃n���f�Ƃ������
����@�Ɗ����Ό�ǂ��̑����ȗ��ł��Ȃ肢���邵
���̕��Ő퓬�@���݂̖h�e�|�A�h�R�^���N���\��
�Βn�U���@�^�Ȃ炠����x�̔�s���\�ቺ���Â�őS�^���N��h�R���邱�ƂɂȂ낤
����ł�Ju87���A������ׂ�
�����ċ��x�R���]�X�͔����Βn�U���Ŋ������Ƃ��l�����
���������̂���
���̕����A�@�̎��̂͂�킢���ǁA���h�ɗ��̉��ɔ��e������Ĕ��
�쒀�͂����Ă������
>>281 �͏�@�̃n���f
������͐v�i�K���畉���Ă��镨�ł��낹�Ȃ����̂ق�������
�r���t�b�N�����̎�t�������̂����x���グ�Ă��
���낹��ƌ������͋�70���L���̓����������
���e�˂�����ᔚ���͂ł��邳
�����Ă邩�ǂ����͕ʂ̘b�����ǂ�
���̔C����p�ɐv���ꂽ�@�̂ɔ�ׂ��
���낹�Ȃ��n���f��w�������@�̂͗�炴��Ȃ�
�R���^���N�̖h�R���ЂƂ���Ă����������U���ꂽ�^���N�͖��炩�ɑ�
�S���̏d���ł���e�ʐςł��^���N�e�ʂł�
>>282 ������������^�Ɠ��^�ł��炢�Ⴄ�����H
���낹�Ȃ��n���f�������������Ă邩�ۂ��ł����Ⴄ�Ƃ�������
��p�@�]�X���A���Ǒ����퓬�@���痎�Ƃ��̂������Ƃ����̂�
���ł̌��_��
�����]�X�ȑO��Ju87�Ɩh�e������픹�ł͌�҂̕������肪�����Ǝv�����ǂˋ�₾��
������p�@�͎���ɑΊ͍U����Βn�U���Ő����c��Ȃ��Ȃ��Ă���
���͋����ȗp�ꕷ�����������ȂƎv������w
>>285 ����������e�^�̑����Ǝ��d���ׂĂ݂悤��
>>284 ����������p�@�𐄂��Ă�킯����Ȃ�
�z�[�J�[�^�C�t�[���̂悤�ȋ@�̂����z���ƌ��������̂���
�͏�@�Ȃ�X�J�C���C�_�[
�퓬�����@�Ƃ��Ċ���P47��P38�����͍����x�퓬�@����
�^�[�{�ߋ��킪�����Ă��
�C�����[�V���̏d�h�e�P���U���@�ɂ̓A�����J�������������Č�����������
���ǂ͑����Ƃ������_��
>>286 �Ȃ�70���L���̓��e�����邶���H
���ʘ_�������A�����n�ɂ͗����������s�v������
>>287 �������L���Ȃ̂��C�ɂȂ������玩���Œ��ׂ������
�ł������������K�d�ʂŔ�ׂ��59kg�����ς��Ȃ��������ǁc�i�O���@�ƈ�ܔ����@�j
���Ȃ݂ɁA���̓�@�̂ōS���b�ȊO���Ǝ嗃��ݑ��u�A�r�ʒu�x�����u�A�r��]���y�⏕�������A�ԗ��ݎ~�b�A�����ɏՑ��u�A���}�p�蓮�|���v�����ʒu�A�������^���N�e�ʕӂ肪�Ⴄ�݂�������
�����ǃl�b�g������������������ƕύX�_�����肻��
>>282 �d�ʌy���Ŗ��ɗ����Ȃ��Ƃ��ꂽ�����@���~�낵�Ă邭�炢�����痤���n������
�@�̂͒��̓t�b�N���O���Ă���̂ł́H
>>281 ��������������70kg�ɂǂ����҂��Ă�̃R�C�cw
�q�������������L�т邩�ȁ[���炢����
70kg�̋@���͍��ŏ��s�������悤�ȓG������H
>>288 ���̃^���N���킴�킴�P�������̂̓p�C���b�g�ی�ׂ̈���
�ł����Ė�����Δ����@������ߏ�ȔR�����㏸�̎ז����A���ꂱ��70kg()�Ȃ�Ĕ�r�ɂȂ��
�����ƌ����ΕČR���ł��Γ��{�@�Ŋi���킪�I�n�t���Z���Ă��͎̂����̗�
�́c����܂��c�A���͐��̍H�����t��G���W���������Ȃ��������炾��
�t��G���W���̋Z�p�ێ��̑_�����������낤�����C�Z���X�����������������Ȃ���Â�������
���́A�j���ŎO�H�����g�p���Ă邵�A
>>291 �ꎮ��Ƃ��̖h�e���������炢�̏d�ʂȂ̂����
>>293 �����������ɉt���点���̂����̗��R�ł���������
>>293 ����͔��V�^�̏�ʌ݊��ƌ����Ă��ߌ�����Ȃ������
����F6F����}�����̂悤�ȃ_�C�u���x�Ƃ���𑶕��ɐ������ɖ����㏸�͂͋M�d
�e�X�g�ŗǂ����������ɂ����܂œ����������܂Ŏォ�����̂͗\�z�O�������낤
�����ڍs���悤�I���Č��������Đ��̍H������������킯�ł��Ȃ���
�@�̂̐��������̂��̂͗ǍD�������̂����X�ނ��Ȃ��������
>>294 ��������퉺���Ƃ����̔n�����z���g�n���Ƃ������̂͋ߍ��̗��s��ł͂��邪�A�܂�BoB�̉p�R�p�C���b�g������
>>298 �ŋߔ��̕]�����������������͂ˁH�����ł�����j�̕]������̑�����
�܂��ČR�Z�l�ō����݃m�����n�������Q�ʂł�����I�Ƀ{�R�{�R�ɂ��ꂽ�[�Ƃ�
���d���������𗽂��ČR�̈ؕ|�̓I�ł����[�Ƃ�
Mig15����B-29���o���Ă��[�Ƃ��M���Ă�z������Ȃ��������c������ȁH
�܂��܂����邱�Ƃ��邩�������
>>299 ���̕]�����������Ƃ��v���Ă�̂��O��������
�~�{�̖{�Ŕ��グ���Ă����ǁA�����~�{�����̖{�o���Ă���ς���������ĂȂ�������
���R�@�͉p�R�@�ƌ�킷�邱�Ƃ������݊p���������A�ČR�@�ɂ͕�������
���͉p�R�@�ɃL������10�{�߂������A�ČR�ƌ݊p
���҂����������������ČR�@�ɂ͈�x�������z���Ȃ������̂������������
���Ղ̃x�e�������W�߂ĉ^�p���Ă������͋��������Ƃ����b�ł������
>>�R�O�P
7.7�~���e�ւ̑Ή��ŗǂ����珉�����璆�U�A1�����U�A���ɔw���h�e�����Ă�����������
>>297 �������ǂ���������Ă��������@�������犸���ē˂����܂Ȃ�����
�i���̐����͈Ⴄ��Ȃ����ȁj
�b�Ƃ��ẮA���̓t�b�N�A�܂肽���ݑ��u�A�A�����u�ƈ��������ɂ��邭�炢��
���ɏ��a16�N�̈ꎮ��Ɠ����̖h�e�����邱�Ƃ͉\����˂Ƃ����b�`
70kg����ւ���Ζh�e�K���X�Ɩh�e�|�A�h�e�^���N�ɂł���i�q�������A�߉ׂ�1680�\��ۂꍇ�j
�܂��A���̒��x�̏d�ʑ��ƈ��������̖h�e�����Ȃ������͖̂��炩�ɑӖ��Ƃ����������ł�����
�Ƃ͂�������^�̂�7.7�~���@�e�Ή�������
�����̗��A���̖h�e�����i13�~�����ӎ��j�͂�����d���Ȃ邯�ǂ�
�܂����ɖ{�i�I�Ȗh�e�����Ȃ��
>>274 �r���}�ŃX�s�b�gMk.8���������͂��߂��̂�44�N�㔼����������
>>274 >����P-40��n���P�[���̕����}�V
�j���[�W�[�����h��R�̃L�e�B�z�[�N�͂��������撣�����炵������
�����X�s�b�gMk.5�͑ʖڂȂ낤��
>>306 �h�e�����ǂ��납13�~�����瑫��ĂȂ������肷�邩���
>>301 �����ɋ@�̐��\���Ă����ƈꎮ��͂�������������
�ނ��둼�̋@�̂��v�����قǑ債�����ƂȂ�������
����Ԃ��A�ꎮ��O�^�ƌ����炢�����A
�{���̈Ӗ��Łu�V�s�@�v�𓊓��ł��Ȃ�������
���{�̌��E�͂��̕ӂ������낤�Ƃ������Ƃ�����
�����ł��Ȃ�����
�r���ő��M��������� orz
�����t��[�^�[�J�m��20�~���@�֖C���ڂ̃L12�������I�ɍ̗p�A
�����Ǝ��d���^�͐V����@�̎�͂Ƃ݂Ȃ���Ă��݂����ł͂��邯��
>>300 �A�����J���~�{���A�ǂ��������Ԉ���Ă���Ď��ɂȂ�ˁH
���ꂩ�c�N�̋L���Ⴂ��
>>304 ��������()�Ƃ������Ă����Ă��O�͎����o���Ȃ��̂���w
�C�t���Ė������狳���Ă�邪���O70kg()�̏ؖ����o���ĂȂ���Ԃ�����
>>311 �l����͑���̃_�C�u�����ɑΉ��ł��������ł��\���𗧂��Ă��ꂽ����c
���ł����H�����킩�邯�ǂ�
�܂������A�{���Ȃ痋�d�ƈ��������ɎO�H�ł̐��Y���I���A���������_�̐V�s�@�ƌ�シ����肾���������
�[��54�^�Ȃ番���邯��
�L100�Ɨ��Z�l�^�͉��}�����ł����܂ł���Ƃ�����͂�����������
>>317 > ���a18�N�ɂȂ��āA��^�Ɨ��d�A���܂������Ǝv�����ȕ��ʁc�c
> ���d�X���ɂ���܂����������݂Ȃ���
���������Ă͂���������ǁA�������o�R��XB-29�̎�����s�̗l�q�����_��
�u����͂܂����A�����l�������Ȃ��Ƒʖڂ��v�Ǝ咣�����l�͗��C������ɂ��������낤�Ǝv���B
�u�ŁA����p�ӂ���v
�u���������鍑�{�y��@����ꏊ��G�ɗ}�������Ȃ���Ηǂ��v
�Ƃ�����ȋc�_���������Ǝv���B
��������Ɗ�����������h��������ł͂Ȃ�����
>>318 ���s�ւ̕⋋��f�x���K���̐�̂ƁA�}���A�i�̎���
��ԊȒP�Ȃ̂̓x���K���̐�́i�C���p�[��������N�������j��
����͊C�R�����͂��Ďj���̋@��\���ł��ł��Ȃ��Ⴂ���Ȃ������b
�}���A�i�͊�n�Q�������n���䂦�h��������Ȃ�œ���Ƃ����̂���m�b���Ǝv��
����C�ʂ̓t�B���s���܂ʼn��������ق����}�V�Ɗ��j�����̂͗��R�l�̍���������
���̐l�̓K��������������ȂNJC���̐헪�ő쌩�̂���l��
�ǂ��l���Ă�����R���ԈႦ���l
���ۃt�B���s���̐��͗��R�q�����̂ňꎞ����������
�}���A�i���ł̌�������Ă�ቷ��������q�͂ƈ�@�͂ŋ������ł�������
�����ŏ��Ă���̏ꍇ���A�e�Ƀ}���A�i�ւ̕⋋��j�Q����v�悪�������̂�
�����������`���̋@���W���ɂȂ�Ƃ܂��܂��q���̓M���M���̗��d�ɏo�Ԃ��Ȃ�����
����Ƃ��L�����Ȃɒn��v����֏悳���ꎮ���U�����͂ւ̓]���ɔ�����A�\�͂̒ቺ��₤���肾�������I�H
�Ƃ�����{���͂�����ӂŎ��d�̑���ɂȂ��Ă��͂��Ȃ��
�t�����d�����d�̑��肾����Ȃ�������
�C�R�u�x�z������̋������肢���܂��v
>>317 >�L100�Ɨ��Z�l�^�͉��}�����ł����܂ł���Ƃ�����͂�����������
�Z�l�^�͎���i�K�łقƂ�Ǎ\�z�ǂ܂�Ȃ̂ɂ���͌�������E�E�E
�������d���Ɠ����Ő�т͂܂����x�������ʎY�ł��Ȃ������Ԃ�
��т͈����Ă����̎���ɗʎY�ɐ��������l���̂ق����܂���͌����Ă���
�����ɂ������
���Z�l�^�ʎY�J�n�̎����͏��a20�N7����\�肵�i��P�ōH�ꂪ����ł����j
>>325 �����Ƃ��C�R�Ƃ��Ă͏��a18�N10���Ɏ�������d�ւ̈ڍs���X���[�X�ɍs�����肾�����̂łȂ�Ƃ�������
�s�������₦�Ă����ꂽ��ˁA�Ƃ���
���܂��炾���A�C�R�����ς����Ă����u�����Ǝd�オ�������d�v�̐��\��R�X�g��
>>327 �����������d�͗���ł͂����Ă��Δ����@��p�ł͂Ȃ��킯�ŁA
�Ȃ�ł���Ȉ����Ӗ��Ő�������̂ɂȂ������Ă���
�ΕĐ�n�߂����Ƃ�14���ǐ킩��ʒu�Â����ς��������Ă�C�������
���ɐU����肪�Ȃ��Ă������n�q�����������̑���ɓn����āA
���Ƃ��ƌ}�����@�Ƃ��ĊJ������ċ����̂����d�B
>>291 �@�̍Ō㕔�t�߂̏d�ʌy���͐�10kg���x�ł��^�����ɍD�܂����e�����y�ڂ�
�̂ł́H
>>317 ���̎����Ŏ��d��������(���d���܂߂��畉���邯��w)
�G�[�X���X�Ɍ��ʂ��o��������Ȃ�܂�����
10�@���邩�ǂ�����64�^����́H��k��߂Ă���w
>>331 �����Ōł܂��Ă�㕔���������āH
�ł����Ă��D�܂����͂��̔��T�^�͂��ߊe���̗��R�@�����21�^��蕉���Ă����������
70kg�̏ؖ��ł��Ȃ���ΗL���ɂȂ��Ă�������Ȃ��A���Ȃ���
>>331 �d�S���牓���ꏊ�Ōy�ʉ����Ă��d�S���Y���Ď嗃�̗g�͒��S���痣��Ă��܂�
�P�^���͋@���20mm�C��ς����ŋ@�����O�������̉��C���d�S���O�ɃY����
���ʁA�嗃�ʒu��4cm�O�i��������ɔ����Ƀo���X�g��ςރn���ɂȂ�����
�������킸���ȕϓ��ł�����e�͈͓��Ƃ���o���X�g�ς܂Ȃ��ꍇ������
�������d�S���牓���ꏊ�قlje�����傫���̂��m��
���ɋ@�̏d�S����5������10kg�y�������Ƃ����
>>327 �����͊m���ɋC�ɂȂ�
�C�R���v���`���Ă��u���������d�v�͂ǂ�Ȃ��̂ŁA����͂ǂ��g����͂��������낤�ȁH
���������Ɋ�n����Đi�o���Ă邩�痤��@�ŏ\���Ȃ͂��������H
�^���Ȃ��퐄���͍̂\��Ȃ����ǁA���グ�̃��C�̂��ڂ������Ăǂ��Ȃ�
>>336 B-17�͂��ߑ�^�����@�p�Ɏg���\�肾��������
�����̎Ώe���v���̂ق��D��������&�q�������������z�u���X���[�Y����������c���Ċ����H
���̒��̓t�b�N�O���͎��ۂɂ���Ă邵���ɂ��Ȃ��ĂȂ�
�C�R�����d��̂̐퓬�@���łǂ��키���肾�������͂킩��Ȃ�
>>338 �ł͂ǂ�����ďd�S�����܂�̂������Ă݂Ă���
������͎Q�l�ɂ��Ȃ��ėǂ���A�N�̍l������������
http://www.cfijapan.com/study/html/to199/html-to150/137-5-WaB.htm >>340 ���܂�������A�d�S�ʒu�ɂ��Ă͂�����x�̕ϓ��͍l������Ă�̂�
���e�͈͂Ɏ��܂邩�ǂ����̖��A����͋@�̂Ƒ����̏d�ʂɂ��
�E�E�E�E���⋖�e�͈͂ł��邩�ǂ����Ɓu�ǂ�����ďd�S�����܂邩�v�Ƃ������w�I�Șb�Ƃ͕ʂ��낤��
>>341 >>342
>>334 �ł܂�܂��̂Ƃ���̎��������Ă���̂��ڂɓ���Ȃ��́H
�w�������킸���ȕϓ��ł�����e�͈͓��Ƃ���o���X�g�ς܂Ȃ��ꍇ������ �x
>>342 �ǂ�����ďd�S�ʒu�����܂邩�Ȃ�Ă��Ƃ���Ȃ��b���
�N�����ݕt���Ă�����������Ȃ���
�V���͎��p��̖��̗L���ɂ���Č��܂萳�K��Ԃ̏d�S�ʒu�Ƌ����u�����v�Ō��܂�Ȃ����Ęb�Ȃ̂�
>>344 �Ȃ�قǗ�������
�������N�������Ă鎖�͂��܂�ɂ������肫������O��̘b�Ȃ�
����ȏ������̏������w�E���Ă���l������Ƃ͗\�z���ĂȂ�����
�ł��N�̋C�����͗�������
����A�܂�O1o8+mql�����������������킩���
����E�E�E
>>339 �����Ȃ��
���̐��Y�ł����ė��d���Y������āA
���j�Ƃ��Ă͂��Ȃ�v�������b�Ȃ킯��
�ΐ퓬�@��͓��A�Δ����@�͗��d�A�݂����ɏZ�ݕ�����Ƃ�
�j���́A�ǐ킾���Ǒΐ퓬�@��ł��鎇�d�̕����Ґ������Ƃ����b��
�܂�������₷�����ǁA���������Ȃ�ł���Ȃɗ��d�d���H�Ă���
�i����͐������������j�ɐ�ւ�����Ȃ���
�S�R�x�^�[����Ȃ��Ǝv��
�a���`�Ƒw�����ŕĐ퓬�@���Ԃ������鍂���퓬�@�I
���d�ɂ܂���}�W���Ȏ��s��
�D�̊J�����Ɠ��{�ł���������v�[��������肵�Ă����Ԃ�i��ł�����Ȃ��ǂ�
>>352 ���{�@�͐_�i���Ƃ������_�b����������������
�����͂���Ӗ����S����ˁH
�ꎞ�����Ă�90�N��܂ł����璷���ڂŌ�����Ȃ�ŋ߂܂�
�h�C�c�@�܂߂Ă܂Ƃ��ȕ]�����������ĂȂ���������
����ƍ�������ă��^���x���Ń_���|�����ǎd���Ȃ�������������
>>349 ���{���i����̂Ă�Ȃ�A�����J���i����Œǂ��W�J�ɂȂ邾��
���x�œ�����ɂ̓X�y�b�N�̑傫�ȍ��ƃG�l���M�[�̗D�ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����
���ǂ͊i�����\�̋@���͂œ�����ق��������I�ɂȂ�
���{�@�̂悤�ɋ}�~���ł��Ȃ��݂����Ȍ��ׂ��Ȃ������
>>354 �������܂Ƃ��ȕ]���Ȃ́H
�ꐶ�����d�������ҒB�̎��s�����͏��Ȃ���
����Ƃ���ΐ�Ɏ��s���������Ȃ��l��
�ꐶ�����d�������o�����Ȃ��l���낤
���⌳�X�ČR�@�͉��B�@�ɑ��Ċi���ŗD�ʂɗ����z��������
���a14-15�N�i�K�ŁA���p���̃��h���o���Ă����낤���{�̋Z�p���W�߂āA
���̈����
�ė��R��P-47�ɏ�����g�b�v�G�[�X�́A���B�ł̓x�X�g10�͐����c��������
���͎��r�C�ǂ̗̍p�͏\�O���͔�����
�x�z�Z�t��96�͐�̊J���Ŕ����@�s�r�����Ă܂����
�x�z������Ăю̂Ăɂ��邠�����
>>359 �̌��E��������
���ʂ͐e���݂����߂ăz�[���[�����낿����
>>359 �����������Ƃ͂킩��˂ǁE�E�E
�Ȃc�u�V�̗����Ȃ��A�g�������������~�[�b�g�t�@�C�^�[�ɂ����Ȃ���[�ȋC�͂���̂˂�̂˂�
���������c���ɓ��������ᑬ��肾������Ō���ꂽ��Ɏ��̂肻���ȁE�E�E
>>361 ���{�͑ΕĊJ��O����ґ���킾�������NJe���D�ʒu�ɐ��ł���Ɣ��f����ƃo���o����
������ĒǏ]�i���ɓ��鎖����������
��ߍU�����Ƃǂ����Ă��傫�������p�Ō��z���ˌ������Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ńx�e�����ł�
�ȒP�ɂ͓�����Ȃ�
�����Ǐ]���ă��[�h�ˌ�����̂���ԓ��Ă₷�����
������ČR�@���Ǐ]���Ă��Ȃ��悤�ɂȂ�Ƃ��������ł��Ȃ���Ńx�e���������e��������Ȃ�
�r�̍������Ĕ䗦�ɂ���ɏo��
>>357 ���{�@�n���ɂ��邱�Ƃ͐�l�ւ̕��J�I�Ƃ������z�{���Ɍ���
�ĉp�@�͎U�X�����̂ɂ��邭���ɁA���Y�펖�������Ă₪��A��
���d�A�ΐ퓬�@�̎��т͂ǂ��Ȃ낤
���������A�p����w�Ƃ����^�{�f�u�ȕċ@w�Ƃ��U�X���Ă邻�̌���
�Ȃ����l�b�g�̐l�Ԃ��S�������l���Ƃł��v���Ă��郄�c������ȁc
�p���ʂ͗_�ߌ��t����
>>371 �S�������Ƃ͌����Ȃ����ǂȂ�ǂ����Ȏv��������ꂽ�����
�_�o���ɂȂ��Ă�͎̂ӂ�
��������������₵�����炢�ŁA���݂���}���Ƃ��A
�n�C�I�N�K�\���������������
>>359 ��m�b�̌��ʘ_���Ǝv���B
�R�p�@�͐悸�ڕW���\���肫�ł����B�����ׂ��G���W���I��Ƌ@�̐v���s�����́B
���̃G���W���A�@�̃X�y�b�N�͂ǂ̂悤�ȗv�����\�Ɋ�Â��Đv�������̂Ȃ̂��H
���̗v�����\�͓����ɖڎw�����̂Ƃ��đÓ��Ȃ��̂��H
������l�@���Ȃ��ƉΑ���L���x���ɂ����o��ł��Ȃ��퓬�@�ɂȂ�B
F6F�Ɗ��S�Ȋ�P�ł�P-51���ق�Ƃɐ�����������c
��������
>>359 �̗��̗��̋�C��R��33�p�[�Z���g�Ƃ����ɏo�Ă�b�Ȃ낤
���̒�R�͗��̑�C�}���p�ő傫���ς�邵�w�����̃��|�[�g�o���Ă��Ċw�҂̘_������
���풆�̐퓬�@�̋�C��R�ŗ��̐�߂銄����10�p�[�Z���g�O��ɂȂ��Ă���
������������
P-47��P-38�Ƃ�381��̂ǂ�������Ő���Ă����ȋC�͂���
������33����Ȃ���40�p�[�Z���g��������
�ꍆ���̗��[����4�`5�m�b�g����
�����܂��A���d�̖��͑��x���㏸�͂ƕ�������
>>378 ���̕ߊl�@�e�X�g�ŁA�N�E�L�e�C�R�E�m�ڍו��̓��|�[�g���o�Ă邩��ˁB
http://www.wwiiaircraftperformance.org/japan/RAAF_Hap_Trials.pdf appendix �� drag analysis�������āA�S�@��R 58�P�ʂ̂Ƃ���Awing������23.5�P�ʁA���ăl�B
������@���ς����炶��Ȃ�����
>>356 ����������F4F,F6F�͊i���킪�o�������Ęb������(�h�C�c�k)
�_�C�u�Ή��Ȃ���o�����A�����㏸�͂��N�\�S�~�Ȃ̂��͂���
�����Ɏ����Ă����܂ł��S�{�A�������������֗�����
>>369 �������̃^�[���Ɏ������߂Ȃ���ΈӖ����Ȃ�
�ᑬ�ŋ@�������ǂ��@�̂���Ȃ��ƈꌂ���E�ɑR�ł���
���d�݂����ȃ|�b�`�������Ɠ�����₷���������
>>377 �����l�����ō����x�œ˂����ނƑ��x��500km�Ƃ��ɂȂ��ē�������̂���Ȃ�����
�����ςȂ��Ə����������ōr�ꂿ������悤�ł��܂����@orz
>>385 >����������F4F,F6F�͊i���킪�o�������Ęb������
�����Ă��͍ڋ@�����A���ʐό���Ɗ��Ɣ[���ł���
�������ȃC���[�W��F4U�ł���29.2����m��
�w�r�[����P-47�Ƒ卷�Ȃ�����
>>387 �Ȃ��Ńx�[�X���̂܂܂Ƀ_�C�G�b�g������2000�n�͋��G���W����p��
���52�^(�̕�������ɗ��Ă�����)�ɏ���Ƃ����Ȃ��i���\�͂��������̂�F8F�������
P-51�Ƃ̖̋[���ŏ������߂Ă邵
>>383 �����_�ȉ����R���}0��5��2��ނŒ�R�l������̂��H
�Ƃ������̑���
�嗃���̔����G���W���@�O�I�o��
�e�p�[�c�ʂɒ�R�����鎖�͂��܂�Ӗ����Ȃ�
���ꂼ��P�̂ŕ����������Đ��m�Ȓ�R�l�Ă�
��������̂ɑg���̒�R�l�͑S���قȂ�(���Z�ɂ͂Ȃ�Ȃ�)����
����R�ׂ̈���Z
�܂����Z�l�ɂ��Ă���G�c�߂�����
>>388 P51�͒������퓬�@�Ȃ��畉���Ă��d���Ȃ��Ǝv��
���^���p�̋@�̂Ƃ���F-8F���p�ӂ����ĊC�R
���Z����ۂ���F8F�����ǁA�h���b�v�^���N������1700km�ȏ�A
>>389 ���O����P-47D�ɕ����܂�����Bf109��Fw190�̑O�Ō�����Hw
�U�X�������Ă���Ȃ��������ȏ�̍q�������̓z�͋ɋ͂���
����P-38�Ȃ�Ĉꌂ���E�Ȃ���ɏ����Ă邶����ق炵����
�ł����Ė̋[�킾�����R�^���N���낵�ĔR���������Ă�Ɍ��܂��Ă邾��
>>392 >�ł����Ė̋[�킾�����R�^���N���낵�ĔR���������Ă�Ɍ��܂��Ă邾��
�^���N�~�낵�ĂƂ������A�h���b�v�^���N�͂��Ƃ��Ƒ������Ȃ���
P-51��F6F�������Ǔ��̓��̃t�F���[�^���N�ɂ͊�{�R������Ȃ�
�������C���̂Ƃ��͐^����Ɂi�h���b�v�^���N����Ɂj�t�F���[�^���N���g����
�d�S������Ă��ԂȂ̂ŁA�h���b�v�^���N�t�����܂܈ȏ�ɂ܂Ƃ��ȋ@���ł��Ȃ���
F8F�͂��̃t�F���[�^���N������]�T���Ȃ������킯�ŁA
�ʏ�͑��Ƒ卷�Ȃ����ǁA�ł�����̕��������킯���
�}���A�i�̎��Ƃ��Ă��R����ŕs���������o�̃A�E�g�����W�U���d�|���Ă邵
��[���h���Ŏn�܂�͋[���Ɗ�P����r�̍�����̎������������ɂ��Ȃ��ł���
�h�C�c�@�͍q���������Z�����Č}���ɂ��x�Ⴊ�o�Ă�̂ł́H
�������R����ɂȂ�̂̓A�E�g�����W�U������Ȃ��Ă����̕Г����U����
���܂��炪�p�C���b�g�Ȃ牽���Ԃ����ł�̂Ə��ꎞ�Ԃقǂ����Ɣ��ł��Ƃ̓e�B�[�^�C���A�ǂ����������Hw
>>396 �U�����a���肬��̔���U������������
�A��������s������������Ȃ��Ē��͑҂��̊ԂɔR���ꑱ�o����
20�@���A�ҁA80�@�����Ŕ�錂���A���钆�j�A���߁A���c���j
>>396 ����Ȏ��͕������Ă�
�A���Ă��Ă����͑҂��Ă�]�T�������̂��Г��ƕς���
��������Ȃ��đ���̓͂��Ȃ�������U������̂��A�E�g�����W�U����
>>397 �e�B�[�^�C���ł����������
���ꎞ�Ԃ�����ׂȂ�����ꎞ�ޔ����čD�����f�����ƂȂ�
�D�ʂɂ���G�@�Ɛ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂͐h��
�����̓��{�R�ƃh�C�c�R���Ƃ��̈Ⴂ�����邠��
�S�͂��ƔR������Ǐ��q���R���H���̂��h��
>>393 ��������P�X���Ȃ�ďo�Ȃ����낤��w
���������q���������������U�N�U�N����Ă����������ȏ�
389�͉��̈Ӗ����Ȃ�
>>397 ��������_���Ĉꐶ���̐��Ńe�B�[�^�C���H
>>399 �����́f�A�E�g�����W�|��f���炢�őË��ł��̂�
��s�b���������Ƃ邳����
>>403 ���╁�ʂɓ��{���̃A�E�g�����W�ɛƂ܂��Č��������͂��Ȃ���v���w�Ĕ��������
���{�����T�d�����ċ������l�߂��猋�ʓI�ɓ͂�����������
�a����V�R�͗��݂����Ƀp�C���b�g�̘r�ōq���͂��X�ɐL���鉻��������Ȃ�������
�X���^�C�̗��d�́A�ΐ퓬�@�퓬�ɕs�����Ŏ��d���Ƒg�ݍ��킹�ɂ�Ȃ��Ƃ��A���d��F6F�Ƃ�肠����̂͐ԏ����炢�̂��̂��A�Ȃ�ĕ]�����قǐ���p�r�ł̓P�`���t���@�̂Ȃ�
�{���͓V�R�Ŗ�ԗ����A���̖������ɗ��Ɯa���ōU���ł��Ă��
>>369 F6F����@�P-51����@�����d�̑ΐ퓬�@�퓬�ł̐�ʁi���t�m����{�����f�j
>>405 �ǂ��Ȃ����Ă��▭�Ȓ������o���Ȃ��ƌ��Ƃ����Ǔ��������Ⴄ��ł��܂�Ӗ����Ȃ�
���d�A�ǂ����Ȃ�݂����Ȓ����A�t�K�����œO��I�ɐ���ė~����������
�^���甼���𗬑w���A�攼�����w���ōX�Ƀe�[�p�[�ɂ����̂�������
����Ƃ����ă\�[�X�͂Ȃ����A�w�����ƒʏ헃�^�̑J�ڋ�Ԃ����Ȃ�c������������
>>409 �t�K�����͑咼�n�v���y�������邽�߂ł́H
�t�K���͂ނ���\���̊W�Œ����ɂȂ����@�̂��r��Z�����邽�߂ɍ̗p����C���[�W
>>412 ��F-4U�ł͓��̂Ǝ嗃�̎��t���p�������C�����܂���
���ΓI�ɑ���a�y����t���Ă��r�͒Z���ł��܂���
���d�������Ǝv����ł��t�K����
>>369 P-47�r�߂�������
�v���y�������ł������Ȑ��\�����邵
���{�ɔ��ł����̂�
P-47N�Ƃ�����������
2800PS�o�邼
��A�����̂܂ɂ��t�K���������ɐ����Ă���w
P-47N�͖���
>>417 D�͒����嗤�Ȃǂ̗��R�S�����ʂ�����
���d�̏o�Ԃ͂܂����肦��
�R�C�c���h�C�c���炵���炠�蓾�Ȃ��قǃ��x�[�z������
>>418 �Ȃ�ق�
P-47D�ȍ~�A���ƂƂ����ŏ��Ă����m��Ȃ��̂�
���d�͂ǂ����������Ǝv�������nj��ؕs�\��
�l�I�ɍŋ��퓬�@�Ƃ݂Ȃ��Ă���P-47
���s���C�ɂȂ���
>>419 N�͉��ꎸ�ׂ���̎Q��������
���{�͑�K�͓��U���I����ĉ����ɓ����Ă��c��ꂩ���������Ȃ����炵��[�Ȃ�
D�Ȃ玾���E���������T�C�h�L�����߂���
����P-47�������ŐU�������A�����g�b�v�G�[�X���̃j�[���E�J�[�r�B�@�����Ă��Ă�
�h�C�c�ƈႢ�y���������P-47�ɂ�������x�R�o���Ă�����
����ł���͂�8��̐����ʂ�J�����œ˂�����ł���̂͌��܂���Ȃ�̋��ЂȂ̂͊ԈႢ�Ȃ�
N��2200hp��2800hp�ɂȂ��Ă��i�i�ɂ͕ς���
2800hp�ً͋}�o�͂ł˂�������
>>421 >��MFS���Ɛ��i�͎��̂͂��܂�L�тĂȂ��ݒ�Ȃ̂�D��N�̍��ȂS���̊��ł����
�E�E�E
���ۋً}�o�͂��オ���Ă��̊��ł���قǂ̍��Ȃ����ł���
>>424 �ǂ̂��炢���\���サ�����͕ʂƂ���
�P�ɐ����^�ŋً}�o�͏グ���݂����Ȑ������Ă�l�����邯�ǁA
���{�ł����Ɖh��_��2x��3x�݂����Ȋ�����R-2800�̃o�[�W�������ς���Ă��
F4U-1D�AF6F-5�AP-47D�܂ł�"B"�V���[�Y��F4U-4�AF8F�AP-47M/N��"C"�V���[�Y
"C"�V���[�Y�͒P�Ɉ��k��グ��100�n�͌��サ����������Ȃ��āA
�V�����_�w�b�h����������b���ɂȂ������p�t�B���̃s�b�`�ׂ���������A
�G���W�����̂��Đv���Ă邵�A�X�[�p�[�`���[�W���[2�i���Ƀt���J���g������
P-47M/N���^�[�{����a������Ă���AF8F�̓R�}���h�Q���[�g����������A
�v����ɐ��オ�Ⴄ
����500�n�͑傫�����^�@�ƈꏏ�ɔ��ł�ƃW���W������čs�����Lj�@�Ŕ��ł���
>>426 �����Ȃ̂�
���ᗋ�d�����r���[�ɉ��ǂ��Ȃ������悩������
�܂���ǓI�ɂ͎����������肩����
��Ȏ����ɕی��@�Ȃ��ŐV�@�������Ɋ|�����̂���
��Z���̎d���Ȃ�Ȗ{����
�a������Ă�ɂ���������C�R�@�̊J���S�ʂɖ𗧂����������
���ꂱ���\�͐�x�[�X��
>>359 �݂����ȋ@�́i����Ɏ����@�Ȃ̂ő����҂����߂ɋ@�핐���Ȃ����ċ������ځA�O�_�~�����Ȃ��ł������畗�h���Ⴍ����j������肵��
�܂��ق�Ƃ��Ɋ����̋@��v�̒P�����@�Ŏ���600km/h�ς����Ȃ��̂��m���߂�
����Ȃ炷���ł������낤
���s���ĉ�������p�t�@���t���a���^���̂̎����@������Ă݂�A�Ƃ�
�o���̒~�ς��Ȃ��Ƒ����̌ł܂��ĂȂ��ɋp���ċC�Â��Ȃ��Ƃ�����Ȃ낤����
����������P-47J�̗��d���̂��݂̂����ȓ���
P-72����
����P-72�͂ނ���G�A�R�u���I�ȍ\�����̗p����Ă�̂��H
���p�u���b�N�͋@�̂����v���Ȃ�����G���W�����v���y�������А�����Ȃ����낤
�v���y���͍ŏ��ؐ�����������y�����Ă����}�n�ō�����H���Ĕ������n�܂������
>>183 �v���y���̐v�ύX���s��˂Ȃ�Ȃ��̂͋��U�̂���������A�v���y�����̌ŗL�U�������Ⴆ�N����Ȃ��킯�ŁA���̒Z���v���y���̋@�͖̂{���̔��^�v���y���t���Ă���Ȃ�����
�m���ʉ_�̂ł�����10�m�b�g���x�̔��X���鍷�������ƋL�����Ă��邵
��s���A3.98m�̃y�����Ă邯��
�ۃ��J�j�b�N�̋L�����ƃv���y�����a3.9m�Ő����e�X�g�Ŗ��Ȃ��������lj߉d�����e�X�g��
�Ȃ�قǓ�s���̏ꍇ�����˂̉ΐ��������ł����v���y���Ȃ̂�
�ꎮ���U�̓v���y����̎����ɂނ���10km/h�قnj��サ�Ă��邮�炢�������
�L���̘b��11�^�ȑO�̘b������G���W���͓��R�ΐ�11�^�Ő����^���˂Ȃ���
>>420 >D�Ȃ玾���E���������T�C�h�L�����߂���
>����P-47�������ŐU�������A�����g�b�v�G�[�X���̃j�[���E�J�[�r�B�@�����Ă��Ă�
�������Y�ꂽ�̂ŕ⑫
�퓬�͎��̉^�Ȃ̂ŋ@�̐��\�͂����܂ŎQ�l�ɂ����Ȃ�Ȃ���
P-47D�ƌ����Ă��O���^��D-20�ȍ~�̌���^�{�o�u���L���m�s�[��D-25�ȍ~�͕ʕ�
�J�[�r�[���펀�����Ƃ��ɏ���Ă��@�̂�D-4�i�����^��������2000�n�́j
D-20�ȍ~�͐V�^�^�[�{�Ɛ����^�Ő퓬�ً}2300�n��
D-25�ȍ~��2600�n�͂�N��2800�n�͂�145�O���[�h�d�l�̐��l�炵���̂Ŋ�������Ƃ��āA
�R���Z�A���܂߂āA�S�̓I��R-2800���ڋ@��43�N��2000�n�͋��G���W���������̂�,
44�N�㔼�������2200�`2300�n�͋��A�I��O��2500�n�͋��ɂ܂ŏo�͌��サ���A
�ƍl������������悢�̂ł�
�R���Z�A��P-47�̈�ۂ��傫���Ⴄ�̂͗��x�⎾���̂悤��
>>422 ���d��P-47��P-51�ɏ��ɂ͒��ɒǂ����ނ����Ȃ��B
B-29�̃G���W�����T�C�p���̔�s��ɎR�ς݂Ŏ̂Ă��Ă����炢�ŕČR�ł��O����
P-47�͊C�ʍ��x�ł��^�[�{�`���[�W���[�g������
1943�N�t�i�\�������͏�Ă����ǁj�̎��_�Ń\��������F-4U�̉ғ����͖�35%
>>444 �X��P-47D�͓r���y���̉��������邩��
���ꂾ����
�㏸�\�͂͊i�i�ɂ������Ă�
�����ɃK���K���o���Ă����̂ŁA�t���Ă�������{�@�͂Ȃ�
�Y�[���A���h�_�C�u���ꂽ��
���������ł����
���ہA���{�@�͂�����ςȂ��̃����T�C�h�Q�[����������
�ǂ����Ȃ���ɁA�d���b�ŋ�����
P-51�EF6F�ȏ�Ɏ苭��
�v���y���͕t�����܂ŕ��L�̕�������������
����ϓ��{�����͂��ׂ��̓r���}�A�C���h���ʂ���
���Ƃ��x���K���˓��Ɏ��s���Ă��r���}���ʂɗ��C�R�q���������
���Ⴀ�\�A�@�݂����ɒ��`���[���ɂ�����ǂ���
�\�A���ꉞ��������̔����@�͎����Ă邵
P-47�����Ń^�[�{�g���Ƃ����{�@���Ǐ]�ł��Ȃ������㏸���Ă����Ƃ����`������
>>458 ���d�O��^�̃C���v���b�V������ǂނƔr�C�^�[�r���̓}�j���A���ō쓮������
�����悤�ɓǂ߂�B
P-47�A���x��g�p�R���ɂ���ă^�[�{�̑���v�̂����܂��Ă�
���l�l�N�A�Z�t�����̓{�u�E�W�����\���̏��������\�Z�퓬�@�A���́u�T���_�[�{���g�v�ɐV�����v���y���������B
P-47�Ɏg��ꂽ�V�^�̃v���y��
http://www.368thfightergroup.com/P-47-R2800.html �����ł͂�������A�������ł͏㏸�͈ȊO�ɂ��^�[���\�͂̌���ɂ��Ă�
�L�q�������B
The P-47D-25 and later versions were factory mated with the
paddle blade propeller. Other models were retro-fitted with the
new props. Introduction of the paddle blade prop enabled the
thunderbolt amazing climbing and turning ability.
���̃v���y����t����P-47��FW190�̃��[���ɐH�����čs�����Ƃ����̂�
�܂����{�@���Ɠ������i�͂Ȃ����낤��
��}�p�ł̏㏸�͖������낤����
�r�C�^�[�r���͉ߋ���݂����ȕϑ��@�������
>>461 �̘b���X�s�b�g������Vx�㏸�ɒǏ]�ł��Ȃ������ƕ���Ă�ȏ�
����ȉ��ł����Ȃ��킯��
�ł�P-47�̊���͒��ڂ��ׂ�
��ʂɌ����㏸�͂�Vy�㏸�Ŏ��ԒP�ʂ̏㏸����������ǂ��ꂽP-47��X�s�b�g�○�d��
>>464 �X�s�b�g�����A�^�ɂ���ăA�z�݂�����
���\���オ���Ă��@�̂�
�I�[�W�[�ɋ����^�����̃X�s�b�gV�Ƃ��ƕʎ�����
�����ŏo�Ă���IX�̓}�X�^���O�ȏ�̏㏸�͂�
���{�@�ł��Ă���@�͖̂�����
>>451 �p�C���b�g�����o���Ă����R�͂܂�����
�c���ĂȂ��Ĕ����݂�����
�S�ʓI�ɕ����Ă鎇�d���Ȃ�āc
>>461 Bf109��Fw190���T���{���͂��납���d�ɏ㏸�͂ŕ����Ă邩��Ȃ��c
>>468 �����G���W���ς�łقړ����\�̇[�^�Ɣ�(�U�ł��s���A�V�ł��L��)�͕��ʂɂ�肠���Ă���ł����ˁc
�U�^�̎��_�łقڏ��c���݂̏㏸�͂��Ă邵
>>468 ������㏸�͂�Vx�㏸���\�͕ʕ����Ƃ���قǁE�E�E
���R�A�K�������S�Ă̕����ɌP�����s���n���Ă����킯�ł͂Ȃ�
>>470 ��肠���Ă��˂�.....
��A�L���u���
���{�@�@�����@65�@�@���@���Ƃ������E���R�A�i����ł���Ƃ�����Ȃ���@
�C�M���X�@�����@3�@�@���@�X�s�b�g�t�@�C�A
>>472 20�N�����̊֓��n���P�Ȃ�đ��̔팂��60�@�ɑ����{����80�@�Ȃ̂�
�������Ă����̂ł́H
���{���̔팂�Ăɂ͐퓬�@�ȊO���܂܂�Ă��邵�B
>>474 �C�R�̐퓬�@���͂���Ă�����ƈӋC���V�Ȃ�ł���
���Ԃ͂Ƃ��������R�̐퓬�@���ł͊����@�ɑ���s�����҂��ꂽ�悤�ł�
���ۂ̋��ł̃L�����[�g���ǂ����������͂킩��܂���
>>473 ���O�V�^�̔z���m���Ă�c�H
�ڂ������́H�]�����������́H����Ƃ��c�����H
���ۂɖ{�y�̐킢�ł̓Y�[���A���h�_�C�u�œ��{�@��
�W�����{���[���̎��Ȃ���{���̓g���b�N���݂��Ȋ�P�Œn�㌂�j���ꂽ�@�̂�������������
>>478 ���̎����̓��{�@��65�@���ĈӖ��������ĂȂ��l����������
�r���}����Ȃ�Ă��������A���@100�@�ʂȂ�
�������A�L���u���œ��{���̍q���͂͂قډ�ł��Ă�
����łقډ�ł�����ԂŃC���p�[���������������
�C���p�[���̍��Ɋ��ɂ܂Ƃ��ȍq���͖������
�X�̐킢�ł̓����T�C�h�Q�[���ɂȂ�P�[�X�͂��邯�Ǘ�������P-51���ƔC�����Ԃ�
>>475 �����̃G�[�X���펀���Ă��̂�TF58�i�ߕ��͊�@����������B
�����͂���܂ł̐퓬�œ��{�퓬�@�Ƃ̋��Ɏ��M���������p�C���b�g��������
�i����ɉ����Ԃ蓢���ɂ���������B
�����TF58�i�ߕ��́u���{�@�Ƃ͊i��������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̒ʒB�����߂�
�S�R�ɓO�ꂵ���B
>>481 �}�X�^���O���瓦������Ă����������ǂ�
�N�E�� B-29���o���@�� ���{�R�퓬�@�U����
1944�N11�� 611 4.4
1944�N12�� 920 5.4
1945�N1�� 1,009 7.9
1945�N2�� 1,331 2.2
1945�N3�� 3,013 0.2 ���@�������ח��A�}�X�^���O����q�ɕt���o��
1945�N4�� 3,487 0.8
1945�N5�� 4,562 0.3
1945�N6�� 5,581 0.3
1945�N7�� 6,464 0.02���@�X�Ɍ���
1945�N8�� 3,331 0.01���@�X�Ɍ����ďI��
�Z�Η������̃}�X�^���O
http://www.506thfightergroup.org/mustangsofiwo.asp * :506thfightergroup��1945/7���܂ŗB�ꋏ���A���Ԑ퓬�@����
26 April and 22 June ���{�̖{�y�h�q
(����ȍ~�͊�{�I�ɑΒn�U���~�b�V�����̂݁F���{�@���オ���ė��Ȃ��Ȃ��ė����̂�)
>In operations conducted between 26 April and 22 June the American fighter pilots claimed the destruction of 64 Japanese aircraft and damage to another 180 on the ground,
> as well as a further ten shot down in flight;
> these claims were lower than the American planners had expected, however, and the raids were considered unsuccessful.
> USAAF losses were 11 P-51s to enemy action and seven to other causes.
P51�̋�푹��11�@
http://www.506thfightergroup.org/iwotojapan.asp �r���}�̐킢�ł́A�Η͂��q��x���ɂ����鍑���R�̓������l������
�t�ɇ[�^���ȂĂ��Ă��U�^�ɎO�@���Ƃ������Ă��炵�˂��Ȃق�Ƃ��炵�˂���
>>477 ���V�^(576km6680m)�ƍō������قڑ卷�Ȃ��������������āH
�㏸�͂�Fw190���݂ɒx����
��������P-51�͊��S�ɃK�_���J�i���܂Ői�o�퓬���Ĕ敾�������o�E���̗��̓�̕��Ȃ��
>>483 ���̐N�U��ł��鉫����ʂɍ������������炶��Ȃ��ł����ˁc�H
�D�揇�ʂ��킩��Ȃ��̂ł����A�����ł����O�O
�ꎮ��O�^�̍ő呬�x�A�F�X���邯�ǂǂꂪ�����l�Ȃ낤
�^�T�C�g�ɑ��@�̗��ʔn�͂���Z�o�����ō����x��\�ɂ����̂��������
>>488 �[���U�^�̉ғ������悷���邗
�A���Ɣ�ׂ���唼�̋@�̂��낭�ɓ�����|���R�c����
��s��20����̂P�ґ������Ŕ�s���A�O���}��F6F�Ɍ������P��ꂽ�ۂɑS���͂œ�������
����ɃO���}���������������ɐU������c���Ęb�����邵
�ǂ��R�����c���Ă��n��Ȃ瑊�������̂͊ԈႢ�Ȃ�
F6F�͊z�ʏ�͂���قǍ�������Ȃ��a���������ԒǐՂ��ꂽ��ŐU����Ă邵
>>480 ���{�@age�̔~�{�{�ł͑�A�L���u����ǂ������Ă���낤�H
>>491 ��������邯�ljt��a�����̑���(580km)��
50km���ŋl�߂��Ȃ�܂�����
�l�Ԃ������ďo���鍷�Őڋ߂�����ς�ł铷�̋@�e���\���ɋ��Ђ��낤��
�̃G���W���S���������ɉċ����ς�ł�c��
��A�L���u�͎��O�̍q�Ő킪�s�O��
>>493 �������ɜa����7.7mm����@�e�꒚��F6F��50.cal6�����Ꮯ���ɂȂ��Ǝv�����ǁE�E�E
�a���͍͊ڋ@���������甭�͂Ɏx�Ⴊ�o�Ȃ��悤�ɃA�c�^�͒��Z�b�e�B���O�������炵��
������n40��n140�ɂ���̂͏��Ƃ͌����Ȃ���Ȃ��H
��A�L���u��ł��ꂽ65�@�Ƃ��̓����m�肽����
���{�̕��m��������������{�R�@�ƌ����㔪�����Ǝv���Ƃ����قǔn�Ԕn�̂��Ƃ����������@�ł���
SN���A�n���C�ƃI�[�X�g�����A�Ƃ̒ʏ��E��⋃��[�g���Ւf�������A
>>495 ����Ⴛ�������Ǐ�����ł킴�킴�댯�ȓz��ɂ������͂Ȃ���
�u�܂��������Ă���Ă����Ƃ����Ƃ�������v���炢�ɂ����l���ĂȂ���������
���̕ӂ̐ݒ�ς��͔C����Ƃ���
�Ƃɂ����ɋ����ς߂ǂ��ł�������(�\�_)
>>498 ����Œ����������Ȃ�ċ��C�R�ł����Ƃ����قǎ��s���Ăă\��������B-17��B-24��
�l���@���m�̋������x����炩���Ă��E�E�E
>>500 �@�A�����J����A�j���[�J�h���j�A�Ȃ�I�[�X�g�����A�Ɍ������A���D�c������͂ŏP�����邽�߂ɁA
�i�E�����璷�������������邱�ƁA�ɈӖ��������łˁB
SN���E�K�_���J�i���i�o�̑ւ�A�Ƃ��āA�ˁB
�b������Ȃ��⏬���������H
>>501 �����܂ő���L���Ȃ�n���C��@��~�b�h�E�F�[���̎��݂����Ɋʂɕ⋋�p�����͒u����
�閧��n���肵���Ȃ���
���o�E���Ɠ����Ƀ|�[�g�����X�r�[�����Ε⋋�ɂ͍���Ȃ�
>>503 �@�|�[�g�����X�r�[�ւ̓��{�R�A���D�c�́A
�X��C�̐��E���C�����ۏႳ��Ȃ�����A�����̗��ɂȂ邪�A
�ǂ����������Łu���o�E���Ɠ����Ƀ|�[�g�����X�r�[�����Ε⋋�ɂ͍���Ȃ��v�Ȃ�ď������ˁi��j
�c�_�������̂��}�E���g�������̂�
�|�[�g�����X�r�[�U���͋��R���d�v�����Ė����N�������𑗂������Ǔ^���̒ʂ肾��
>>504 �t�ɂ��q�˂��邪�j���[�M�j�A����݂̊�n�Q�i�|�[�g�����X�r�[����������������{���C�R�q������W�J����j
�̎P�̉����q�s����䂪�D�c���A�I�[�X�g�����A�{�y�����P���������o����Z�i�Ƃ́H
���a18�N�㔼�ɂȂ�Ƒ�^�U���@����̐������������낵����
����܂ł͈ێ��\����
�Ȃ��R���ƌ�m�b�Ŗ���(�h�����ƎN�����Ă����łɋ��R�Ŏ��s���邩������������Ȃ�
�|�[�g�����X�r�[�͑��i���Ŏ��\�肾����
�܂Ƃ��ɖ{��ǂ�Ŗ������炾��H
�����ČR�̃K�_���J�i���N�U��m���Ă邩��̘b�ŕČR���p�ӂ��s�\���Ȃ܂܂������R�ɏo��Ƃ�
>>511 ���A�O��^�̎��_�ł����ƔR���^���N���݂��ė��[���`������
��낤�Ǝv�����P�b�g�z�ǂ��i�\�O���͐�Ŏ����ȂǑ��݂͒m���Ă��j�ł��Ȃ��͂Ȃ���������
������ŏo�����̂����s�������Ƃ��������悤���Ȃ�
�Ƃ͂������a17�N2���ȍ~�A�G��ꕔ�����@����P���Ă�̂�
���݂̘A�g�������n�Q�����o�E�����珇�ɐL���̂ł͂Ȃ�
�����Ȃ�c���M�A�K�_���J�i�����܂Ŕ�̂͂�낵���Ȃ�
��ꕔ���ɑ����n�q����̗��_�����Ȃ��A�Ƃ������܂Ƃ܂�����n�Q���Ȃ���
�ނ����ꕔ���ɂ������Ƃ����̂͑��Ȃ�ʒ鍑�C�R���ؖ����ĉ���Ă��킯�ł���
>>507 �@�I�[�X�g�����A�������n�ɁA�ČR�����͌Q�œ��{�R�A���D�c��_����������̂��A
�ǂ�����Ėh�q������H
���Ɂu��ԁv�ˁB
���̕⋋���[�g���f�₵����A�|�[�g�����X�r�[�ɓ��{�R�@�����݂��Ă��A
�K�\������A�e���ŁA�S���Ӗ����Ȃ��Ȃ����P�Łc
>>512 ���Ƃ��K�_���J�i�����ւ̏㗤���킸�Ƃ�
�ċ��ɂ���P�͂��蓾���킯��
550�\���ꂽ�ʒu�ɌǗ�������̂͊댯���Ƃ킩���ē��R
>>513 ���̋��Ђ͑��̋��_���ς��Ȃ���
�q���n�Q�̉��݂�ʉ߂��镪�A�}�V�Ȃ̂ł́H
>>458 �E�F�C�X�g�Q�[�g�̑���ŃR���g���[���ł���
>>510 >>�L�`���ƕ⋋�v�悪�������c
�Ƃ������
�v��u�����v�͂������c
�̕��������ĂˁH
>>517 �C�R���v������������2�������^��ł���Ȃ��������炾��
�⋋�Ɋւ��Ė��c���̂����łȂ����Ƃ͊m����
�d��ȗ����x���������̂ɖ��c����s���ɔ����Ȃ�����������ȗ����x�͂Ȃ������ɍŋߕς����
�y���d�̓r���}�ɔz������Ă��Ȃ��z�ȏ�A
�p�R�R�}���h�����o�ŕ����̗A�����ĐH���ɂ��]�p���Ă�̂����ēł����������ł���
���߂ĉt��͐퓬�@�Ɣ�r���P���ȋ@���ōςފ͔���͍U�����̐��\�ł͂����Ȃ�
>>519 ���������X�s�b�g�Ƃ������o�����o�J�̂���w
�펞���ɍ��ꂽ�������o������ƕ����邯�ǍU���@���͋����U�����œG�͂Ǝh���Ⴆ��̂�
>>523 ���₩�čH��40mm�Ȃ�ċ�炦���ł����ɕ����႗
�ł����ċ����^�̏ꍇF6F��40km�ȏ�̍��̓f�J���Ǝv����
�����ł�12,7mm6�����肶�ᒷ��������
�͍U�Ȃ璴����瑽���x���Ă��܂��]�݂͂��邯�NJ͔��͂�����������
�����Ȃ��œG�͂Ǝh���Ⴆ��Ȃ�Ă��ꂱ���L�c������A��C�ΑS���������킯����
�a���͍ő呬�x��3�m�b�g�������Ȃ��̂ɎO�O�^�ƈ��^�Ő������ς��̂��ˁH
>>525 �Ԉ�����͏�@�ɑS���������d���Ȃ�t��@��I�ԂȂƂ����b
���A������h�C�c�@�̃R�s�[����n�܂��Ă邩�炠���Ȃ��Ă��܂����̂�����
�O���@�̖͕�Ɏ��߂���Ė{�����������Ă͘b�ɂȂ�Ȃ��A����ϋ�Z���͂Ȃ�
>>526 ����Ȃ�܂��킩��
�����a���̎��ɖ����ȃp�C���b�g�����Ȃ��ȏ�
���@�������Ƃ���ł������m��Ă邵�s���]�X�Ō����܂��퓬�@�����|�I�ɑ����
�ł����Ĝa���ƌ��A�ǂ���������邩�l������c����A���������肪���邵
�{��Bf109�S�����ł��ғ���80%�Ŏ��͎���(�{�y)����
�������������͔̂ۂ߂Ȃ�
�a���͐���������@�̂��Ǝv����
>>507 �|�[�g�����X�r�[�̊�n�̋K�͂ƈʒu�킩���ĂȂ�
�K�_���J�i���Ȃ��y���Ƀf�J���q���͂������āA�X��C�̍��ł��瑍��͂Ŋ��ɕ����Ă�
�����āA������Ƃ���Ă������̓I�[�W�[�̌����n���炠���Ƃ����Ԃ�
��s�@�����ł��Č����߂���B
�������Ƃ��Ă��A�A���I�[�W�[�̊�n����o���o����P�����̂�
�ێ��Ȃ�Ė��̂܂���
�a���͉ΐ�������ׂ��@�̂������Ǝv���̂���
>>520 ���������R�}���h���ł��邩����Ĉ�ʕ����ɂ�点��Ƃ������ꒃ�������
�a���̕ČR�]
>>530 �܂��ɂ���
�R����d�ʂ��ΐ���DB�ŕς���
��p�n���l������DB�͗�p�t�@���t���ΐ����݂ɏd��
�����d���Ŕr�C�ʂ��n�͂��ł����ΐ��̕������͐��\�������Ɍ��܂��Ă邵
�a���^���́A�܂����O���m���߂Ă���w������Ƃ���
����500km/h�����邩�����Ȃ����̗v���̜a���ɖa���`�܂ł���ł�������낤
�C�R�͂Ƃɂ������d����
>>533 ���e�ꔭ�Ō������ꂽ�̂ɕ]�����Ƃ������@�ŏI��肩
>>537 �������3�ǂ��d���߂��ݑ��͔��Ƃ�
���E�ő�̐�͂ɔ��e���Ƃ����̂낭�łȂ��Ƃ����낢�날�邵��
��тƕ]���͂܂��ʂ�
���a13�N�Ƃ����Ί͔�����Ί�i�@�e�j�Ś삵�����Ղ����ɂȂ��Ă�����
�����̌���30���a���C�t���e���x�Ȃ�L���ˍ��O��������v
400m�œ��e�A�����N�����܂łɂ��Ȃ荂�x��������
�ĕ���30���a�������C�t���͓��{�̕����e�݂����ɑ�Ǝڂ��t���ĂȂ����낤
�͏�@���h�e���ĂȂ��̂��v�z���Ƃ͌�����Ȃ�
�W�����b�����AM16�͑�p�̃��[�h�˖@�������ƃ}�j���A���ɏ����Ă���B�܂��ˌ����o����
>>534 >�a���^���́A�܂����O���m���߂Ă���w������Ƃ���
�A�����J�͉�������a���`���̂̎��𑱂��Ă��ۂ�
�J�[�`�XXP-42�͎��s����P-36�̔��W�^���炢�̈��������A
�R��NACA�͂��̋@�̂��g���Ă��܂��܂Ȍ`��̃J�E�����O���e�X�g���Ă���
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc61149/ �����炭���̉ߒ��ŃJ�E�����O���ǂ̒��x�i��ƒ�R���ǂ̒��x���点�邩
�܂���^�X�s�i�[�{��[���^�C�g�ȃJ�E�����O�{�������t�@�����g�����Ƃ���
�G�A�t���\�ƃG���W���̗�p�����ɂ��Ă��m���Ă���
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc61149/m1/31/ ��Řb���o�Ă���XP-47J��XP72�����̕ӂ̃f�[�^�����܂��������Ă�̂ł�
����XP-72�Ƃ��J�E���S�ʂ͖{���Ƀ^�C�g�����nj�둤�͑�_�ɂ��������W���r�C��
R-4360�ł���p��萶���ĂȂ��݂�������
https://oldmachinepress.com/2018/03/05/republic-xp-72super-thunderbolt-ultrabolt-fighter/ �v���y���㗬�l�����Ȃ��A�z���_�݂����Ɍ����邱�Ƃ�����a���`���̂����A
��������l�߂Ă�������Ȃ�ɗL�]�Ȃ̂���
https://digital.library.unt.edu/search/?q5=%22XP-42%22& ;t5=dc_subject&searchType=advanced
����������^�Ȃ��A�������t�@������^�Ȃ��Ƃ������ȏ�����
���@�v�����肩�������ۂ�
�����I�I
NASA�̃y�[�W������܂�܂ȃ��|�[�g�_�E�����[�h�ł���
���@�����ŃJ�E�����O�ς��Ē�R�W���v�����Ă��Ȃ���
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19930093282 >>543 �ł��������ɂ��炭�����悤�ɃK�X�{���x���̋@�̃t���[�g�܂ŕt���Ă��肷��
�������̂������ɂȂ��Ă����ɒ��܂Ȃ��悤�v���Ă�����������
���d�̓��͎���͈�T�ɖ��ʂƂ͌����Ȃ���
>>550 �u�G���W���������͂Ȃ�v�Ƃ����������肫�i���������肾���ǁj�Ȃ�
�͈ĊO�����@�̂ł͂Ȃ���Ȃ����Ƃ����C�����Ă���
���d�����̃e�X�g�x�b�h�ɂ��āA�ɒ[�����Ȃ����̂◃�`��I������
��R�y���ɐ������Ă�̂ł͂Ȃ�����
���Ƃ̓A�����J�ɗ����R-2800�������Ă��炤��������
>>551 �͗��d���猋�\���ݎ��Ă���̂����邯�ǁi����������ł��邪�R�����ڗʂ������Ȃ̂ł悵�Ƃ���j
�����䂪����@�̗��d����Ȃ��Ă����Ƃ������[�g������Ǝv���Ă��܂�
�[���ꂽ��Z���NACA�݂����Ȏ�������Ƃ�
�\�͐�̐v���p�ł��Ƃ�
�����@�́A�\�����͐�ɕK�v�Ȃ��̂͏��a20�N�Ĉȍ~�ɂ������p������ĂȂ���
�ǂ����悤���Ȃ�
�_�͉^�]�����������Ă������I�ɂ�2000�n�͏o�Ȃ���
�n43�͋�P��Q�Ŋ������x��Ă邵�A�n104�ł͌y���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��͐�ɂ͔R��ł������邵
���d���^�x�[�X�̊͐���@�����̉������K�v�����A�����ʼn^�p�ł���Ƃ͎v���Ȃ�
�i���K���ł̉^�p�ł悯��Η͎��d��葁���������Ă邾�낤���j
���������ő呬�x�d�����Ԉ���Ă�
���d�����[�P�艺���Q�x����Ă��
�P�ɖa���`����Ȃ�����������Ȃ�
���d�Ƃقړ�����AFW190A-1�Ɣ�r���Ă݂�B
�m���ɗ��d�́A�������x�������l�K�e�B�u�������Ă����B
���A�X�y�N�g��͋�Z�͐�Ŏ����Ă�
���A�X�y�N�g��͋�Z�͐�Ŏ����Ă�
�����嗃��l�߂����̔h���^�ł����C�����Ă���
�͂ĔP�艺�����Ă�����̂����ɍ��E50�Z���`��l�߂Ă���̂ɂ���ȏ㉽�Z���`�l�߂���Ƃ����̂���
>>562 ��������Ȃ��ē��O�|���ł����������Ă���
���łɂǂ����ǐ킾�����Ă��Ƃŕ�������������
�h�e�ς�����Ɋ���������
�����L����w
�P�艺���͗��[��������Ȃ��Ď嗃�S�̂ɓn���ĕt���Ăă\���͓����̋@�̂ł͕��ʂ̎���
>>557 ���d��FW190A-1
����������ē��I�J�V�C����
���d�͕s��Ƃ�Đ����̗p
1944�N10��
�h�C�c�Ȃ�Me262�Ƃ��Ɠ�����
Fw190D9��1944�N8�������痋�d�����Â��@��
�������������ėʎY�ł��ĂȂ�����
���Y�����l����ƂƂĂ�����̋@�̂ł���Ȃ�
Fw190�Ɨ��d�̖��Â����̂͐��͎��P�r�C�ǂ���
>>557 ��@�@�┚���@�Ȃ�Ƃ�����
���f�@������퓬�@�ŃA�X�y�N�g��傫������Ǝ嗃���d���Ȃ邩�痋�d�͂���ł���
�̎c�O�ȏ㏸�͂͋ǐ�ɂ͈���
>>558 ���d�̃t�@�E���[�t���b�v�͊撣�����Ǝv����
���̃X�v���b�g�t���b�v�͂������
�Đ퓬�@�ɑ����X���e�b�h�t���b�v���ő�g�͌W��������
����ɐe�q���t���b�v�̓q���W���펞�O�ɓˏo���Ă邩���C��R�ł���
��z�������c���\�ŃA���_�[�p���[�̋ɂݔ�
���d���ゾ����
�����̋Z�p�`�d���ĉh�̌��^�����s�G���W������~�������ɂ͂˂�
��킪�ܓ�^(����������)�Ő��͎��P�r�C�ǂ���Ă�̂ɗ��R�@�����������̂�44�N���Ոȍ~���ĉ�����Ă�̂Ǝv��
J2M1�Ȃ珺�a18�N3�����琶�Y�J�n�ł��邪
>>569 �̓����q������̃\�[�X�����Ƃ���ꉞ
���l�Ё@�R�p�@���J�V���[�Y�R�@�ʉ_�^�됅��@P101
�@�x���͒�f�ʉ_�f�a���̔閧�@�����q��
�w�����ł̓v���y���㗬�����k���ɂȂ邱�Ƃɑ������璅�ڂ��A���R�̋㎵���퓬�@�ł́A���̒��z�����Ƃɓ��̂̕��ʌ`�������܂��Ⴍ���`�ɂ��ڂ��Č��ʂ������Ă����B�x
���ȍʉ_���@�`�̂��߂Ƀv���y�������������Ă�
�������Ƀh�C�c�@�̓_�C�����[�G���W���ɔ�ׂĂ����̂��ɗ͂ق�������Bf109��
���d�̓L65�v��ŗ��R�̗̍p�G���W���ł���n42�ɐv�s������A���R�̗p�Ȃ猋�ʃI�[���C��������˂�
�ł�
>>84 �݂�Ƃ���ł��]�铷��w
���d�ɐς�ł���Ɓu�i���ݓ��́v�ɂȂ�G���W�������ȁc
���22�C���s���܂����B
>>574 ���d�����̂������̂͂����܂ł���͓I������_�������̂ł���
���W���]�X�̕������͌�m�b�̂������ɂ����������Ȃ�
�x�z�Z�t�ɂ��̓��̂��̗p������
�@600km/h�t�߂����C�̈��k�����ڂɌ����Č����Ă���
�Ƃ������������֒����ꂽ�c�_�ł��������Ƃ���ɂȂ��Ĕ���������
�Z�t�{�l�������ɏ����c���Ă���
�v���y���㗬�ɂ��Ă͌��y���Ă��Ȃ���
���̕����܂߂ē����ԈႦ���ƌ��킴��Ȃ�
�G���W���J�E���ɗv���镝���đ������̂Ɏ嗃�����ݍ��܂���̂͌����ăv���X�ł͖���
�X�s�b�g�A�C�A�͂��Ƃ��ƃX�s�[�h���[�T�[�A�������Z�@�ɂ����Ă����~�b�`�F���̍�i��
J1M1�ł́A�ΐ�13�𓋍ڂ��Ă�B
���U�̉����o�@�|��������E��Z���U�E�ꒆ�U�ɂ��ā|
�������Ɨ�p�t�@����p����A�@��݂͂������Ȃ邪
��ʂɃv���y���͑��c�Ȃ��猩��ƁA�E���ɉ�]���Ă��܂��B
>>579 �� ���C�R�q��Z�p���̕��������ŁA���̌`���ŗǂ̂��̂ł��邱�Ƃ�\���o������ ����ł���B
�c�O�A�v���y���㗬�Ƃ��������̒��ł͑w����ۂ��͊��҂ł��Ȃ�
�����łȂ�
�y�����O�ł����Ă��w���̈ێ��͔��Ƀf���P�[�g��
�h���̓h���ɋC�A���ЂƂ��邾���ł��̌���O�p�`��ɑw���������
���{�@�̃y�R�y�R�������ʕ\�ʂł͑w���ێ��͊��҂ł��Ȃ�
�ꎮ���U�ɂ��Ă��@��K���X�Ƙg�̒i���̌J��Ԃ��őw���͕���Ă���Ǝv����
�܂藝���ʂ�̍D���ʂ�������͕̂����ɍ��ꂽ�����͌^�����Ƃ����b�ɂȂ�
�]�ނ����ʉ��ł���Y�����ȓ��̂Ɣ�חʎY���ł����̂�����
�ŁA���d�̓v���y���㗬�ɂ��A���i���萫�ɖ������Ă��������H
����s�ł͓��ɖ��ɂȂ��ĂȂ��݂�������
>>579 �ł��o�͂Ȃ瑽���A�ΐ���Z�^�n�����Ȃ�z�ʊ���ł͂Ȃ�����
�Ԃ����Ⴏ�����˂Ȃ���J2M1��J2M2�̑��x�����A�@�̂̍Đv���l�����Ă����͎��P�r�C�ǂ̗L�����炢�����Ȃ�
���ꂾ�����琅���˂ƐU���̃g���u�����Ȃ��O�҂ɋ@��̉��C�Ɛ��͎��P�r�C�ǂ��t�B�[�h�o�b�N�K�p���������ǂ������Ǝv��
�L65�̃n42���ڂ͖��̂���b��
�t�K�����͍����ɂȂ�Ƌ��ȕ����痐������������
�O���}���̐��Y�͂̏����́A�X��-�u���x�z�l�̓w�͂̎���������
�O���}���̋�������ł͂����������̃��[�J�[�Ƃ̏�������������
���a19�N�ĂɃO���}���̓t���C�g�̏����������w���L���b�g�̑��c�ȂɊ��荞��
�ŋ߂Ȃ������d�X���L�тĂ邩��
���������������A�ۃ��J�����������B
�O���}���̃X��-�u���x�z�l�����q�]�ƈ��̕����̂��߂ɑ�����
WW2�̃O���}�����ď����J���̃��f���P�[�X�Ƃ��ďo�Ă��邭�炢�L���ȗႾ�����
>>594 >����҂Ă��̂ւ�̎q�A��̃}�}���N���}�Œʋ��Ă��̂�����ăJ�L�R�������āA
���b���A�l�N�h�[�g���m��Ȃ����ǁA�\�A�Łw�{��̕����x�̉f�挩����
�A�����J�̘J���҂͋s�����Ă��ł���[�ăv���p�K���_���悤�Ƃ�����A
������Ƒ҂ĕn�_���Ȃ�Ŏ����ԏ���Ă�A�Ă������Ȃ�
��풆�͏��q��������̕��i���Y�撣�����̂͂ǂ��̍��ł��������Ǝv����
>>598 �����Ȃ��ǁA����������������A�����x�ɂƂ�
���̘J���X�^�C�����肵������������̂ł悭���グ���Ă�
�{��̕����ɂ��Ă��ƍ���S�����蕥���Ăڂ�Ԕ����ĂƂ����G�s�\�[�h��
�\�A���Ɛl�������̂̓g���C�J����Ȃ���
>>601 ���݂̂�Ȃł����o���ċ��p���]�Ԕ�������I�Ƃ����b���L��̂Łc
�����J�[���u�ԁv�������炵���A����ς�݂�Ȃł����o���Ĕ����Ă��c
���������A���d�̋@��̃G���W���J�E���ɃX���b�g������������āA
�������̃l�b�g�t�H�[�����łȂ�ŕČR�@�̓v���y���X�s�i�[�ȗ����Ă�̂�
���a15�N10���́y���{�q��w��z�ɁA�C�^���A�̃}�b�LMC200�̃X�y�b�N���Љ��Ă���̂��m�F�ł���B
�O���X���b�g�͒��ڗg�͂𑝂����u�ł͂Ȃ�������x�点�鑕�u��
�`�L����ɂ����b�ł̓x�e�����͑��c���̔����ȑ���ŃX���b�g��Е��Âo������ł����炵��
�C�^���A�퓬�@�ɑ����̗p���ꂽ�t�B�A�b�g���14�C����870�n�͂����łȂ����̂�
�C�^���[�̃v���y���@�\�͓Ǝ��̂��̂�����Z�p�͍��������B���{�y��̎Ј����������ѐԒj��
�O���X���b�g���O�����ɐL�тăL�����o�[��������̂ł���Ό}���p�������ł��g�͂͑������낤
>>610 �q��͊w�{�Q����������o���Č��Ă݂���
��͂�O���X���b�g�P�̂ł͗g�͑����ĂȂ�
��s�͊w�̎��ہ@�����q�� P33
���X���b�g�t�������p�̃O���t
��s�@�v�_�@�R�����v�^�������@P61
���R�E�V�}
�p��̒�`�̖��őO�������ɓW�J����悤�ȑO���X���b�g��
���ɗg�͑��₷�l�ȃX���b�g�̗l�Ȃ��̂���������A�A�ǂ��������Ă����ƃt�@�E���[�t���b�v��O�Ɏ����Ă����l�Ȃ��̂����疼�̓I�ɃX���b�g�̖{�`����͊O�ꂻ�������
�ł��㉏�t���b�v�Ƃ������āA�O���Ȃ�S���ɓn���Đ݂����邩�炢����Ȃ�
�X���b�g�̌��ʂł��傫�Ȍ}�p�ŗ����̔�����}����킯�����玸����x�点����ʂł������
>>612 ����͑z���H����Ƃ��\�[�X�L�H
�O���t���b�v�ɂ��Ă������Ă����
�w�����p�����傷��̂��ő�̓����ł���x
�wKruger�t���b�v����ёO���܋Ȃ��́A�O�����a�̏��������^�ɂ����Č㉏�t���b�v���������Ƃ��A�O���ɑ����������N��̂�h���ړI�Ŏg�p����Ă���x
�w�O�����a���傫���Ȃ�قnj��ʂ����Ȃ��Ȃ�x
���d�ɂ͗v��Ȃ�������
�g�͂͋�C�̗�������ɉ����Ȃ��鎖�ɂ���Đ�����Ƃ����
���̖т���ނ��Ă�̂ł͂Ȃ�
>>580 �X�J�C���C�_�[�̑O�g�w�a�s�Q�c�͂S���@����^�̃X�s�i�[��t���Ă�����
������]���镔�i�ł��荂���o�����X�����߂��H���������鎖
���͎��Ƀo���P�[�h�ɓ˓����ď��Ղ��鎖�������������ς킵�����̗��R��
�Ȍ�p�~���ꂽ
>>604 �_�O���XXA-26���X�s�i�[�t������������͂��p�s���ŗʎY�^�ɂ͕t���ĂȂ�
���v���Ίm���ɁA�������Ȃǂ����ċ@����i�荞�܂�ł��A���O���ł���X�s�i�[�ŗǂ������̂ł�
�������퓬�@�͏\�O���팓���Ŏ�������A������ǒn�퓬�@�͏\�l���Ő�p�@�ł�낵��
>>620 ��^�X�s�i�[�̋��^�@���Ă����ƃz�[�J�[�V�[�t���[���[���v��������
�ČR���̃X�s�i����+�v���y���J�t�X�L��͏㏸���\��i���ɂ�鍂�x�������Ƃ��͗L������������
���x���\�ł̓X�s�i�[��������L���ȋC������
>>620 �t��ł͕K���t���Ă邵�A���ł͕��Q����傫�����ɂ͌��ʂ����Ȃ����Ă��Ƃł�
�@��i��Ƃ��{���]�|�Ȃ��Ƃ����ɁA�ނ���r�C��������������l����I��
�������v���y���@�́A�v���y���Ȍ�̒�R�݂̂����
�ǂ��̍��ł����s����͂킩�����
����^�X�s�i�[�̋��^�@���Ă����ƃz�[�J�[�V�[�t���[���[
���낢��ǂ�ł݂��Ƃ��낾�ƃe���y�X�g���V�[�t�����[�̊J���ߒ���
���s���낵�Ă�
�S�ʓ��e�ʐύi�邽�߂ɃJ�E�����O���^�C�g�ɂȂ��ė�p�s���A
Fw190�̑O�ʃI�C���N�[���[�{������p�t�@���������Q�l�ɂ�����
���ǁA�I�C���N�[���[�ƃ|���v�̗e�ʂ��ǂ�ǂ�傫������
���������G���W���݂����ɂȂ��Ă�炵��
�ɂ��Ă���p�t�B���Ƃ���������������
>>626 �V�[�t�����[�̑�^�X�s�i�[�͋@�̎��̂̒�R�����Ƃ������
�G���W����p����C����������ʑ_���Ă��Ȃ�����
>>604 �݂����ɃX�J�X�J�ɂ��ċ�C�ʂ����čl�����Ƃ�
�G�A�t���\�̍l�������Ⴄ�낤��
�V�[�t���[���[���傫���G���W���ɂ�����炸�X�}�[�g�Ɍ�����̂́E�E
�햾��������Ƃ���Ȃ��̂���
���������⎋�E�ȂǓ��{���łǂ���������ꂽ�b�Ɋւ��Ă͗��d�̕ČR�]�����D�ӓI
�����]�����l�������A�p�C���b�g���R���������{�@�̒��ł͍ŗD�G�@��������
https://s.webry.info/sp/f6f-a6m.at.webry.info/201106/article_1.html �ł����d�͒ʏ푬�x�ł���⏕�����d��325�}�C���ȏ�̍����ł͔��ɏd���Ȃ�A�������ŏ��~�ǂ��y�߂���Ƃ�
������ւ�l����ƑΏƓI(�v�ҞH���l���͕⏕���͌y���A���~�ǂ͏d���Ƃ����̂��v�z�炵��)
�����Ă���ɂ��ƃG���W���̐M�������Ⴂ������
���̕\�ʐς͗L�Q��R�̌�
>>624 �����ł�1931�N�W�[�r�[���[�T�[�ɂ̓v���y���X�s�i�[�͖����A���̕č��@����т��Ă�
���ꂾ�ƃ��A�x�A��Z�v�e���o�[�E�|�b�v�X����^�X�s�i�[�t���Ă闝�R�������ł��Ȃ�
>>631 ���̂��Z����������ŗL�����Ƃ����
�����ł�����o�b�t�@���[��C���h�L���b�g�͂Ȃ����ɏ��ĂȂ������낤
����Ƃ��������Ԃ�����̓���́A���̂����������ǂ̌������ǂ���
�ǂ̂����ł͂Ȃ����ɍ��x����
�������v���y���X�s�i�[��傫��������ꂾ���@�̖̂ʐς͖��ʂɑ傫���Ȃ�
��s�@�̋@����D�̓����Ő�������̂���
��������ΐ���Z�^�A�����˂̒��q�����Ȃ�^�]��������
J2M1�ɐ��͎��P�r�C�ǂ����ő呬�x�͎��E���̉����ɔ����������݂�
�V�[�t���[���[���O���t�H���X�s�b�g�Ƃ̖͋[���ň��|���A�܂莆���̊i�����\��]���ꂽ�����L�����Ǝv�����Ȃ��c
���c�ɉΐ���܌^�ł悩����
�܂�����Ō��_�o�܂����
�ΐ����c�����������Ƃ��Ă���
>>636 �x�z�Z�t�ɂ��v�ɂ͊��������������
�P�@���֎��e�̂��߂̓��̐茇�������Ȃ�
�@�i���������͊O��̓��̂Ɍ���������̂�����ē��̂��I�������̋�͓I�n���{�e�̒��Ɏ��e����j
�Q�@�����̌�����瓷�̌�[�܂Œ��J�ɐ��`����
�R�@���������̈���ɑ��đǖʂ��������i�m��������25���j
��������ɑ��đǖʂ��傫���قǎ嗃�Ɛ����������߂��ł���X��������
�i���{�q��Z�p����s�@�y��s�@�̐v�@�@�k�E�p�Y�}�j�[�@�o74�@��W�\�@�����e�ρj
����ł��ǂ̏d���Ƃ��L�����x��ł̑��c���Ƃ��ւ̂�����肪������
�R�̐v���̗p���Ă�
>>589 �u���[�X�^�[���ăO���}����J�[�`�X�ɂ͋y�Ȃ����[�J�[�Ȃ́H
F2A�ł�SBA�ł��������������̗p����Ă����Y�Ɏ�Ԏ���Ă₽�玞�Ԃ�������
���̍��ɂ̓��C�o�����[�J�[�͂�荂���\�ȐV�^�@���J�����Ă�Ƃ�����Ȃ̂���B
�u�����[�X�^�[�͂��Ƃ��Ɣn�ԃ��[�J�[�ő�ʐ��Y�Ɍ����Ȃ�
��ʓI�Șb�����ǁA���̎����̃��[�J�[���Ă�����������肪�����
�O�H�́A�����ɂ���ΐ��ɂ���A�����^���ɐ������Ă��镔�ނł���B
�u�����[�X�^�[�̓A���~�̉��H�ɒ��������ߍq��@�̉�����������
�����˕t�������@�ł����Ȃ�A�������ɋ����Z�Z�^�ς߂�����
�����̓[��G�o���u�̊J���ɐ������ăL���u���^�[�ŎO�H�𗽂��ł����J���Ɏ��s�����O�H��
���_�͐����^�����ŗ���1800�n�͂̂悤����
>>653 �����^�͒����̋Z�p�ł��O�H�̋Z�p�ł��Ȃ�����
�h�C�c�̃p�e���g�������Ă�������
>>655 �_�ɐ����^�����Ƃ��ˁ[��
�����^�łȂɂ�邩�킩���ĂȂ��o�J
���_�͉ΐ�2x�A�_�ł��Ȃ���ΐ����^�����ł��Ȃ���Ȃ����������H
�����ˁA�R�����ˎ��łȂ��Ɗ�{�I�Ƀ��m�ɂȂ�Ȃ�
���ۂ̂Ƃ���A�_��2000�n�͒��߂Đ����˂Ȃ��̕����ǂ������Ǝv����
>>657 �Ⴂ�܂��A�O��
�����^�ʼn����ς��̂��킩���ĂȂ�
>>658 ������ƈႢ�܂��A�ČR�̐����^�͒�����������
�n�͂͏オ���Ă�
>>660 ������f�}������ˁ[��
�G���W���X�y�b�N�̌����m��Ȃ��߂�
>>657 ���܂_��
���d�Ɠǂ݊Ԉ����
�ΐ���2x�͐����^�̂悤����
�����^�łȂ��Ƃ����\�[�X�́H
�����^������1���܂ł̂悤�Ɍ����邪
���_�̔����@�͉ΐ���Z�^�n�Ȃ̂Ő����ˑ��u�t���Ă��
���Ƃ��Ɨ_�Ƃ����G���W���ɂƂ��Đ����^�m�[�����˂͑z�肷��Ƃ���ł͂Ȃ��A��������̈����Ȃ����R����100�I�N�^���R��(91�I�N�^���݂����ɕ�����������������鍬���������܂����ĂȂ�)��z�肵�Ă���
>>663-663 ���������Ƃ��A���Ⴂ���߂�
91�����R�����ǂ��������̂��킩���ĂȂ�
���ƁA�R�����˃|���v�͓��{�̃p�e���g����Ȃ�����
�h�C�c�̃p�e���g�ˁA�����܂Ńh�C�c�̐�s�Z�p��������
������g�킵�Ė���Ă邾��
����ƃA�����J�̃n�C�I�N�ɂ��Ă����Ⴂ���Ă�
�ǂ����ɂ��Ă������^�ɂ��Ċ��Ⴂ���߂�����
�A�����J�������^�g������
�A���R���̔R�����m��Ȃ��߂�
91�I�N�^����87�I�N�^���ɃC�\�I�N�^�����������ăA���`�m�b�N�������߂����̂ł���A92�I�N�^���̑�p�R��
>>665 �Ȃu�m��Ȃ��߂��v��A�Ă��߂��ĕK���Ƀ}�E���g��낤�Ƃ��Ă��邪�O�H�̔R�����˂͐�O����̓Ǝ��̌����������Ɋ܂܂�Ă��āADB601�́A�h�C�c���瓱���������̂Ƃ͂܂��ʂ̌`�������H
�ߋ��킩��z�C�z���ꂽ�V�����_�[���O�̋z���Ǔ��ɕ��˂����
�V�����_�[���ɒ�������DB601�̌`���Ƃ͍��{�I�ɈႤ
�m���A�����J��100�I�N�^���ł͖O�����炸�A�X�ɓY���܂𓊓�����100/130�O���[�h�R���ɂ��āA�푈���͂����炪��͂��������
��̎O�H�̔R�����˂̃��|�[�g����ǂ܂��ɂĂ��Ɓ[�Ȏ������Ă�Ȃ�w
>>�R�����˃V�X�e���̊�b�������̂́f35 �N����J�n����A���É�ᢓ��@���쏊�̕� ���Ɨ�(�f38 �N)�ȑO�Ɏ��p���x���Ɉ����O�̐��ʂ����߂��Ă����B����āA�@��̃^�C�� ���O�͒P�ɌR���̈ӎv����A�O�H�Ɠ����@��Ƃ̑����Ƃ������ɋA�������߂��ėǂ��B
���������u>>�h�C�c�̂��g�킵�Ă�����Ă邾���v���Ƃ��āA�����牽�Ȃ�w
���^�G���W����
�n40�̎O�H���R�����ˑ��u�Ȃ�C���̋L�^���͕҂ɂ�������ڂ��Ă邩��m�F���悤
>>673 ��������������Ȏ��͑���������I���������I������܂�����˂����I
�C���ɂ̓n40�̃��C�Z���X�̐������o�܂��ڂ��Ă��āA���܂ł̊ԈႢ���悭�킩��
�C�^���A�͍��͓͂��{�̂��͂邩�ɂЂ�����������
�O�H�̋����G���W�������Ԏ哱����
�O�H�̋����͐v�����[���햱���u���E��̃G���W���Ő��E�ɔ��肽���v�Ƃ�����]�������Ă���
���˂Ă���̓䂾�����O��13�~���Œ�@�e�̊J����
�����l�Z�^�͓����A�����x���\�ɓ��������
>>359 �̕⑫�B
�u13���̐���v�ł��錎�����h2x�Őv���Ă��킯�����A
�u14������v�̗��d���h2x�O��Őv�����Ƃ��Ă��A�S���s���R�͂Ȃ��B
�܂��A�������x�𗎂Ƃ��d�g�݂Ƃ��ẮA�u�`�������W1934�v�ŁAFi97��Bf108�o���ɗp����ꂽ�A
�O���X���b�g�ƃt�@�E���[�t���b�v���p�̋Z�p�A
��݂���6���@�Ƃ��āu���{�ł��A���ς݁v�������̂ɂˁB
���̋C�ɂȂ�A���x�͈͂�5�ɋ߂�����{���������̂ɁA
��Z�����x�z���A���������N�Ɏ����Ȃ��������Ƃ��s�v�c�ł���B
�ނ���A�A�����J�̂悤�ɁA��n�̓G���W���ł�����悤�Ƃ̕��������ˁB
�C�R���A���a14�N�ȍ~���A�������쑱���Ă���A�����̏��c�����@�Ƃ̑����ŁA
�����Ƒ����ɋǐ����ɓ��ꂽ�����H
���R�́A�퓬�@�͒����E���ȂǁA��^�o�������@�͒����ƎO�H�̂悤�ɁA���\���킹�Ă����킯�ŁB
�푈����ł����A�x�Ԃ̑R�n�͐��Ɏ��삳���Ă����炢�����B
�C�R�Ƃ��Ă͏��c�̉ΐ������^���\�z���Ȃ�����ɂ�
������A���̋ɏ����ł͂Ȃ������Ǝv��
�����ăG���R��20mm�����Ď嗃���g��A�ΐ��Ŏl����ɁE�E�E
�G���R���͏e�g�̎��͂Ƀ��R�C���X�v�����O���͂ݏo���ŃR���p�N�g�Ȃ��ǂ�
�嗃�g���20mm�ςނ��߂����邪�A���c�R�^���l���Ă����̘H����������Ȃ���[��
�@�̂Ɣ����@�̐��Y���_����������Ă�Ƃ�����ׂė~�����Ǝv���̂��H
����M4�V���[�}���̖ڂ̑O�œ�����������́H
>>689 �����͑����I�E�`�̓E�`�I
��B��s�@�Ƃ��A���C���k�d�Ȃ�炸
>>690 ���Ⴀ�E�`�̂����ł������
�Ƃ肠���������͔ɉĂ�ꂗ
�~�����x800km�����Ă�Ȃ�����A�����������
�X�s�b�g�┹�ɓ���Ă�낤������ς�@�̂��V���������ǂ���
�����������̓G���W���ȑO�̖�肪�ł�������
>>664 ���̐푈�Łw�����x��₦�A�哝�̑I�܂łɃ��[�Y���F���g�ÎE�����
���ĂƂ���win&win������
���d�ɂ̓|�b�h�^20�~�������đ��x�ቺ���N����������
>>689 �����I�ȋ�����肻�ꂪ������Q�ɂȂ邩�̕����d�v���Ǝv������
�����@�ƈ���ăG���W���Ȃ�Ă���Ȃɉ^�Ԃ̂�����킯����Ȃ����A
����đg�߂ΏI��肶��Ȃ��Ăǂ������������̑O���ɂ͕�[���i�͂��Ȃ���Ȃ��̂���
�펞���̓����̓S�������m��ljh�G���W���̋t�Ŗ��É��ŏ��c��낤��w
�ČR�@�ł�����Ȗ����ȋ}�~�����x�����Ă��Ƃ͌����̂�
�@�������̒����10�{�̊͏�@�����@�ނƏ����p�ӂ��Ă����m�b�͂Ȃ������̂�
10�{�Ƃ��������Ɉ�̉��̍���������̂�
>>697 �����800km/h�I�[�o�[�̏o�����ǂ����Ƃ������A�����Ń_�C�u���Ă�
����݂����ȋ@�͈̂��肵�ăR���g���[���ł�����Ă��Ƃ��Ǝv��
�nj������܂߂Ă��̕ӂ̐��\�͒P�ɐ�����̍~���������x�݂Ă�
���܂�悭�킩��Ȃ��A�ڈ��ɂ͂Ȃ邯��
�O���+�\���Ƃ�����+�\��+���Օ��Ƃ����˂��B
�X���`�ɂȂ����Ⴄ������ɑ���]�����A�̂͌y�����
�C�R�̐퓬�@���͊�{�I�ɕ�͍q����ւ̓]���O��
>>703 �������x�z�Z�t�̒����ł��A�C�R����C�e�X�g�p�C���b�g�̏����c���̒����ł�
�u�͐�Ƃ̑��ݓ]���P���ւ̔z���v���S��������Ă��Ȃ��̂��䂾�ȁ����d
�C�R�͗��d���ǂ�Ȕ�s�@�Ɏd�グ�Ăǂ��g�����肾�����̂������ς蔻��Ȃ��B
�����A�j���̊J����q�������Čv��ʂ�ɐ���@�̗��d�������z������Ă�����A
�C�R�͊͐�p�C���b�g�Ɨ���z���p�C���b�g�̌P���ے���l������������肾�����낤���H
�C�R�Ƃ��Ă͕�͍q����̒n�ʂ�������ɔC���Ă邩��
�C�R�̋����͊�n�q����Ɉڂ��Ă���
���d�͉^�����\����������Ȃ�
>>707 �ނ�����c�݂����ɗ��������Ȃ炠����߂������������݂ɗ��ł���������
�E�l�@�����������Ă̂͑����f���������̂ł�
���`��������
>>693 �Ȃ��Ȃ�
���C�e����
52�^��FM-2�Ƀ{���N�\�ɕ����������
�[����͒��E�ᑬ�ł̂݉^������������
�����i400km��j�Ŋ��ɉ^���������������|���R�c
400km�ȏ�ŏ펞�킦���s�@�ł͂Ȃ�
���ۃ��C�e��FM-2��
�c����E�_�C�u�E���[��
�S�Ăɂ����ĕ����Ă�A��������9�C���̊ȑf�ȃG���W���̔�s�@�ɂ���
�G��Ȃ�
>>706 �����̎����A343�̎��d�������ł����V����̂��A�A�����J�̕��ʂ������肷�邵�ˁc
�ғ��@���\�ł���Ȃ���A���[�_�[�ɂ����G�ƁA��{�O�O�ȂǕS��B���̃x�e������������
���a18�N�N���̃��o�E���ɁA�^�����ɓ������d��S�@�P�ʂœ����ł���A
�Ƃ͎v������ǁB
��p���A�t�B���s����A�����Ɋւ��ẮA10���ǂ̋�ꂪ�ςސ퓬�@���R�U�炳�Ȃ��ƁA�G�͑��i���ԁj�U��������Ȃ��A
�Ƃ����n���f�����z���邽�߂ɁA�L�����[�g10��1�̂悤�ȃE���g���퓬�@�A�܂��͒��l�p�C���b�g���K�v�����A
�n�C�I�N�R���̗ʎY�ɓ�V���������̓��{����A����ጵ�����łȁB
>>697 �����������Ǒ債�ċ����Ȃ��ĂȂ�����Ȃ�
�^�����\�Ō����ނ�����Ă邵
>>710 ���ɋ������Ȃ��[�b�Ȃ̂ɂǂ����߂����炻�̒����Ɏ���̂��H
�w���d�͈��]�ɂɂ��ĊO�A���₷�������B�������ė��̌ܓ�^���f���Ȋ����ł������x
>>709 �@>>���`��������
���`�̂ǂ����ǂ������̂�������
>>713 ���Ă��~����т�332��͗��d��������ɉ����ė���ꂾ��
�Δ����@�Ȃ爫���Ȃ�����đ�g�̕]���͕ς���̂���Ȃ���
�ނ��낻��ł����Ȃ��đʖڂ�������{���ɂǂ����悤���Ȃ��킯��
���d�̔��w�����̗��`�͎����̗\�����Ȃ��ˑR��������X���������������ŗ���B9�n����������ۂł��ɂ₩�ɋ����ω�����̂�
��킪�{���Ɏ���400km�œ����Ȃ��Ȃ�퓬�@�Ȃ��x������Ɏg�����Ⴂ�Ȃ���
���C�e���C��Ō�q���ɓ˓��������U�@�̌�q�̗���
���C�e�͋@�̐��\���^�p�̍��������ꒃ�߂���
2000�n�͂�F6F-5�͂��납2540�n�͂�18�C������P-47D�����������
���R�̈Ӗ��̂���u�q��v�͎����C���p�[���ƃt�B���s��
�ꎮ��t�@���̑Œʂ���ɂ͎l����X���̕������������ł́H
>717
���͎嗃�`��ɂ���ĕ⏕���̗��^�̃q���W���[�����g���傫���A�ᑬ�����������ǂɗv����͂�80�|���h���x�ƁA�ČR�̑z�肷��50�|���h�ł͍ő�X�g���[�N�܂œ������Ȃ������悤��
�⏕������������ɂ��ċ����ɉ����ł��Ȃ��������̂���
�����^�Ńo�����X�^�u���t��������̌^�͂܂��p�~�ɂȂ��Ă邵�⏕���̌����Ȃ��Ȃ鑬�x��
>>725 �l�͂œ������Ȃ��Ⴂ���Ȃ�����y��������Ȃ�
�ČR�@�����l�������
�������ƂŕW�I�@�ɂȂ���P-39�ł����⏕���͕z������
>>717 �⏕���̑��ǂ��d���Ȃ�A�Ƃ͎w�E����Ă邪�u�^���ł��Ȃ��v�Ȃ�Ĉӌ��͂Ȃ����Ȃ�
���̂܂ɂ��u���́A�����ł͂������Ȃ��A���@�������̂ł��I�v�u�ȁA�Ȃ��Ă����I�I�v
�݂����Șb�ɂȂ��Ă��肷�邯��
>>727 �������̑ǂ̌�����ǂ����邽�߃X�s�b�g�t�@�C�A��P-47�A���{�@���ƗȂ��������ɂ��Ă��ł�����
�ʏ펞�͋t�ɏd���Ȃ��ł�����
�����ʉd�̋@�̂ʼn���Ɍy�����[������ƃX�s���ɓ����ĉł��Ȃ��Œė����邱�Ƃ����邩��˂�
>>720 >P-47D�̃g�b�v�N���X�G�[�X�p�C���b�g����@������1210�n�͂̔��V�^�Ȃ�ė�̑O����
D�ł�C�ɂ��߂������^�����đO�ɏ���������
���ƎO�^����Ȃ��ĕ��ʂɓ�^��
�����������P-47�Ɛ킦��Ȃ�Ă͕̂ʂɒ��������Ƃ���Ȃ�
>>732 �O�ɏ��������Č����Ă������
������������ɂȂ����͎̂ӂ�A�X�}��
710�̃C�~�t�ȕԐM�ƃC�L��ɑ��Ă����瑽���͂ˁH
�������������܂�A�������̂�>444������
���d�̒�������Ȃ����Ęb�A���m�b�g�ȉ��Ŏ���������Ă����J�^���O�l���������̊��o�A���c���̃K�^���Ƃ��ł���Ă��n���p�C���b�g���������Ƃ�����Ȃ��̂ƂӂƎv���Ȃ�
�����̗\���͎嗃�̍����Ŕ������闐�����������Đ��������̏��~�ǂɓ����鎖��
>>734 �a����l(�T)�����@(�U)���o��(�V)�̔���
�N��f�r���[(21)����C(32)���J�^���O�X�y�b�N�͏オ�������ǁE�E�E(52)�̗�킶��
�S�R�ς���Ă��邵��52���21�̂��D�܂ꂽ���Ęb������
P-47D�̏ꍇR-2800-21W��R-2800-59W�̈Ⴂ���y���̉e�����ł����Ǝv��
�ύX�����烋�t�g�o�b�t�F�������Ȃ��܂łɃ{�R���Ĉȍ~���̖ڂ����邱�Ƃ͂Ȃ������c
>>716 ���w�����͓����������ŗ��[�Ɍ������ĕ��ʂ̗��^�ɂȂ��Ă邩��
�������̎��������������Ă���Ɨ������邪
�����Ńe�X�g���Ă邵��肪����ΑȂ��͂�������
�v���y���㗬�Ƒ������̂����������\���͂��邪
���^�P�Ƃ̖��Ƃ͎v���Ȃ�
>>736 WW�U���@�ŃX�g�[���X�g���b�v�t���Ă�@�͉̂��������������H
�R���Z�A�͂ނ��덶�E�̎����𑵂���̂��ړI����
�t��P51�Ȃ͎�֎��e�̒��o��������ʂ̃��C�����������Ă邹����
�������������ɂ����Ȃ��Ă�
H�`�͒��o�������Ȃ�������
>>736 ���ۂǂ������Ă邩�m��Ȃ�����Y��������
�\���̂Ȃ�����������������Ƃ���Ȃ��܂ܐ����ɂȂ��Ă�̂����狳��Ƃ��Ă͖�肪�Ȃ������̂�������Ȃ��A�Ƃ������ꂾ��
���d��P51�����؏��őΐi�p���ʼn�G����
>>710 >�~�����x800km����
�̕ӂ肾�ȁA�[����͂����܂ł���͊ɍ~���܂ł̐������x��
�}�~���ł���P-40�Ƃ����X�̐퓬�@�Ƃ͎����̈Ⴄ
���@�Ȃ�
�@�̋��x���ʎ����Ŏア
>>717 >>728 �[���킪�����ŏc������_���ɂȂ�\�[�X�Ȃ�Ċ��ł������
����ȊO�����ł����邩��
>���O�Y���̒����ɂ��ƁA����
>���x�������Ȃ�ƎO�ǂ��d���Ȃ�A�Ƃ��B
>
>���x�͎�����500�`�ȏ�o��͎̂��������ǁA�h�b�N�t�@�C�g�����ɂ�
>300�`400�`���炢���K���ȂƂ������Ă������B
���O�Y�������n�t��
>Claire Channault found out before the US entered the war the rules when fighting a Zero or Oscar:
>Keep your speed up above 230 MPH. The Zero had lousy controls that stiffened up above 230-250
Claire Channault���ɂ��ƃ[�����230-250�}�C���z����lousy controls������A���ȃR���g���[���ɂȂ�Ƃ���B�i���[���Ɍ��炸�j
230�}�C����370km
>The Zero could not keep up with Allied aircraft in high-speed maneuvers,
> and its low "never exceed speed" (VNE) made it vulnerable in a dive.
�[����͕ʂɃ��[�������ł͂Ȃ��A������ł̋@�����S���_��
���Ɣ�ׂă_���Ȃ̂��A����͋�킪���藧���Ȃ���ԂȂ̂��H
�ĕ�������Ă����A�ČR�@�Ɣ�ׂă_���Ȃᖳ���́H
���x�����킸�ɉ��X�ƈꌂ�q�߂�����������
�����Ă����������Ɨ��ɕ���������Ɠ݂��Đ����c��Ȃ��ƌ����b�ɂȂ�
�t��Ta152���炢�̑��x�ɂȂ�Ɓu�o�����X�v�Ő����ʂ̋��݂���������
���{�̏ꍇ�AB-29�ɂ���Ēɂ��������ԍU���͔����@�H��ɑ�����̂�
>>748 ���������@���Y����ł��Ȃ������q�퓬�@�������ς����ł���悤�ȏɂȂ�Ȃ��̂�
�鍑�̒n���I�����������ƌ��������������ǂ����ȁH
�ČR�p�C���b�g�ɗ��Ɣ��̋�ʂ��t���Ă������Ƃ���
�ꎮ��F���@��s��R�P������F���R��с@���i
>>742 �H�H�H�ǂ̃\�[�X�����m�����750km���˔j�ł��Ȃ�����c
800km�͌���̎��������Ă��
>>744 �����ɂ���
�U�^��21�^(�`32�^)�����������ƂȂ�����������Ă����������Ȃ�
750�������悤�ɋ�ʂ��Ė����������ăP�[�X������
>>751 ���c���ʂ̓G�@���ォ�猩�Ă�ꍇ�͏㏸����̖���
�g���B����_����ɂ���Ȃ�C�`���o�`�����邩��������
���d�ɗ����d������
�O�ɂ�������Ă�����
�}�~���ϋv�����̂Ă��d���Ȃ����A�X�y�N�g��̎嗃���ĈӖ��Ȃ́H
���d�̑�������L�����������Ȃ��ł������
�����̔�e�Ɏキ�Ȃ邵
�L���������S���ɐ�߂闃�f�ʌ`�̊���
�u�[���ƈ���Ď苭���v���Ă̂̓A�����J�̕]���ł������ۛ����N�\���������ǂȁc
>>740 ���풆�Ɏ����X�s���Ƃ��P��������ĂȂ��ɂ���������
��肱�Ȃ��ĂȂ��؋�
>>741 ���d��P51�̎嗃�v�͕ʂɎ��ĂȂ�
���w�����Ɗ��S�ȑw����
���[�Ɍ����Ď狌���������d��
���U�߂�P51(���[�̍ő嗃���ʒu55%)
���\�ʂ̕������ł����Ȃ荷������
>>755 > �ČR�e�X�g���[�_�[�u���������ȁI���̖��O�t����ɑ��������I���d���H�m�l�Ŏv���������O�ł�����v
����������ƈႤ����B
�u���d���H���d��������Ɖ��ǂ������̂��ȁB���d�̃R�[�h�l�[���ɃT�u�^�C�v���邾���ł�����v���B
���x���オ��Ƒǂ��d���Ȃ�͓̂�����O�����A�����ɐU��̂ɓK�������x������i���R�A�ō������Ⴂ�j�Ȃ�Ă̂�������O�ŁA
���S��ʌ݊��łȂ��āA���̋@�̓��ӂȕ���Ɏ������߂Η��Ƃ���Ȃ��Ȃ瑶�݈Ӌ`�͂����
>>755 �I�X�J�[�̕����[�����育�킢�Ȃ�ĕ]������́H���������ƂȂ�����
�j���[�M�j�A�ł͗����^�����a18�N�ɂ��Ȃ��Ďg���Ă��̂�
>>757 ���̃R�[�h�l�[����������F�l�m�l�o�R������c
���������ʂȂ͎̂���
>>760 http://home.f04.itscom.net/nyankiti/ki43-top1-page1.htm �������Ƃ��H���\�ȒP�ɏo�Ă��邯�ǂ����ǂ��Œ��ׂĂ���H
>>762 ����̂ǂ����Ă��������Ɣ��̔�r�Ȃ́H
�ΐ퓬�@�����ł��Ȃ��퓬�@��
>>763 �t�ɕ������A�}���A�i�ȍ~���52�^�̍ĕ]���͉����ōs��ꂽ�H
�ʉ_�Łu����肸���Ƃ͂�[���v����Ă�Ԃ�
���͇V�^�ŃO���}���u������ɂ��Ă�A���\�̗����鍂�x6000�I�[�o�[�Ŏ��d(583km)���݂�576km�Ȃ�ďo���Ă邵��
���R���猩��F6F��P-40����^���U�R�Ƃ��������ĂȂ���
���ꂪ�����Ă����̒m�����牫��ւ̃X�v���[�A���X���m�C���[�[�ɂȂ����������1,5�ǂ̓��U�ꂽ��ł̕ČR�͒��̑��Q���낤
�C�R�̐l��2500���ŗ��R1400���������͍��v2500�@��������������60�̑�j90�ŏ����j��220�A����A�s�\��110
�}���A�i���p��(����)�����v����قړ���������ˁH���nj��������̂��Ȃ���
�ꎮ��O�^�́A�摖���čb�̔����@�˂̗ʎY�����Ă��Ȃ���Ȃ��Ƃ������x�ɖ��Ɍ���
�ꎮ��3�^�̍ő呬�x576km/h�͉����\�[�X�Ȃ�H
>>767 �������762�Ƀ����N�\���Ă�̂ɂǂ��������R�������Ċm�F���Ȃ����H
>>768 ���₾���炻�̏o�T���Ȃ�Ȃ낤�ȂƂ����b����w
�戵�������̗ނł������l�Ƃ͌���Ȃ��Ȃ��ꂪ
>>769 �������������A��v�����̍��ڂ�
>�ꎮ��O�^�v�喱�҂ł���哇����̌��e�y�ѓ��{�q��@���W�i�����ҁj
>���Q�l�ɂ����Ă��������܂����B
�Ƃ����
�����������f�Ȃ�Ȃ���
>>771 ����ȏ�ɐM���̂����郂�m������������ǂ˂���
���ۖ���s200���Ԍo�߂�����荠�ŏn���H�̋@�̂�
�o�����Ăł܂��@�̂�����ĂȂ��㖢�n�ȋZ�p��������p�����O�̋@�̂���
�������Ė�ɂ͂����Ȃ��̂͂��邵�S�����グ��ɂ͂��ꂱ���_�̖ڂ��Ȃ��ᖳ����
�����܂Ŗڈ��Ȃ̂͏��m���Ă�
>>765 ���ׂāu���ɑ��Ĕ��̕����苭���v���肫�̌��߂��ł����������
���ړI�ɂ�����ؖ�����ɂ́A�N�̂����Y�������(�A���R�̔��̕����苭���Ƃ�����)�����p����ׂ����Ǝv�����ǁA����͉ʂ����đ��݂�����̂Ȃ̂��낤����
>>773 �܂�762�Ő�ɕ������������̎���ɓ����Ă��炨����
���̊�Ȃɗ��M�����ς͂ǂ������������Ō`�����ꂽ�̂��ȁH
>>774 ����M����Ƃ́H�����������������̂���
�����������N�̂����u�[���ƈ���Ď苭���v���Ă̂̓A�����J�̕]���v�Ȃ̂Ȃ炱��ȏ㉽�̈Ӗ����Ȃ���
>>775 �����Ƃ����v���Ȃ��������Ă邩��˂��AID�`���J�`���J�ς��ĕs�R�ɂ܂�Ȃ�����
�@����̖��Ń����N���3�b�ȏ�ǂ�ł͂����Ȃ����܂�ł�����̂��ȁH
>>776 �H
�u�A�����J�̕]���v�������o������ɂ̓e�L�g�[�ȑz������Ȃ��Ă����Ƃ��́u�A�����J�̕]���v�������Ă����Ƃ����p���Ȃ����Ȃ��ǁA���ꂪ�ǂ����ė��M��Ɍ�������H�H
�m�F�����ǁu�A�����J�̕]���v�Ƃ��́A���������̂��Ƃ������̂����H
>>777 RwyyFmCG�Ƃ������p�����������Ă���̂ɉ��Ŗڂ�ʂ����Ƃ��Ȃ��̂��H
�ڂ�ʂ����玀��ł��܂��̂��H�Ȃ�E�l�ƂɂȂ肽���Ȃ��̂ł����ɂ͏����܂���(�����G)
>>778 ������o�T�̖����A�A�����J�̒N�����������m��Ȃ��l�T�C�g�̑������̂܂����������ǂ��M�p������āH
����͂����܂Łu�����������\�[�X�v�ł���������
���a�̃��b�N�{�̃��C�^�[�̋r�F�Ƃ����S���M�����Ⴄ�h�H
>>779 (���̐l�ǂ�Ȏ����Ȃ��b�b�b�ΐ��������Č�����낤�Hw)
�A���R�ŋ��퓬�@�Ɩ�����P-47D�������Ɣ������Ƀ����T�C�h���߂��Ă���
�����ň�����������A�j�[���E�J�[�r�B�@��@���������肵�Ă�̂�
����ȋ@�̂��m�[�}�[�N�ɂ��Ă�����Ƃ������ł��ˁI
>>780 ������A���̂����u�A�����J�̕]���v����Iw
�t�ɂȂ�����ȊO�L�ۂ݂ɏo�����ł����ˁH
���{�̈ꕔ�̃I�^�N�̊Ԃł܂��Ƃ��₩�Ɍ����ʐ������������̕����ɗ��t����ꂽ���̂悤�ɏ����Ȃ�R���r�j���b�N�{�̃��C�^�[�Ɠ����x������Ȃ��́H
�����ăm�[�}�[�N�Ƃ́H���M�ҔF��Ƃ����A�u�ے肵������M�ҁI���m�[�}�[�N�I�v�Ƃ��ɒ[�߂��Ȃ��ł����˂��H
>>781 �������������̂��悭�����I
����ȂɌ����Ȃ�L�~���u����[������(�V�^)�������悤�ɑΏ��ł���v���Ď����o���������������ȁ[
>>782 �N���u(���̐l�ǂ�Ȏ����Ȃ��b�b�b�ΐ��������Č�����낤�Hw) �v
�Ƃ�������A������O�ɁA�u�u�[���ƈ���Ď苭���v���Ă����A�����J�̕]���v���̂��̂������Ă��ĂƂ������ƂȂ��ǁA������邭���ɂ܂��������ǂ߂Ȃ��̂ˁH
������{�l������Ɍ����Ă邾������Ȃ��ł����˂��H
>>755 >�u�[���ƈ���Ď苭���v���Ă̂̓A�����J�̕]���ł������ۛ����N�\���������ǂȁc
>>762 �̃����N��ɂ͉��������ǂ��납�|����Ȃ������
�Ȃɂ������Ƀ[���ƈ���ā`�Ƃ������Ă�̂�
�T���Ƃ��Ӗ��S�R�������ĂȂ���Ȃ����A���̐l
���ꂪ�������Ƃ����爹�����͈ꎮ���4����ƍ������Ă�̂ł�
>780
�v������
>788
>>784 �������ĂR�C�c��
�l�̌����Ă邱�ƂɃP�`�t���Ă邯�ǂ�Ȏ����Ȃ琳�����Ǝv���́H���킩���I
�E�E�E�ے肷�邾���̍���������́H������Ȃ���H
�������̂��O�̖��G���_��������
>>787 ��Ȃ������Ȃ�
�����������Ƃ�788�ɂƂ�ꂽ���ǍŗD�G���ŋ�������
>>791 ���t���̎��Ȃ��b�������������݂������̂悤�Ɍ����̂�߂ĂƂ������ƂȂ��A�Ȃ�����ŗ��M�҂ƌ��߂Ă�����̂��c
�܂������v�l���u�ꂩ�[�����v�̒P���]�Ȃ̂��ȁH
�ʂɔ��_���悤�Ƃ��Ă����Ȃ��āA����͋�̓I�ɒN���������Ɣᔻ���Ă�����Ă̂����ĂȂ��悤��
�܂����A�u���������ł��D���Ȃ瓯�ӂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��I�I�v�Ȃ�Ďv���Ă�́H
�A�����J�R�̉��Ƃ����l�̏،����邢�͉��̕��ɂ��������Ă����
����o���Ȃ��ăx���x����10��20�������A�˂��Ƃ���ł��傤���˂����낤��
�_�_���炵�āu���O�͔�����̂��H�v�͔n��������
>>�l�̌����Ă邱�ƂɃP�`�t���Ă邯�ǂ�Ȏ����Ȃ琳�����Ǝv���́H���킩���I
�m�\���ȉ�����
�����ė����ł��Ȃ��t�������Ă���̂���
���̎����Ȃ琳��������
>>781 �A
>>785 �ŎU�X�q�ׂĂ�
����ŁA����51�𓋍ڂ����L43III�������삳��Ă��A���Ęb�����������B
�L115�̎d�オ�������ɁA
�{����4�A����^���Ԃ����������
>>798 ������Ȃ�
���O�������ɂ́A�u�ČR�����̕����苭�����Č������v��H
���Ⴀ��������ɂ͕ČR�����������Ă��镶����،��̈�ł������Ă�����
�t�ɂ���ȊO�̉���M�����
�l�b�g�œK���ɃO�O���Č������T�C�g�ɂ��������Ă��������ƁH�ӂ����Ă邨�O�H
���O���g�����x��������ꂽ������Ȃ��A�N�������������s���A�ǂ̕��ɏ����Ă��邩��������Ȃ��A����ȉ������Ȃ��̂����M���X�ŏo���Ƃ����q���Ȃ�
>>796 �W�^�̓n45(1650hp)or�����\�肾�����݂�������
���52(565km:7,7mm2��20mm2��)52��(540km:13mm3��20mm2��)54(�����F563km:13mm2��20mm2��)�������
���������l�����Ă����܂葝���͌����߂Ȃ��݂��������ǁc�M�����ɌR�z���オ�肻��
���ܓ�^�̔h���^�̑��x���r�Ă��Ă��d���Ȃ�
������Ȃ��ČR�@�����Đ��ŃJ�^���O�X�y�b�N�Ȃo���Ȃ����낤�E�E�E
>>802 B-29�u���A��q�̃��X�^���O�����A�R�C�c�����E�`��̉����Œu���Ă���邩���U���E���狏�Ȃ��Ȃ��ȁv
�u�I�b�X�I�b�X�O�O�v
B-29�u�v
�E�E�E
B-29�u�w�������I�Ȫ�I�I�I�v
P-51�u���������R���I������ȃo�J��Y���̖�Y�v
���u�Ȫ!�v
���d�u��������߂�v
���Ȃ����������H
>>803 ��B���ɂ�
�l����u�Ȫ!�v
���d�u��������߂�v
�o�������҂Ȃ��A�������C�R���痤�R���d�R�c
�t�B���s���ɂ�
�l���핔���u��P�̍��ԂɌP�����Ă������v
4�@vs4�@�̕ґ����P�������{
P-47�u�Ȃ�Ă������A�������W���b�v�ɒǂ���Ă�B���s�����I�v
���卬���B
�Ȃ��o�������҂Ȃ��B��㒓���ČR�l�Ƌ����Ƃ��čĉ�đ��
�y�{�M�[�A�X�J���N�A�T���^�N���[�X�z�@����ȋ���Ȃ��̂��}�ɕ��サ�ĂˁA�������X�s�[�h�Ŕ�Ԃ�
http://2chb.net/r/liveplus/1546914326/l50 >>802 �����������̔��o�J�͌�F�Ƃ��ȑO�ɋL�^���̂ɂ������ĂȂ�
�S���ϑz�Ō���Ă邾��
�����ł������蔭������������ꍆ��킪�������炢�����������a18�N�̃j���[�M�j�A�Ȃ�
>>808 �u�ČR���猩����A���̕��������I�v�͖{�����H�Ƃ����b�Ȃ̂ŁA�ČR�̕��Ȃ��ƈ�����O�ɏo�Ȃ��̂�
�ČR�̏،����ƍ��̂Ƃ���A�u�[���ƃI�X�J�[�́`�v�݂����Ɉꏏ�����ɂ���Ă�̂����o�ė��ĂȂ�
>>808 >�Ƃ������Ƃ��͂����肳���Ȃ��ƕČR�̕��]�X�ƌ����Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ�������
�����̏��������Ƃɂ��炢�ӔC���Ă�
��ł�����Ă�̂�
>>755 >�u�[���ƈ���Ď苭���v���Ă̂̓A�����J�̕]���ł�����
�������߂�ID�ԈႦ���AID:Vwyvwdgl��
>>755 �̒��̐l��
�u�i�G�@���j���Ƃ��Ȃ����A�i�G�@����j���Ƃ���Ȃ��v�Ƃ����i����j�L43�̐��\��
�܂��ł��G�퓬�@�𗎂Ƃ��Ȃ��킯�ł��Ȃ���
�ʔ����V���[���Ƃ͎v��ˁH������
>>812 ���݂��ő呬�x�ŏ�ɓ����Ă��Ȃ�����Ȃ�
�傫���Ӗ�����͔̂����@���@�@�A�����_���}���@�ł�����
�}�~��������ő�580km�̌����850km�ȏ�ۏ��邵
���Ƃ͂�͂�����͂ɏ㏸�́H�ČR�@VS�h�C�c�@����ƌ���
�ł����ĉ^�������A600km�ȏ�Ŋ��S�ɂ������o���Ă�200km�`300km�̌y���ȑ���Ɉꌂ���E�Ȃ�Ă�قǂ̉^���Ȃ��Ɠ������
���͂��G�ƌ������Ƃ�悪��ʼn������������̂���
�n�R�����Ă�������A�h�C�c�̐�Ԃ͂͂łȖ��ʂȂ̂Ƀ��V�A��Ԃ͔Z�Έ�F�Ȃ́H
��Ă̓��Ƃ��ƊC�̏オ���C����������Z���Έ�F�ł�������
���{�̃v���y���̗��^�Aclark-y���嗬���Ə������B
�v���y�������́A�v���y���ɍ̗p�����g�R�䂪�����Ȃ�A�㏸����B
clark-y
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=clarky-il 100�����C�m���Y���ŁA�g�R��114.8
�h�C�c�A�Q�b�`���Q�����^�ŁA�g�R�䍂���āA�����̃v���y�������̌��݂������̂Ƃ��āA
�Ⴆ��
GOE446 �c�g�R��148.7�����C�m���Y��100��
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=goe446-il GOE528 �c�g�R��137.7
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=goe528-il GOE501 �c�g�R��137.9
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=goe501-il NACA6412 �c�g�R��142.7
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca6412-il �ĂȊ����ŁA�h�C�c�ŕ����������|�[�g��O�O�ɒT���o���āAClark-y�������\���������^��T���Ȃ�A
�������̂��ƁA�h�C�c�̃v���y�����[�J�[�ɐv���˗����āA�����������{�i���}�n���A�Z�F�n�~���g�����j�ōs���Ƃ��B
�O����������ł����Ȃ̂����A
DB601�̐������C�Z���X���́A�v���y�����^�̃��C�Z���X�̕������{�����������肵�āi��j
�O�H��쐼�A��������̎d���Ƃ������́A���ꂱ����Z���̎d�����Ǝv�����ǂˁB
�v���y���͊����i�A�Ƃ��������Ȃ̂�����c
���쎁�����������쎁���������Œ�s�b�`�y���ɂ���
�Œ�s�b�`�Ȃ�ᑬ�d���ō\��Ȃ����낤���ljσs�b�`�͘b���ʂ���
>>821 �Ƃ��铯�l���ɁA���a19�N���b�l�@�̃y���ׂ��Z�p�҂̃m�[�g���������b���������Ȃ�
�c�}�W�Ńt�B�[�h�o�b�N�x�������ᖳ���́H
>>819 �Ȃ�قǂ�
�ēƋ@���y����(���{�@�Ɣ�r����)�A���_�[�p���[�Ȃ̂ɁA���ƍ������\�Ȃ̂̓v���y���̐��͍��̂����Ȃ̂��˂�
�L���Șb�����ǁAP-51C�AP-40E�AFw190A5�A�O����Ǝl����
�����̃��`�F���s�ǂ͐������@�̕s�O�ꂪ�����炵������A�ȒP�ɉ��P�o������
�l����A�ǂ��������@������Ȃ���v���y���͂����ƍU�߂Ă����v�������\��
�����̓��{�̃v���y��������́A
�v���y���Ŏv���o�����l�^�B
>>823 �@���ʉd���������Ă�b�ƃZ�b�g�A���Ǝ����͌��Ă邯��ǂˁB
�u�����d�v�ƃG���������̌������œK������A����̂悤�ȍ����^�����ƍ����ʉd�͗����ł���A
�Ƃ����y�䕐�v�̐v��@���A���{�ł͍L�܂�Ȃ��������Ƃ��l�b�N���낤�H
�͏�퓬�@�����łȂ��ɂ���A�ǒn�퓬�@��������I�b�P�[���낤�H
����̗��ʉd��175.���x�A���c������Ƒ卷���Ȃ��킯�ŁB
�����āA�A���_�[�p���[�i�n�͉d��3��j�͌����Ă��Ă��A
�^�����ɂ̓P�`�����ĂȂ��킯�ŁB�C�R�p�C���b�g�ɂ��D�]���������B
>>828 ���������z�Ɍ����ăP�`���邾���ʼn�����������Ȃ�����܂��
�ʓ|�Ȃ�X���J�����Q�Ă�����̂�w
>>827 1939�N10���ɃA�����J���甃����DC4E�̓t���t�F�U�[�������͂�������
����VDM�܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ�����
�����@�̓t���t�F�U�[�o���Ȃ��ƃy����]���嗃�̋��U�Œ��댯�Ȃ��ǂ�
>>830 �����d�̐v�v�z�����{�ōL�܂�Ȃ������̂�
���t���b�v�̕��������ƌ��ʂ�������������
�f�Ŗ͋[��킵�ė��ɏ��ĂȂ������t���b�v���g���Ɨ��ɏ��킯
���R�ɐ�킹�Ă����c�҂���サ�Ă����ʂ͕ς�炸
�ǂ�����u�����d�v�M�����낻�둲�Ƃł��������ȁH
���d�Ɍ�����AJ�T���F�[�W�̃G���W���J�E��
1:15����
�_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �J�t�X��t����͓̂��{�ł͂Ȃ������́H
�����ČR�ɂ́u�O����͓��{�@�ɂ��Ă͑����������Ǐ㏸���x��������퓬���ʂɕ|���Ȃ��v�ƕ]����Ă錏
J2M1�̎嗃�����������@�e��4���ڂ������ƂȂ��
>>834 ���{�@�̓v���y���X�s�i�[��t���鎖�ɂ���č����̃v���y���f��(���x��ۂɋ߂������f��)
���B���Ă�����J�t�X�Œf�ʌ`�����P���悤�Ƃ������z�Ɏ���Ȃ�����
�X�s�i�[�����������ċ@�Ȃ�ł͂̔��z�Ȃ̂��Ǝv��
�`��G���W����p�Ɏu�������J�t�X������
�A�X�y�N�g��̍��������U����R�����Ȃ��L���͗����ł��邯�ǁA�����d���čl�����̓s���Ɨ��Ȃ�
>>832 �@�S���Չ��ǂ�����i�j
�������d���������i�܂藃�̕����傫���j�q��@�́A�d�S���痣�ꂽ�ʒu�ɃG��������z���鎖���ł��邽�߁A
���G�������̌������悭�Ȃ艡�]���\�����シ��Ƃ������_������B
������E���̃h�C�c�̃t�H�b�P�E���t Fw190��Ta-152�͉��]���\���d�����A
�������d��Ⴍ����i�嗃�̑�A�X�y�N�g���V�I���j�v�ɓw�߂Ă���B
��
���܂��G�������̌������悢���́A �G�����������ʐω��Ȃ������p�x�ɂ��Ă��悢���߁A
�����̋�C��R�����������A�������߂���ʂ����邽�߁A
�����{���R�̎O���퓬�@�́A�����������ϓ_���痃���d������������v�ɓw�߂Ă���B
�X���Ⴂ�ŋ��k�����A���킪������⎾�����ƈقȂ�_�́A
�J�E���̐v�ŒP�Ƀj���L�j���L�r�C�ǐ��₵�Ă�̂̓u�T�C�N�����
>>835 �O���͋@�̐v�]�X����ȑO�ɃG���W�����v���I�ɃA���_�[�p���[
1300�n�͈ȏ�A�܂��^���{���̐��Y�^���Ď��_�Łc
�t�Ɍ������������s�����ׂ͍̂������ƈȑO�ɂ܂��p���[�A�b�v���肫���낤
���a15�N�i�K�́A���d�v���d�l�B
�v���̒i�K��DB�ȊO�����ɂ��Ă��
���m�Ɍ����ΈႤ��
>>821 �킪���q��̋O�Ռ��O�ł�NACA�n��Ƃ��������Ă����
���a16�N�ɁA�u���̋Z�t�v���q��@�v���y���̍u�����A���D����ōs�����������A
�l�b�g�Ō��J����Ă���B
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjasnaoe1903/1941/68/1941_68_295/_pdf/-char/ja �v���y���͍\������Țd�ŁA���C����K�X�̑��x�Ői�ނ��̂Ɏӂ��Ă͍K�^�ɂ����ɗ��z�I�Ȑ��i�@�\�ł��邽�߂ɁA
�����̍q���Z�p�҂̌������Ƃ́A�ʓI�ɂ����I�ɂ���荢��ȋ@铋y��ᢓ��@��ᢒB�̕��Ɍ������A
�ߋ�40�N�Ԃ�ᢒB�̌o�߂����Ă��A�v���y�������������ɕ��Ղȓ�������Ę҂��l�Ɋ�������B
�����v���y���͍ŏ�����e�Ղ�70%�̝�����ᢊ����ċ���A
�����v���y�����o�����Ă����80%�̝������펯�ƂȂċ���B�������̏��ǂ�Ȕ�s�@��v���悤�Ƃ��A
�v���y���������I�ɑI�������ւ���A�����Ƃ����x���\�ɉy���Ă̓v���y�����g�̐v�ɂ�ďd��ȉe�����o�ւ�l�Ȏ��͂Ȃ��A
�n�Č�X�̓v���y ����1�̑����i�̔@���l�ցA�ɒ[�Ɍ��ւΗ�ւ�
�ԗւ�I�ԗl�Ɉꗗ�\�̒�����D���Ȃ��̂�I�肵�Ă��哕�[���ł����Ɖ]�ւ�B
��ԏd�v�ȃ|�C���g�́A�u��18�}�ANACA5868-7 Clark-Y�v�ƋL�ڂ�������B
���̏��a16�N�����A���Ɏx�����ꂽ�����i�v���y���́AClark-Y�ł���炵���L�͂Ȏ����ł���B
���̎��_�ł͊ԈႢ�ɋC�Â��Ă����̂��������
����Fw190�̃����N�@�\����
>>839 ���]���\�̓G���������t���Ă��镔���̗��ʐςɈˑ�����
�d�S����̉��߂͊W�Ȃ�
���A�S�����傫���قlj��]���\�͈�������
���]�Ƃ͉��ɓ]�Ԏ��ł��藃���̑召�����ډe������
�d�S���牓���G���������ʐς����炵����NJp�����������Ă�
���]���\���ێ��ł���Ƃ����̂͊��S�ɊԈႢ
�G�������͐���ɕK�v�ȃo���N�p���Ƃ邽�߂̕���
�u���v�Ƃ͒��ڊW�Ȃ�
�u�����d�v�I�ɔƎ��Ă���̂�P38
�J�퓖�����̋@�̃p�C���b�g�͒ᑬ�ł̐��\�ɂ��Ȃ�̎��M�������Ă���
���Ɋi�����Ńy���n�`�Ƃ��������ꂽ
���A�X�y�N�g��̎嗃�͍����x�̋@���ō��x�̉��������Ȃ��Ƃ�
�������A�q�������ʂƂ��̗��_�͂��邯��
�d�ʑ����͔������Ȃ�
������
>>836 �̎w�E����ʂ�y�����O�̕��������e����X�y�[�X�ɖR����
>>850 ����Ȃ�ŁA���ꂾ�����ʉd�������āA��ʓI�ɂ͉^�����������n�Y�̌��킪�A
��@�Ŏ����O�@�������l������A�݂����ɐ�^�����^������L���Ă���̂��A
�L�`���Ɖ�����悤���i�j
�����d�E�G�������������ȊO�łˁA���R�����ǁB
����F�@��s��P�P�P�����Q������F���R�����@�w�^��
>>851 �y���n�`�Ɏ��Đ��\�͂���
������832�ɏ������ʂ���t���b�v�ɂ͗��
�����Q��
1939�N�ɏ���s��FW190�́u�����ʎY�^�vA-1�ƁA����x�ڍׂɔ�r���Ă݂悤�B
>>851 �₠���͂悤
�N�ɂ͐l���킹��˔\��������Ă����
�����d�E�G�������������������o���Ă����̂�
>>839 �܂�N���g�Ȃ��H
�u����������́A�悭�͂����イ�ł��ゲ���I�I�I�v�������o���Ȃ�
>>856 ���t��ς���v���y���������͌��ǁA�v���y���e���f�̗��^���ɋA������Ƃ�����{�F���ł��B
�c�u���[�h�e���f�̗g�R�䂪�A������A30�C20�C10�C5�ƂT�ʂ�ɕω������ꍇ�ɑΉ����闃�p�Ɨ��f�����̊W�������܂��B
����͎R�����v�E���������́u��s�@�v�_�v��184�y�[�W�̃O���t����̂�܂����B
�c��������w�тƂ�鋳�P�͂����ЂƂA��͕����̃u���[�h�f�ʂɂ͍��g�R�䗃�^��^���邱�ƁA����ɐs���܂��B
http://www.yp1.yippee.ne.jp/launchers/dr-isii/p-and-r_3.html �g�R��20�̗��^�v���y���ł���A�ǂ�ȑ��x�ł���A�L���v���y���ʐϕ����̃u���[�h�p30�`45��ۂ悤�ɁA
�s�b�`�p�ςł���悤�ɂȂ�A�v���y������90���͊��҂ł���B
�g�R��30�����闃�^�̃v���y���ł���A�u���[�h�p20�ォ��v���y������90������B
�����̓��{�̂悤�ɁA�s�b�`�p�ϔ͈͂�20�`30�x�ŃA�b�v�A�b�v���Ă�Ȃ�A
�܂��܂��v���y�����^�̗g�R����P���A�A�����J�ȏ�ɋ��߂���B
>>858 ���u��������L����O����������₷��������\�͂Ȃ�ł����ˁH�v
���ʉd���قȂ�A�O����i����II�^�j�ƌ���ꎋ����i�j
���̔h���^�����āA���ʉd���������邽�тɁA�^�����̒ቺ������p�C���b�g���烄�����ƌ����Ă�̂ɁB
�O����̐��a�͗��ʐςŏ���FM-2�Ɠ����Ȃ͕̂ČR�̃e�X�g�ŏo�Ă��
>>858 �O����͊�{�A�悭���퓬�@����
��ŏ����Ă�l����悤�ɃA���_�[�p���[���S�Ă�䖳���ɂ��Ă邾����
���Ɠ��{�@���i����ɋ����̂́A���m�ɂ͏�����������Ƃ������
�n�͂̊��Ɍy������Ȃ�ŁA�d���Ƃ���Ȃ��̂Ȃ̂�
�O�����f�r���[����43�N�āA�C�^���A�ł�DB601��MC.202���������āA
2G�̐���ł͗U����R��4�{�A4G�̐���ł�16�{�ɂȂ�A����ł͗U����R���x�z�I�ȃp�����[�^�ƂȂ�B
�ێ����Ƃ�͂萄�i�͂��傫�������L������
>>863 �܂���DB605����Bf109�̉ғ����Ⴗ���邵
���ł�P-47D�ɑR�ł��Ȃ��ጋ�ʂȂ�Č����Ă���
>>864 ����͂R���^�T������f�B�X���Ă�́H
�u�R�^�T����͓G�@�ł͂Ȃ��U����R�Ɛ키�퓬�@�ł���܂��v
�ƌ��������́H
��s�@�̓o�����X�̎Y���Ȃ�
�܂�15G�����̐���ł̗U����R�͒u���Ƃ��Ƃ���
G�X�[�c�����̐l�Ԃ��ς�����̂͂S����TG�Ƃ�������
15G�����ɑς���嗃�Ȃ�Ė��ʂɏd������
�u�@�̏d�ʂ�����v���ĂȂ���
�d�S�ړ��ɑΉ����邽�ߎ包�Ƙ]�ނ����ꂽ��Ԃ�
������g�t���Ė��Ȃ��Ƃ����̂����ʂȏd��
�y�各�͂̔����@�𓋍ځz�̓��V�v���炵���Ȃ�������������
3�^5����͂ł��Ă�́H
�ł��ĂȂ���ȁH�f�B�X��߂�����w
>>862 �ł̓A���_�[�p���[�Ə����Ă邯��
�ŏ��ɃG���W�������߂Đv�ɓ���킯������
�A���_�[�p���[����Ȃ���Too Heavy�[�d�ʉߑ��̈��ɐs����
�A�X�y�N�g���傫�����鎖���U����R�̒ጸ��
�L���ł��鎖��ے肵������͈�x���Ȃ�
�������퓬�@�̓A�X�y�N�g�䂾���Ő키�킯�ɂ����͂�������킯�Ȃ������
�R�^�T�����ٌ삷�����Ȃ낤��
�����̉�������ɖ����ɂȂ��ċC��������f�B�X���Ă�Ƃ�
�ǂ��ʔ�����w
����R�^�T����֘A�͂T����X���ɏ����ׂ�
���傭���傭���ɂ������ɂ���
>>858 =
>>867 ����ȁH
�ʂɃA���_�[�p���[�ł��鎖�͔F�߂���ŁA���\�ƍ����ʉd�𗼗������̃A�v���[�`�̕��@�Ƃ���Ă��邾�����N�ɂȂ��Ĕے肷�闝�R���������
�O��/���Ƃ����ʂ̋@�̂��̂��̂ւ̔ᔻ�Ɨ������L���鎖�ւ̔ᔻ����������Ă���
>>868 �l�Ⴂ��
����850�A853�A855
����������839���]��ɂ��f�^�������������炻��𐳂�������
�O����15g�Ƃ����͎̂���i�K�ł̑z��S���d2950kg�ɑΉ��������̂ł���A�S���d��3.5�g���߂��ɂȂ��������O�����^���Ō�����12.6g�ɑ�������d
>>868 851�ł�852�ł�5����Ō���Ă�
864�Ƃ͕ʐl�Ȃ̂��H
���̊ԂɌŗL�@�̘b�����炷��ւ�����H
>>870 15G�����ĉ�ꂸ���������߂�����v�Z�o���Ȃ�
��������X���ł��ׂ�
>>871 ���≴��864�Ƃ͕ʐl����
�u�����d���_�v�Ɋւ���c�_���Ǝv������A�r��������������ɏo���������̎O��/����{�̘_�c�ɂ���ւ�����l�Ɍ����������ɂ�
���Ƃ��Ɓu�悭�͂����イ�I�v����������������
>>830 �̏������݂��A�����܂Ŗ{�|�͌��킻�̂��̂���Ȃ��ė����d���_�̑Ó����ɂ��Ă��ۂ���
�r���������/�O����̑�d�ʂɂ����\�����Ƃ����A�����d���_�ɂ��Ȃ����ł̔ᔻ�ɔ�ĂȂ����H
�{�|�͌ʂ̋@�̂���Ȃ��Đv�v�z�̘b�������̂ł́H
�v�~�X���Ƃ͕ʂ̘b���Ǝv������
�����d�_�c�͂ǂ̓��{�R���@�X���ł��l�@�Ƃ��Ă��蓾�邯�ǖ{�|������̏d�ʔᔻ�ɒB������A���ꂱ���X���`�����
�����܂ŗ�Ƃ��ďo���Ɏ~�߂�ׂ��ŁA�����b��ɏオ���������̌���̔ᔻ�ɓO������������������������̂ł�
>>867 >�ŏ��ɃG���W�������߂Đv�ɓ���킯������
>�A���_�[�p���[����Ȃ���Too Heavy�[�d�ʉߑ��̈��ɐs����
��肾���Đv�i�K�ł��ꂭ�炢�͗������Ă�
�܂������Y�J�n���N�߂��Ă��A�b�v�f�[�g����ł��Ȃ��Ƃ� orz ��ԂȂ��
���Ȃ݂ɃA�c�^�̕��͈��k��Ɖ�]���グ��DB601N�����̏o�͌���ɐ������Ă�
�܂���Ƃ��Ƃ͌ŗL�@�̘b��ł͂Ȃ��A�ŗL�@�͗�Ƃ��ďo���ꂽ�����Őv�v�z�̘b���{�|���������̂��A
�v���v�揑�̓��e���炵��
�n�܂��
>>830 ����
��̓I�ɌŗL�@�̘b�Ƃ��Č���Ă�
�Ƃ������ɂ͓ǂ߂Ȃ�
�ǂ������邩�͕ʂɍD���ɂ��Ă���
���������B���͐v��@�̘b���{���Ɍ����邪�ȁB��/�O���͗�ɏo��������
>850�܂ł͈�ʘ_���ۂ���������
�����͔ᔻ���Ă�����A�u�́H�����d���_�Ƃ��o�L�ڂ�����v�݂����Ȕ������Ă���
�ނ͂����Ɩ{�𗝉��ł��Ă���
�r������b�̗���̖{�|�𗝉������A�ڂɕt�����匙���ȋ֎~���[�h�ɔ��˓I�ɃR�����g���q�ׂ�l�������Ă���
�Ƃ����
>>858 �Ƃ͕ʐl�Ȃ킯��
>>875 14���ɋ���60�͂ˁ[��
14�����̂܂܂��Ɛ��\�����������ɂȂ���Ŕ����@���nj^�ɂ��Ă��������A�������ǂ�������v�������グ�ȁA���[���ĂȂƂ�����
F8F�̓A�X�y�N�g��5.16�ŗ��ʉߏd200�O��
>>859 ������C�R��Z���ł͂��̃v���y���̎��ɋC�t���Ă����̂ł́c�H
�Ƃ���Ɯa���̍������\�����_���s��
�R�����͊C�R�̋Z�p�m�o�g����
�a���������炩�ɓ��{�͂��납�����̐��E�������璴�z���Ă���
���d�̃v���y������������������ቺ�A����̕��L�v���y����������������A�Ƃ����b�A
�O����̓A���_�[�p���[��������Ȃ����y���̗L���ʐς��L�����琄�i�����͓����n�͂̋��G���W���@��肢�����Ȃ��ǂȂ�
>>883 �v���y�����^�͔������̂��D�܂�Ă��邻����
���ƁA�v���y�����a�݂����ɁA�����ł͐��i�����ǂ��Ă��ᑬ�ł͑S�R�����Ȃ��A�݂����ȁA�����d�����ō����x�d�����݂����ȃg���[�h�_����Ȃ��ė��^�͂����ƍL�����x��Ō����Ă���Ǝv������㏸�͂����ɗ��܂炸�ő呬�x��}�~���܂ł悭�Ȃ�ꍇ������Ǝv������
P-47��F4U�Ƃ��͗L���Șb����
�L61�̃n40�̓L78��DB601�ł�����悤�ȃt���J���O���ă`���[�����ė����㏸1500�n�͂ň�������Ηǂ�������
>>880 ���₢��A���a18�N10���̌����ŁA���d340�m�b�g�̔�Z�p�����̊��ɋy��ł��i�v�������グ����3�N�o���Ď��@�����ł��j�����Ă��̂��Ȃ�
���ꂭ�炢�o�Ȃ��Ɨ��Ƃ̍��ʉ��̕K�v���Ȃ��悤�ȋC�͂���Ȃ�
�ꍏ������340�߂̗��d���A�Ƃ̏ł肪�A
��p�t�@������������ċ@��̊J�����������L���邾����
�ǂ������[�ƃy���̐��͑����Ƌz�C�o�H�ɂ͂�C�Â�
�������d�̗��ʐς͌��点�Ă�18�u���炢�܂ł��낤��
�������t�@���́AFW190A�Ƃ��V�[�t���[���[��
���d�Ƀn�S�R(2200�n��)�ς�A�ǂ��������Ȃ��H
FW190A�͑咼�a�G���W���̂��߂悯���ȓˏo�������ׂ�
>>894 �V�[�t���[���[�͋������t�@���Ȃ��̂ł�
�G���W���쓮�̃I�C���|���v�ŗ����̑�^�I�C���N�[���[��
�V�����_���̃q�[�g�V���N�̊Ԃ��z�����Ă锼���₾�����͂�
���d�̂������㏸�͂��l����Ɩa���^���̂��ɂ��������
�P�r�C�ǂ̃K�X���̃x���`�����[���ʂŋ��C�����z���r�C�ŗ����̂����
���͗��̔����@�M���M����菭���i��߂ׂ̍��u���a���`�v���̂������������Ƃ����͔̂���Ȃ��̂�
>>899 ���ہA�x�z�t�@�C�^�[������ɐ�����������@��
�鍑�ɗʎY�\�ȋZ�p�͒P�r�C�ǂɂ�鐮���Ƌz���o�����ʂ̊��p���炢����
�t�ɂ����Ɨ������d�����Ȃ�s�H�ȏ��������Ă�
�����Ɏ���Ȃ����������ŗ��̉��ǂ����d�i�ʎY�^�̐v�ł͂����Ƃ��Ă��݂��������ǁj���܂Â����悤�Ȃ��̂�
http://www.warbirds.jp/sudo/a7m.html ���̃T�C�g������Ɩx�z�t�@�C�^�[�̗��킳��
���̒��ł����d���u���̓��{�@��Fw190��F-6F���݁v�̐����x�ł��邱�Ƃ��킩��
Fw190���̔r�C�ǂ̏�����������Ă�����ł��i���x�́j�������ƂɂȂ��Ă�
�����^�̓��̂̓^���N���m��Fw190�̓��̂����ɂ������낤����
���{�̏ꍇ����ł���Ȃ��@������ł��̂�
���x�b�g�ł��̎�ԉ]�X�͗ʎY���ƊW�Ȃ�
�ǂ�Ȃɓ��̂�嗃�̗ʎY�������Ă������@�Ō��肳��邩���
>>904 ��������
��p�t�B���̃s�b�`�ׂ����Ƃ͂����A�悭�₦��Ȃ��Ă��炢�^�C�g�ȃJ�E�����O
������130mm�~150mm�~18�C���̃n51�B
>>905 �₦�Ȃ���ŃI�C���N�[������剻���Ĕ����≻�c�c�݂����Șb���ǂ����̃X���Ō���
>>906 �h�n�̕���22�C���̉\���͖ʔ����������A�������v���Ⴀ��
�O�Ԃ���̒����ɂ��������Ǝv����
�y���q�@�P�Q�R�փ��b�N�I�������z�@���]���u�^���͕��܂Ŏ����Ă����i�������͈��͊u�ǂł͂Ȃ��j�v
http://2chb.net/r/liveplus/1546740721/l50 >>907 �@�_2x�ւ̐��\�������ؒ��߂āA�����ɁA�h22�C����2200ps�ڕW�ŊJ�������Ă���A�ǂ����������ˁH
����Ȃ���A8000m�ŗ����n�͂�8�|����B������炵���A�n50�̗D�G�ȁi�O�H���j�ߋ��@���A���G���W���ɉ��p����Ƃ��H
>>910 ��قǂ̑厸�s�ł��Ȃ����肻�̃��[�g�͖������낤��
���̕ČR�����ɂ��n51�̉ߋ���͎O�H����2���炵��
����2500�n�́A����2400�n��/2000m�A1970�n��/8000m
�u���̂ق����悭�₦���v�Ƃ������̂������ŁA�����̊�b�Z�p�������Ƃ��Ă���ʔ������������A�̃��x��
�h��1150�n�͂��̂܂�܂̃u�[�X�g�ŁA�����Ȃ�18�C���ŗ_�̕����ʔ���������
>>911 �����́u���s�G���W���v����̗]�͂��A�h22�C���ɔ�₵�Ă�����ˁB
�Ⴆ�A14/18�C���i�n46�j�̌�n�Ƃ��A
18�C���i�n44�j�̎��n�Ƃ��B
�����́A�x�Ԍv��̂Ƃ��ł���A��18�C�����h��36�C���̃n54�Ƃ����o�P���m��҂ݏo�����Ƃ��邮�炢�A
�t�ɎO�H�̋Z�p�������ċ~�ς��ꂽ�̂��h�n�ł͂Ȃ�
�C�R�A�����a�̔����@�ɂ�������Ĕ��W���ɖR�����h�Ɍ����ꂷ�����
>>912 �@�h21��18�C����������A740kg�����ʼnΐ�1x�Ƒ哯���ق̏d�ʁB
�o�͂�������������ŁA����1180mm�ƌ��I�ɏ������Ȃ�A�܂��C��R���������Ȃ�B
�y���d�z�̍������i���̐v�̕ύX�j�Ɋ�^�������� IF ���ˁB
�ܘ_�A�ΐ���ςꎮ���U�Ƃ��A�l���ς���̍X�Ȃ鍂�������e�Ղ��B
�ΐ��ȉ��̔R��ɂȂ�Ȃ�A�q���������ɂ���^�����������B
�_�͒�u�[�X�g�ł����N�����Ă邩��]�݂͔����Ǝv��
�����͏��{�A130mm�̉h�E�_�i11�̉^�]�����Łj�́A14-18�C������肭������Ǝv�����A
�_�̍��{�I�Ȗ���AMC���K�v�Ȃ̂Ɏ��p������ĂȂ�����
�Ԃ����Ⴏ���b�A1500�n�͂ɐ��������_���
��̕s���Ƃ����̂����܂��̓I�ɕ������Ă��Ȃ���
�U����̏Ⴊ�����A�\�肵�Ă����o�͂��o���Ȃ������Ƃ���Ă��邪
>>913-914 ����Č��Ȃ��Ǝ��s���킩���Ƃ͂���14�C���ł��܂������ĂȂ����n5��18�C�������镪�̃��\�[�X���ق��Ɏg������Ȃ����Ƃ����̂͂܂��킩���
�ł��n50�����O�H�̎��Ă���Ȃ��ė��R�̔����ŁA�O�H���������h���̃n108���Ƃ�A19������Ă��킯��
���R������ȃQ�e��蕡��22�C���̂ق��������Ǝv�����炿����ƍ���Ă݂Ă���łł����̂��n50����A21
�c�c���[�n44�ƃn46���ׂ�������22�C���h��ꂻ���ȋC�����Ă������ւ�
��͂��܂ł����Ă��N�\�G���W������������A�V�R�͉ΐ�2x���ڂɐ�ւ��킯�ŁB
�C�����a150�~���ȏ�ُ͈�R�ĂŎg�����ɂȂ�Ȃ�����
��A�\�O�����U�ł̓_���_������������
150mm�ȏ�̃{�A�̃G���W���ŁA
>>927 �@�ΐ�2X�͐U����肪����ɂ���A������܂Ƃ��E���p������A�Ɣ��肳��Ă�킯�����ˁB
�܂�A��̃N�\�x�����͉ΐ�2X�ȏ�A�ƊC�R�����F�����悤�Ȃ��́B
��̃X�y�b�N�ׂĂ���A�ǂ��������n�͂�1870�n��/2600rpm/+400mmHg�炵��
���퓖���̃G���W���ł́A15kg/cm^2�A15m/s�A15cm��3��15����̌��E�_�ł��i���ۂɂ�16�O��܂łȂ狖�e�͈͂Ƃ͂����܂����j
>>931 ����
�~ ����6x���݂�15kg/cm^2
�� ����6x���݂�16kg/cm^2
>>930 ���̓��ڂ��K�v�Ȃ����g�[�^���ł͌y���킯��
�C�R�Ɍ�Ɖΐ��̔�r���������������Ȃ�Ă�����ˁH
>>931 ���₾����A����ł��h��18�C�������_�O�Ȃ킯
AMC�ǂ�����́H�Ƃ����b
�L�����ψ��͉]�X�ȑO�ɉh��Z�^�ł���肪�������Ă鎖���ɂ���
����Ȃ܂ܗ_���J�����Ă鎞�_�Ŏ��s�͖���Ă�
>>933 �ق�ƂɂȂ��̂��Ȃ�
+400mmHg���u�[�X�g�����Đ����^�����ł����Ɖ��Ǝv���Ȃ�����
�����܂ň������Đ����^�����̔����@���ɂȂ���
>>936 �ł��Ȃ���Ȃ��c�c
�V�R���^�ɂ��[�R�ɂ����^���N�͂Ȃ�
�_�ȏ�́u�厸�s��E�_�O�v�ȑ��݂���i�j
>>937 �ق�����ُ�U�����ăf�g�l�[�V�����N�����Ă���˂��̂��ċC�����Ă���
����͍��I�N�^���R���^���N�ƒ�I�N�^���R���^���N���ڂ��ĂĎg�������Ă�����
���Ⴀ�A�V�R11�ɐ����^�^���N������A�Ƃ�������������A��~�͔�������낤�ȁc https://forum.valka.cz/topic/view/1295 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ohgai/3853/jnrs/jnrsC233a.htm ��Ɖΐ���Z�^�̐U���A�u�[�X�g�������萅���˂���ƋN�������ُ����낤
�ł��_���͂ˁA�͂��Ă����A�C�R�ɂƂ��Č�͂���ς�v��Ȃ��q����
>>941 ���₢��V�R���^�̔R�����ڗʂ�1625ℓ�i�@�����ځj
�����������d�����^���200kg�d������
���Ȃ��U���߉d�ł��̕������^�̂Ȃ�ɂȂ������A����ች���Ƃ����b��
>>943 �����
�Ⴆ�Η��U�ł͐����˂���ƐU������������̂�
���������ɗ]�T������ꍇ������g��Ȃ������������
>>944 ����
���^�̔R�����ڗʂ͋@��1615���b�g��
�ŁA������90���b�g��
���̃T�C�g�̃^���N�e�ʂɊւ��鏔���͈��^�̂��̂�
�����ł킩����
���[�т����肵��w
���x�s���ŋC���T��̕s���n�ڕ⋭�̃��b�c�P�ŕЕt�����̂�
��́A400mm�u�[�X�g�̐v���v���I�������낤�ȁB
���Ȃ݂ɁA�����^�Ȃ��G���W���̑��̗�������čs����
�����ƎO�H�ł��ꂼ�ꔭ���@���Y������U��K�v������
>>949 �������܂��A���ԂƂ��ēV�R���^�͐����˂Ȃ��ŗ����̓e�X�g���N���A����
����ɂ���������Ă邵�A���ꂪ�ΐ���Z�^�̎��p���ɒǂ����ꂽ�̂́i�������U�����Îāj
��ɋ@�̂̋�̖͂��ł���
�\�l���ǐ�̔����@�̌��Ƃ��Ă͉h�n��18�C���̔����@����قnj����I�Ƃ�������
�����^�Ȃ��ŁA95�I�N�^���̃K�\���������āA400mm�u�[�X�g�A���Ă̂��u���I�̋ɂ݁v������i��j
�����Ƃ��āA��͉ΐ�20�^�ɒǂ�����郌�x���ŊJ���x�����ĒQ�肵�Ďg���Ă�������@�̂��ڂ��������Ă��܂����킯����
>>943 ���̃G���W�����v��Ȃ��Ƃ�������Ȃ璆���ɎO�H�̃G���W�������C�Z���X���Y������悗
>>955 �R�ɂƂ��Ă���ʼn��̖�肪�H
�@���Ɋ���70���b�g���A�R��1540���b�g���A��85���b�g���͓V�R���^�̏����ł�����
>>956 �R�Ƃ��Ă͓����̔����@����킵���Ȃ��͔�������
�_�Ɋւ��Ă��n43����������A�����ɓK����@�̂��犷���ē�{���Ăɂ�����肾������
�ΐ��ƕ��ԕʂȔ����@���K�v
amc�ăG�A�~�N�`���[�R���g���[���̎��H
>>959 �R��
�h�Ɨ_�͍����C�̋��e�͈͂������̂Œ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂���
�唼�̓�����͎蓮�őΉ�������Ȃ��̂�AMC���������Ƃ������������ُN����
�����R�����ˑ��u��AMC���������Ă�Η_��������ΐ����݂ɂ͂������Ǝv��
�����^�Ȃ���400mm�u�[�X�g���ł���A�ƐM�����ނ��̃��e���V�[���āA���Ȃ̂��낤�ˁi��j
>>961 ����A�������͎��s���Ă邶���
>>961 �����ɂ͐����˂Ȃ��Őv�^�p����Ă邵�A����ȉߋ����o�ĂȂ��˂����Ƃ�������
�����z�ʊ��ꂵ�Ă�ɂ���V�R�̑��x�������ΐ���܌^�Ɠ����̐��\������
�u�d���v�ƌ����邯�ǁi�j�g�[�^���ł��Ȃ��߉d�ʂł�葽���̔R���𓋍ڂ��A��蒷���s�����a�������Ă���
�\�l���ǐ�̔����@�Ƃ��ĉΐ��̑R�n�Ƃ��Č�������Ȃ�
�ǂ�ȂɎj����莞�����J�グ�悤�Ƃ��Ă��ł��Ȃ��Ɍ��܂��Ă�h��18�C���łł͂Ȃ�
�j����肳��Ɋ��������𑁂߂�ꂤ���A�m�j�V���낤��i�h�n�̑���Ƀv�b�V�������ꍇ�j
B7A2�Ő��͔r�C�ǂɂȂ��Ă邩���
�����Ǝ��p�I�ȁAJ2M1�̐��\������w�E���Ă����B
�ΐ����������ɂ�92�I�N�^�����Ď���
�C�R�́A�����E�ΐ����������C�ɓ����Ă邱�Ƃ͊ԈႢ���Ȃ��B
���������A�n42�͔R�����˓����O�̉ΐ�1x�^���x�[�X�ŁA����̓n42�����P���Ă���l��
�p�l�s�A�Z�C�o�[�̓��b�^�[�n�͂��ˏo���č������X���[�u�o���u���D��Ă��̂��H
�ΐ���Z�^�ɔR�����ˑ��u�����ĔR���̃O���[�h���グ���
���������ΐ�20�^�ŔR�����ˑ��u�Ȃ̂͐퓬�@�p��23�^��26�^�A���Ƒ�^�@�����ŏI��25�^�����Ȃ���
BUN�Z���Z�̃c�C�b�^�[���B
�����o�͂̕��σs�X�g���X�s�[�h�Ō����A
4�T�C�N���G���W���ň�ʓI�ȃL�m�R�ق������|�y�b�g�o���u��������
��Ɖΐ��̓X�g���[�N170mm�͓���B
�n5�n�̕s���͂ނ��됮��������i47����ł͓�P����n45�̎l����ɂȂ��Ċy�������A�Ɓj�Ȃ��Ƃɂ��
�n45�̏ꍇ�A1����9�C���ɑ��鍬���C�̔z�����Ƃ���
����Ō�͌�����ŋꗶ���������P�̖��A��e�ʂ̋C���Ƀ`�������W���Ă���
>>979 �@��̎���ɂ́A����95�^����92�w�肪�����āy���̎S��z������A100+�̃I�N�^�������K�v�������Ɨ\�z�����B
>>980 ��ɂ���_�ɂ���ΐ��ɂ���A�w�肳��Ă�92��91�{��or92�{���ł̓J�^���O�ʂ�̗����^�]�͖�������������
���͉^�]����������Γ������A�ǂ̒��x�̐����ōςނ������Ȃ킯��
�J�^���O�ʂ�̍����ɂǂ�ȔR�����K�v���ǂ����ł�����
�����ݎg���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂�
���ۂ͔w�ɕ��͕ς����Ȃ�����
������������z�ʊ��ꂵ�ĂĂ��A�����^�]���̐U���⍕���������Ă�����ɓ���������
���̂ЂƂ���ł���A���ۗ_�̎��p���i�o�������Ƃɂ���Ă����j�܂ł̌q���ł͕K�v�Ǝv���Đ��Y����Ă�
�ΐ���Z�^�̎��p���܂ł̌q���A�܂��͗_�܂ł̌q��
�����d���������Ăđ�ʐ��Y���ꂽ��L65�Ƃ��ė��d�����R�ł��g��ꂽ�ꍇ�A�_�����d�̃G���W���̌��ɂȂ�Ǝv��
�ΐ���Z�^�Ƃ̍��ʉ��ł͑S�J���x�͏グ�������ǂˁi���������J�����\�[�X��_�ɂƂ��Ă����j
>>981 ����
���d�̎��v�Ǝ�������ł͌�����ɂȂ��Ƃ������Ƃ�
�쎩�̏�߂��Ⴍ���Ꮽ�Ȃ��āA�U���������Ċ����������炢�����킩��Ȃ�����ǂ�
���������
���d�̏ꍇ�A�U����Ƀv���y����ς����W��
���R���K�R���͂Ƃ������A�����s�ǂ����z���āy�����M�����E�]�������������z�A
>>985 �@����̓A���^�̉��l���_�i�j
>>987 ���₢��A��͎��ې[�R�ł��V�R�ł��J�^���O�ʂ�̉ߋ����Ɏ��炸�^�]�������Ă��
�V�R���^�̗��͂�ő呬�x�̎���������Ŏ��{����Ă�
���̏�ł̐���
���������A��~�[�̖������Ă̂́A
�G���W���ڂ����}���������ς����邩����łɕ����Ă݂�������
>>989 ���₾���������ƌ�Ɖh�ł͖��̎�ނ�g�ݍ��킹���Ⴄ��w
�Ȃ�ł��s�X�g���X�s�[�h��ߋ����ɒP�������邩�炻��ȉ��߂ɂȂ�
������ł�
�܂�1��9�C���ւ̕��z������Ƃ�����肪����
�����87�I�N�^���̔R���ł͑�e�ʂ̋C���ł̔R�Đ���̖�肪����
����Ȃ��1��7�C���A14�C���ɂ��Ă݂Ă�
�h�̏ꍇ�͋C�����������Ēᐫ�\�̔R���ł��悭�����������C�̋��e�͈͂������Ƃ����̂�����
��͍��i�ʂ̔R����O��ɂ��������ǂ̓J�^���O�ʂ�̉^�]�����ł͏Ă��t���ƐU���������Ďg�����A�^�]�������K�v
�_�͋C�������������ǁA�h�n���L�̖��������p���A1��9�C���ł̔z����肪����
���o�͂�_�����̂̕s���ȊO��
�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������킯�ň�Ԃ̖�莙�i�n5�n���́��Ȃ̂œ�P�������Ă������ł̕]���͈����Ȃ��j
�_�͉^�]������������������˂���
>>990 �����E��Z�����A�����������s�Ɛ������J��Ԃ��ďn���̃m�E�n�E�āA
�����s�ǂ����X�ɒׂ��Ă����A�ƍl����A�ǂ��Ȃ낤�ˁH
�h�_���s�X�g���X�s�[�h15m/s�i�����̓��{�̌��E�l�j�ŁA�M����������v�m�E�n�E�ƁA
���ϗL������15�`16�i�����̓��{�̌��E�l�j�ŁA�M����������v�m�E�n�E�A
�u�o������ɂ��āv���߂āA�_2000ps�͐�������킯�����B
�Е������Ȃ�A�_1x 1800ps�����낤����ǁB
>>991 �@������95�I�N�^���ő厸�s���J��Ԃ���̗i��ɁA�S���Ȃ��ĂȂ��[�i���j
�����̓��{����A95�I�N�^���ȏ�̔R���ʎY�͕s�\������A
��͕s�v�̒����A�Ǝ咣����Ȃ�A�����ł��邯�ǂȁB
��~�[�́A����95�I�N�^���̑O��ŁA
>>994 �ߋ����ƃs�X�g���X�s�[�h�ƗL�����ψ��͂ʼn��I�ɘ_���鍪�����Ӗ��s���Ȃ�
����ɓ��{�̑�o�͂̔����@�͂ǂ���s���ɔY�܂���A�z�ʊ����^�]�������|�����Ă�̂�
�J�^���O��̐������E���Ă����Ӗ�
400mmHg�ʼn^�]�ł��Ȃ�����ǂ��A�Ƃ��ł͂Ȃ��i�����Ăǂ��܂ŗ��Ƃ������͒m��ǁA�^�]�������Ă��̂͊m���Ȃ���j
��������\�Ȕ����@�Ŏ��p��ǂ̒��x�̃p�t�H�[�}���X���o��̂��H
���厖
���������b�̏o���_��1500�n�͂ɐ��������_���J������Ώ\�l���ǐ�ɊԂɍ�������Ȃ����A�Ƃ����b������
����͂��蓾�Ȃ��i�h��Z�^���u���ۂɔ���Ă݂���v�����C�̒���������Ɣ����A�ꗶ���Ă��������j��
����Ȃ��̕����ڂ������Ƃ������Ƃ�
�q��95�ł���Ȑ��\�ɂȂ��A�Ƃ����̂͐����˂��g���Ă������ɂȂ��
���ې����˂Ȃ��������̂ʼn^�]�����������A�����̐U���ɖڂ��ނ��Ď��p��
���̌��ʁA�p�t�H�[�}���X�͉ΐ���Z�^�ƕς��Ȃ��Ȃ�����
������O�H�̉ΐ��ɑ�ւ��ꂽ�͉̂ΐ��̐��Y�͂��]���Ă������ƁA�_�D��Ƌ}篗��p�̉h���ʂɍ�炳�ꂽ�����̐��Y�̖͂�肪�傫��
>>995 �킩��̂́A�V�R�̐��\����ΐ���Z�^���x�i�����������n�͏o�Ă��������j�Ƃ������Ƃ��炢����
�܂��A�����ł��Ă��Ȃ������e�픭���@�̃J�^���O�l��������
����͖����A����͎��p�I�ƒf�肷��̂͂�������
�^�]�����̋�I���e�͍���̉ۑ肾���ǂ�
�������̂́A��̃J�^���O��̉ߋ����ɂ�������đ����̂̓o�J���Ă�Ƃ�������
�J��Ԃ�������ȉ^�]�͑����ɒ��߂��Ă�
�ΐ��̃{�A�X�g���[�N�g������悩�����̂ł͂Ȃ����H
>>990 �h�͏����ł��g���ł��Ȃ����G���W���Ă킯����Ȃ����낤
�~�N�X�`���[�͍��x�ɂ���Ē������K�v�Ȃ��ljh�͏Ă��t���N�����Ղ��Ȃ�������
�I�[�g�~�N�X�`���[�t���ĉ����������Ă����̘b�Ŕn�͓�����̔R��Ɠ��e�ʐς�
�����̃g�b�v���x���������͂�
>>998 �@�ΐ��̃{�A�A�b�v�͂Ȃ��B�X�g���[�N�����͂܂����蓾�邩������Ȃ����c
���ɓ����̓��{�̌��E�l150mm�ɓ��B�A�����Ɠ������ɓ��ݍ��݂����B
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/army/1543328863/ �q���g�F http ://xxxx.5chb .net/xxxx �̂悤��b �����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��BTOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜 ���u�ǒn�퓬�@���d���̂V YouTube����>1�{ ->�摜>17�� �v �������l�����Ă��܂��F�E�y�ǒn�퓬�@�z���d���̂P�P �y�C�R�z�ǒn�퓬�@���d����4 �y�{���͍ŋ��H�z�퓬�@�@���d �y�{���͍ŋ��H�z�퓬�@�@���d���Q �y�쐼�z�ǒn�퓬�@���d/���d���@12 �y�鍑�C�R�z�k�d�@6���@�y�ǒn�퓬�@�z �y�鍑�C�R�z�k�d 7���@�y�ǒn�퓬�@�z �yJ7W1�z�k�d 13���@�y�C�R�ǒn�퓬�@�z �y�R���z�����퓬�@ �Ē�@�@�Ɉُ�ڋ� ���̋����X�Om ���V�i�C���[07/25] �E�[�}���E���{���A���{�ɂ��퓬�@�w���ᔻ�u���̊z����Δ�Вn�����̐����ɖ߂��v�@�l�b�g�u�h�q��͕K�v�����퓬�@���K�v F-16�퓬�@���u���邾���v�Ń��V�A�͖ق�I�H �E�N���C�i���^�ڑO �����ς����邻�̈Ӗ� [���܃J���p�`��] �y�R���z�����Ƃ̋���V�~�����[�g�A���̌��ʂ́u�Ȃ��ꂸ�A�㏸�ł����A�����Ȃ��v�c�ŐV�s�X�e���X�퓬�@�uF35�v�̏h���I���ׁ�2 �y�����z�X�e���X�퓬�@�u�r20�v�z���Łu���{���p�j�b�N�v�ƒ������A���̐^�ӂƂ�[12/11] �y�|�l�z�E�[�}�����{�@���{�ɂ��퓬�@�P���~�w����ᔻ�u���̊z����Δ�Вn�����̐����ɖ߂��v �y���ہz�|�[�����h�̃~�O�Q�X�퓬�@�A�S�@��ČR��n�ɔz���ց@���̌�E�N���C�i�ɑ����錩�ʂ� [�V���`��] �y���{�z�����퓬�@��2035�N�ɔz�����؍��l�b�g�͎��u���̍��؍��ł͂����Ɩ��l�l�H�m�\�X�e���X�퓬�@���o�ꂵ�Ă����v��3 [10/30] [�V��̃z�P������] �퓬�@���� �퓬�@�����}���X�̈ꕔ �̐퓬�@���ċ����́H �P���퓬�@����荇���L�� �퓬�@�ɂ��Č�荇���X�� �퓬�@�Ńt���A�o������ �O�HF-1�x���퓬�@�Ƃ͂Ȃ����̂� �؍��R�A���D�ɐ퓬�@�o�� ���̏����̐퓬�@�p�C���b�g�a�� �K���_���V���[�Y�ŋ��̐퓬�@��� F-15�n��퓬�@�����X���@54�@�� ������͐퓬�@�l�@�X���@733 �����y�[�W����ȂƂ���ɐ퓬�@���[�I �g�b�v�K���̑��҂̐퓬�@�͂r�t-35�� ������͐퓬�@�l�@�X���@728 �����̐푈�͐퓬�@���Q�[�����o�ʼn��u���� �؍�KFX�����X�e���X�퓬�@�@Part16 �؍��V�^�퓬�@ KF-21�@Part59 �؍��V�^�퓬�@ KF-21�@Part50 �؍��V�^�퓬�@ KF-21�@Part37 ������͐퓬�@�l�@�X���@740 ������͐퓬�@�l�@�X���@730 ���Ă�F35�퓬�@�����̋����P���@�O���n �y���ہz�� ��p�ɐV�^�e16�퓬�@���p�� F-35�퓬�@�A�u���b�N4�ő�Z����퓬�@�� �����̃��V�v���퓬�@�l�Q���m�ƒm�������� �y�ŋ��z���d/���d��23�y�퓬�@�z �y�ŋ��z���d/���d��22�y�퓬�@�z ���퓬�@�t�@���N���u�y�L100�z��^ F-15�n��퓬�@�����X���@52�@�� F-15�n��퓬�@�����X���@56�@�� F-15�n��퓬�@�����X���@53�@�� �y�ߕ�z�[�����X�L�[�u�퓬�@����v �y�ŋ��z���d/���d��27�y�퓬�@�z �y��p�z��R��F16�퓬�@���s���s���A���K�� �y�퓬�@�z���{���R�q���X�� ��s��4��� �yMe�zBf109 vs�@�뎮�͏�퓬�@�y�[����z ���q���e35A�퓬�@ ���[�_�[����@�e������ �؍�KFX�����X�e���X�퓬�@�@Part8 �؍�KFX�����X�e���X�퓬�@�@Part25 �y�ŋ��z���d/���d���@22�y�퓬�@�z �y���ہz�C�X���G���퓬�@���ė��A�V���A�ɋ� �y�L����͂ɁzJ���[�O�����X���y�V���퓬�@�z �y���_�z�{���A���d���R�~�ՁI ��7 �؍�KFX�����X�e���X�퓬�@�@Part17 �y����@���z�l���퓬�@����Part22�y���@���z �Đ퓬�@F-15�AF-16�Ɂu���͌����v���ڂ� �f�A�S�X�e�B�[�j�@�q�q��F-2�퓬�@����� �y����z�ߔe��`�Ŋ����H���@F15�퓬�@�̕��i������ F-35�ɏ���H �t�����X�ƃh�C�c�̎�����X�e���X�퓬�@
20:33:45 up 22 days, 21:37, 2 users, load average: 34.14, 18.10, 13.53
in 0.70863485336304 sec
@0.70863485336304@0b7 on 020510